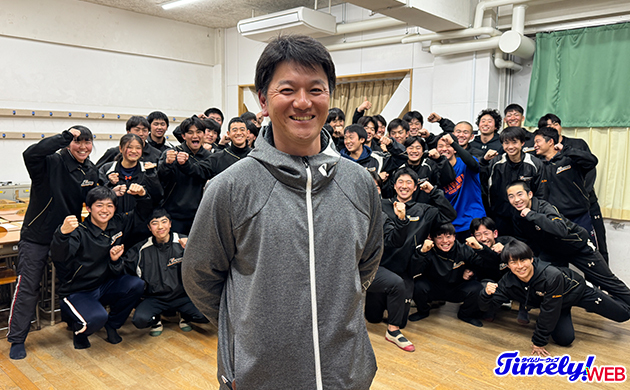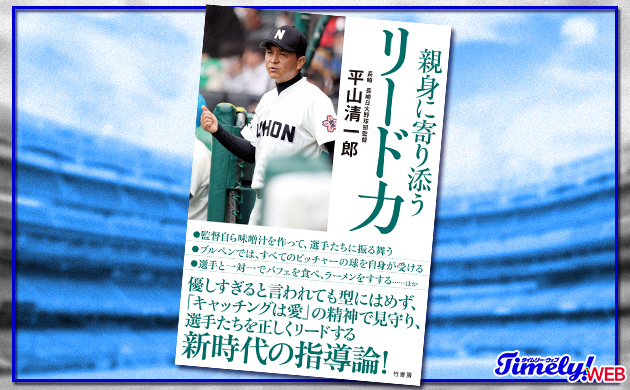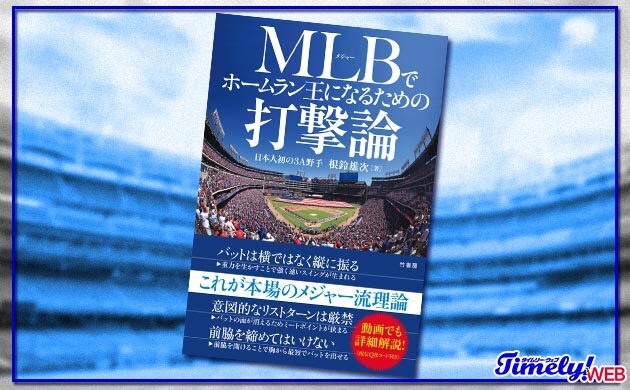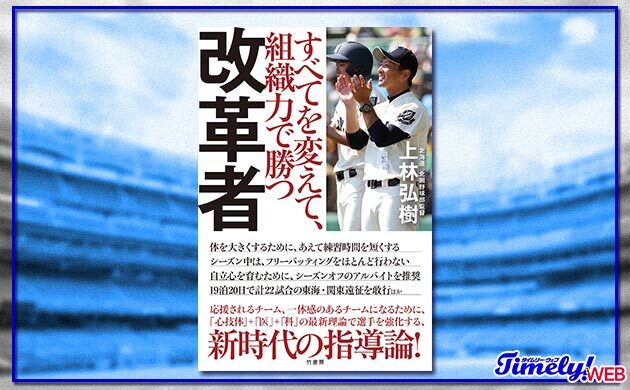〜第14回〜
交流戦を終え、オールスターが間近に迫った六月四週の金曜日。中六日での先発を任された火野周平は、マウンド上で珍しく表情を失っていた。
「ボール・フォア!」
審判がフォア・ボールを宣告し、投球を見送った打者が一塁へと歩いた。火野はしきりに右腕をぐるぐると回した後、気を落ちつけるためにか、念入りにロージンバッグに触れた。先ほど投じられたボールは、白鳥が外角に構えたキャッチャーミットとは真逆に、打者の背中を通過していった。初回からストライクがまともに入らず、八球連続のボール。キャッチャーの白鳥がタイムを要求し、二者連続の四球を与えた火野の元へと近寄って行った。
「おいおい、どうした。周平のやつ」
栗原監督がベンチで腕組みをしながら、マウンド上の火野周平以上に落ち着かない様子で戦況を見守っている。
「なんだか右腕を気にしているようですね」
栗原の傍らに寄り添うように立つピッチングコーチの今中が、不吉めいた指摘をした。
「試合前のブルペンではどうだった?」
「いつも以上にバラついていましたし、棒球でしたね」
栗原に試合前の火野の調子を尋ねられた控え捕手の笠松が答えた。
「立ち上がりの調子が悪いのはいつものことですけど、今日は相当に変ですね」
火野周平がセットポジションから九球目を投じた。手からボールが放たれた瞬間から、それと分かる大暴投であった。伸びあがって捕球しようとする白鳥を嘲笑うかのように、ボールは白鳥の遥か頭上を越えていった。労せずして一塁および二塁ランナーが進塁する。バックネットに当たって跳ね返ってきたボールを拾い、本塁方向に向き直った白鳥が大声で叫んだ。
「ホーム、カバー!」
火野周平は本塁へのベースカバーを失念したのか、投げ終わった後マウンド上から一歩も動かず、棒立ちになっていた。 この日、一塁を守っていた大ベテランの稲嶺がホームベースカバーに入っていたため、三塁ランナーがホームへ突っ込んでくることはなかったが、稲嶺の機転がなければ失点に直結していた公算の高い凡プレーであった。
火野周平はマウンド上で右肘を庇う仕草をした直後、両手を交差させバツ印を作ると、何かに追い立てられるかのように自らマウンドを降りた。普段であれば、栗原監督が降板を告げても、元来が投げたがりの火野周平は自らマウンドを降りようとはしない。それがこの日は栗原が降板を告げる以前に、あっさりと自らマウンドを後にした。火野の右腕に何らかの異変が生じたことは、誰の目にも明らかであった。
試合後、監督室に呼ばれた控え捕手の笠松は、無遠慮な調子で数回監督室の扉をノックした。
「どうぞ」
室内から、明らかに不機嫌な様子の声が聞こえた。敗戦に憤っただけではあるまい。火野周平が病院に運ばれる直前に漏らした言葉が、栗原を苛立たせていたことは明白であった。
「右腕に感覚がまったくないんです。自分の腕じゃないみたいに」
ベンチへ戻る際に付き添ったベテランの稲嶺が、周平がそう口にしていました、と栗原に進言していた。開幕から六連敗して一軍登録を抹消された世良正志に続き、目下五連勝と波に乗っていた火野周平までも登録抹消となれば、ローテーションの再編は急務であるだろう。
「検査では、異常等は見つからなかったらしいが」
医師からの診断書であろうか、机の上に手紙らしきものが置かれている。笠松が栗原の掛ける椅子の前まで近寄ると、
「どう思う?」
質問なのか、独り言なのか、どちらとも判別しづらい問いを投げかけてきた。栗原は苛立つと、余計な修辞が一切無くなる性質である。
「イップスではないかと思います」
――イップス。手足が痺れ、全身の硬直や震えが起こり、自分の思うように身体を動かすことができなくなる運動障害のことである。
「……そうか」
栗原が小さな溜め息を漏らした。
「長引きそうか?」
「症状によっては、引退を余儀なくされる選手もいます」
イップスは精神的な原因などにより発症するとされ、運動障害の原因となるような怪我や故障が認められない場合が大半である。
「自分も一時期、罹ったことがあります。盗塁を刺すために二塁ベースまでは放れるのに、ピッチャーまでは緩くしか返球できない。若い頃、そういう時期がありました」
「その程度であれば、騙し騙しでなんとかできそうだが」
栗原の言葉から一切の抑揚が失われていた。試合後の会見で垣間見せるいつもの快活さは、すっかり消えていた。
「ええ、投手の場合ですと話は別です。まともにストライクが入らないとなると、かなり長引くでしょうね」
栗原は椅子から立ち上がると、笠松の肩を軽く叩いた。
「笠松、頼めるか?」
「分かりました。自分に拒否権はなさそうですし」
くだけた口調で答えた笠松に、栗原は苦笑いで答えた。
「すまんな、よろしく頼む」
「ええ、よろしく頼まれました」
笠松が扉の方へと振り返った。
「周平は復帰を焦るだろうから、オーバートレーニングだけには気を付けて欲しい」
笠松は何も答えなかったが、栗原は構わず言葉を続けた。
「すぐサボる王子様の方は……」
扉の前に立った笠松が、栗原に向き直ると小さく礼をした。
「血反吐を吐くぐらいのスパルタで構わんぞ」
「了解しました」
笠松の気の乗らない様子の返答と共に、監督室の扉が静かに閉じられた。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら