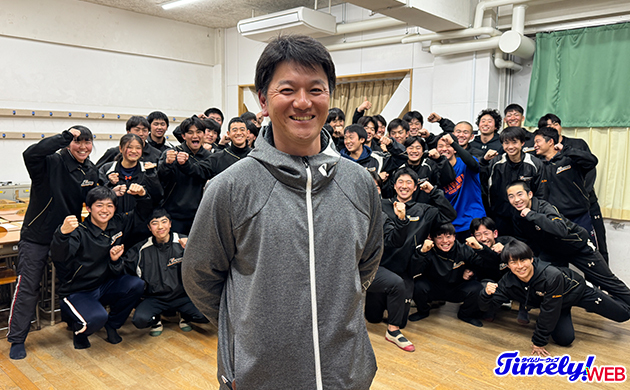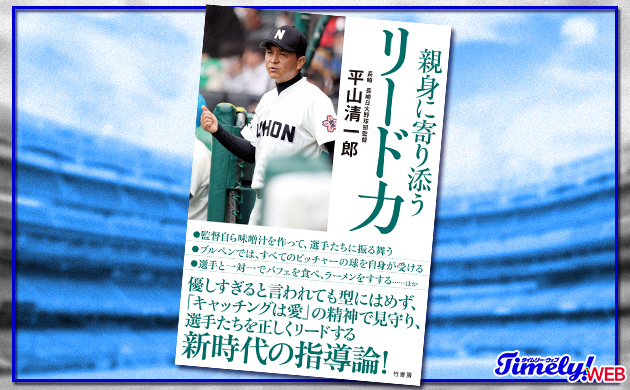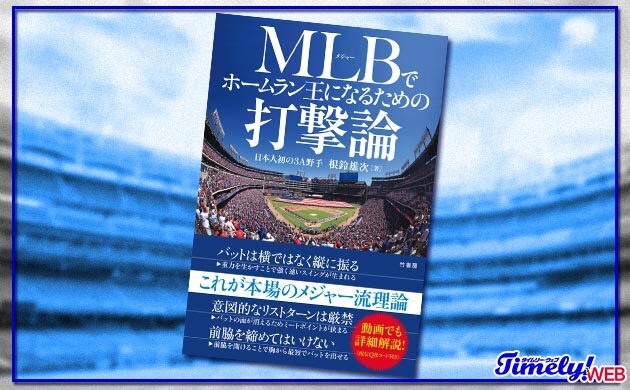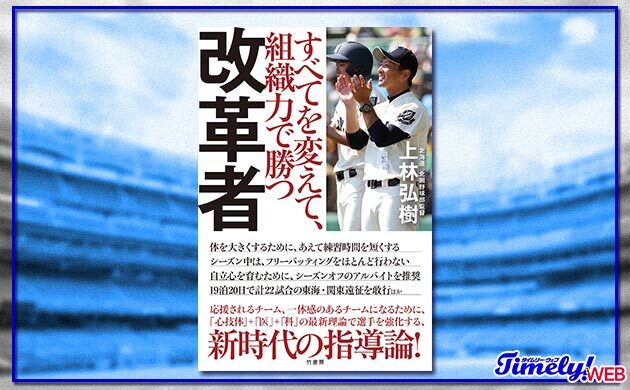〜第13回〜
六月三週の六連戦を勝利で締めくくったガンナーズの選手たちが、ぞろぞろとバスへと乗り込んでいく。
「ひのせんしゅー、サインくださぁい」
移動用のバスに乗り込む直前の火野周平にサインをねだる子供特有の甲高い声がした。タラップの二段目に足をかけていた火野は声の方向に振り向くと、ガンナーズのベースボールキャップをかぶった背の低い少年が小走りに近寄って来るのが見えた。アウェイゲームとはいえ、球団関係者か取材許可証を持つ人間以外は選手に接触できる機会は相当に制限されているのが普通だ。
「周平ちゃんは敵地でも人気だねえ」
外野手の松本が軽口を叩きながらバスに乗り込もうとしていたので、火野は先輩選手に道を譲るためにか一旦バスから降りた。少年にサインを書くつもりであるのか、ドアの前に立つ火野はすぐにはバスには乗り込む素振りを見せなかった。火野から数歩離れた位置に警備員が無言で佇んでいたが、「早くバスに乗ってください」とも何も口にしなかった。
警備員の視線の先には、談笑しながら連れ立って歩くスーツ姿の二人の男の姿があった。ピッチングコーチの今中と栗原監督の両名だった。警備員は帽子をとり、「お疲れ様です」と一礼した。火野周平も釣られて黙礼する。
「お荷物等ありましたら、荷台の方に積んでおきますが」
試合のデータの類であろうか、今中の持っている重そうな鞄を見て警備員が声をかけた。
「ああ、悪いね。ありがとう」
警備員は今中から鞄をうやうやしく受け取ると、バス後方のトランクを開けた。今中と栗原がバスに乗り込む。
「そうだ、周平。緋ノ宮学園の浅野監督から、お前と連絡を取りたいって球団に連絡があったみたいだぞ」
タラップから振り返った栗原が、バスの前で小さなファンを待つ火野に声をかけた。
「えっ、浅野先生からですか?」
火野の声は少しばかり上ずっていた。
「ああ、そうみたいだな。完封直前で打たれたりしてたから、詰めが甘いってご立腹なんじゃないか」
栗原の茶化す声は、勝ち試合の後ということもあっていつになく上機嫌に聞こえた。
「でも、先生から電話なんてプロになって初めてですよ」
「携帯は持ってないのか?」
「あっ、寮に置き忘れました」
火野は栗原を見上げ、申し訳なさそうに頭を掻いた。
「ホテルに帰ったら、連絡しとけよ」
栗原はほれっと、電話番号を記したメモ書きを火野に手渡した。
「はい、ありがとうございます」
火野はメモ書きを丁寧に二つ折りにすると、ズボンのポケットへと仕舞った。
背番号11「S.Hino」の刺繍のあるやや大きめのユニフォームを着た少年は、少し息を切らせながら火野の目の前に立つと、ベースボールキャップを脱ぎ、手にしたサインペンと一緒に差し出した。火野は少し身をかがめて少年の頭をぽんぽんと撫でると、ペンと帽子を両手で受け取った。少年に名を尋ね、さらさらと自らのサインを書きつける。
「あの、私にも頂けますでしょうか」
背後からくぐもった声が聞こえた。火野はちらりと顔だけを声の方向に向けると、少年の父親であろうか、特徴のない白いシャツに無精ひげの男がふらりと音もなく火野の背後から近寄ってくるのが見えた。少年と同じく、北海道ガンナーズの帽子をかぶっている。濃い色をしたサングラスをかけていたため人相はよく分からなかった。首から取材許可証らしきものをぶら下げていた。
「ちょっと待ってくださいね、順番ですので」
火野はサインを書きこんだ帽子を少年の頭にかぶせた。
「今日はお父さんと一緒に来たのかな?」
火野の問いかけに少年は大きく首を振った。
「ちがうよー、おばあちゃんといっしょにきたの」
少年は火野を見上げながら、嬉しそうな声でそう言った。火野が辺りを見回すと、杖をつきながらバスの方にゆっくりと歩いてくる老人の姿が見えた。
「ひのせんしゅ、どうもありがとう、ございました!」
ベースボールキャップに両手を添えて満面の笑みを浮かべた少年は、ぺこりと火野に向かって小さく礼をすると、老人の方へとスキップするように駆けていった。
少年へのサインが終わるのを待っていた男は、自身の横を走り去っていく少年には一瞥もくれず、ただただ火野周平の顔を見据えていた。
「火野選手にとって、浅野監督はどのような存在ですか」
無精ひげの男の目はサングラスに隠れて見えないが、その声音にはどこか探るような色が混じっているようであった。サインを記す間に投げかけられた質問からして、サインを蒐集するファンというよりは、報道陣のインタビューの一環であるかのようである。
「先生は、俺をプロに導いてくれた恩師です」
火野はサイン色紙に淡々とペンを走らせながら、答えた。
「教え子の活躍、先生もさぞお喜びでしょうね」
男の低い声は、言葉とは裏腹に、称賛ではなく嘲笑に近い色を帯びているようであった。
「お名前はなんと書きますか?」
「片仮名で、デザインベビーと書いて頂けますか」
「……は?」
火野はサイン色紙から男へと視線を移す。男の口の端がわずかに上がっていた。火野周平は言われるままの名を色紙に書き込み、男に手渡した。
「いえ、最近子供ができたものでしてね」
色紙を受け取った男は言葉を言い終える間もなく、踵を返しどこかへと歩み去った。
「失礼な男でしたね。一言ぐらい礼を言うべきでしょうに」
トランクに荷物を積んでいた警備員が、礼もなく歩み去った男の背中に向かってぶつぶつと文句を垂れている。
「それにしても、デザインベビーって何なんですかね」
「さあ、なんでしょうねえ」
しばらくの間、火野も警備員と同じく男の背を見つめたまま立ち尽くしていた。
「あ、警備どうもありがとうございました」
火野は去って行った男の背中から目を逸らし、バスへと乗り込んだ。
「今後のご活躍、期待しております!」
背中越しに警備員のよく通る声が聞こえた。バスのドアが閉まり、ゆっくりと発車する。火野が窓から外を眺めると、沿道に立つ警備員は直立不動の姿勢のまま、バスが走り去るのをずっと見送っているようであった。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら