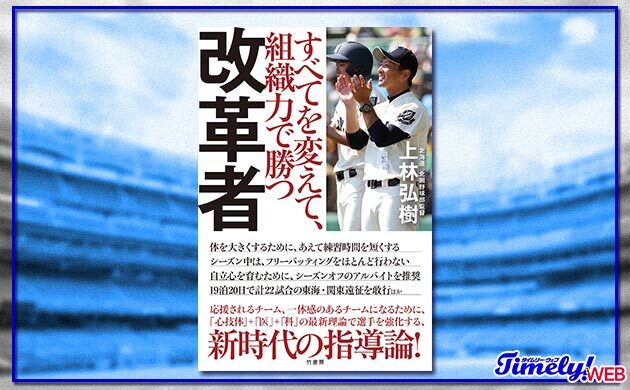==PICT-01==
〜第4回〜
かつて白球を無心で追いかけた母校のグラウンドに山口俊司は戻ってきた。
ただし、プロ野球選手としての華々しい凱旋ではなく、しがない一体育教師としてではあったが、とにもかくにも母校に帰還したのは紛れもない事実である。
光陰矢の如しとはよく言ったもので、気付けば私立緋ノ宮学園中等部を卒業してから丸十年、同学の体育教師となって早三年目を迎えていた。
今年から、中学生時代の担任であった小峰先生が受け持つクラスの副担任にもなった。なんとも妙な気分である。中学時分に二十代後半であった小峰先生を完璧にオッサン扱いしていた気もするが、晴れて自分もオッサンの仲間入りということだろう。
二十五歳になったかならぬかの体育教師など、たかだか十数年しか生きていない中学生共からすれば、迷うことなくオッサンの枠にカテゴライズするであろう。
二年二組と五組のニクラス合同の体育の授業で、男子生徒はサッカーに興じている。
昼食前の授業は全体的にちんたらとした雰囲気に覆われていた。試合に出ていない生徒は、全部で三段ある鉄製のバックスタンドにそれぞれにだらけた格好で腰掛けて試合を眺めている。
体育教師の山口俊司は、手持ち無沙汰にサッカーコートのセンターサークル辺りをうろうろしていた。審判とは名ばかりで、生徒たちが好き勝手にゲームを進行するので笛を吹く機会は滅多にない。せいぜいがゴールが決まった時と、反則時にコールするぐらいだ。
山口はホイッスルを首にかけて立ち、精一杯の恨み節を漏らした。
「俺が学生の頃は、でこぼこの土のグラウンドだったのに。何だよ、この恵まれた環境は。せめて俺が卒業する前に整備しろっての」
緋ノ宮学園の広大な敷地内にある第二グラウンドは、一面天然芝が敷き詰められている。
「喰らえ、シオン!」
7番のビブスを着た二組のチビッ子が、殺人スライディングだなんだとわめきながら五組のチビッ子に向かって滑り込んだ。背格好も、顔もよく似た二人。
おいおい、お前ら双子で潰し合うなよな。
スライディングを仕掛けた方のチビッ子は、ただ芝の上を気持ちよく滑りたいがために、蒸し暑い春の日差しの中で紺色のジャージを着ているのだろう。その見込みは半分成功したようで、双子もろとも折り重なって倒れ込んだ。
ボールには一切触れていなかったので、厳密に言えばファールである。いや、厳密にジャッジせずとも、誰がどう見たってファールであった。
「おい、霧島チビーズ。双子で削り合うなよな」
山口がファールの笛を吹こうとホイッスルを咥えた。
「あー、そいつショコと同じ組になれなかったから、僻んでんすよ」
前髪を垂らした二組の生徒が、山口がホイッスルを吹く前にさり気なくボールを前線へと蹴り込んだ。
「しれっと流すな、殿村」
「あ、バレました?」
殿村真は、小さく舌を出してからサイドライン方向へと逃げるように駆けて行った。とりあえず、笛を待つ気は毛頭ないらしい。
「ほんと、バスケ部は問題児ばっかりだな」
山口が溜め息交じりに呟くと、スライディングを仕掛けられて素っ転んだ方のチビッ子が「えっ、ぼくも?」とでも言いたげな、さも不本意そうな顔をしていた。
スライディングを仕掛けた方、霧島兄弟の兄・リオンは、芝生の上に気持ちよさそうに寝っ転がっている弟のシオンを尻目にさっさと立ち上がると、前線へと風のように駆けて行った。パスをくれだのなんだとの、ぎゃあぎゃあ喧しい。
「ウルせーな。どいつもこいつも」
それにしても、中学生の頃の自分はこんなにもアホであっただろうか。とりあえず黙ったままで、サッカーぐらい出来ぬものであろうか。
さり気なくゴール前に詰めていた殿村真が、ゴールネットを揺らしたようである。
山口がゴールの合図としてホイッスルを鳴らした。
霧島シオンは陽光に目を細めて、まだ芝生の上に寝転んでいる。
立ち上がる気は更々ないらしい。まさしく猫のお昼寝か何かのようであった。
「ほんっと、自由だな。お前ら」
それもまあ、緋ノ宮学園の校風を鑑みれば無理からぬところではあった。山口は内心で苦笑する。なんだかんだで俺が中学生の頃と何一つ変わってねーわ。教師の指示を律儀に仰ごうとするお行儀の良い生徒など、緋ノ宮に生息してるわけねえよなあ。
ましてや、体育の授業など無法地帯に等しい。ベテランの体育教師ならいざ知らず、三年目の若輩である山口などは、先生というよりは、少し年の離れたお兄ちゃん感覚である。
殊勝に山口先生などと呼ばれることはなく、ぐっさんだの、グッチーだのと呼ばれるのが関の山だ。良くも悪くも、生徒と先生との距離が近い。教わる側だった頃はそれが当然の環境であったが、こと教える側になると、それが相当に異常な伝統であったことを身を持って思い知る毎日であった。
生徒の誰ひとりとして「教師を敬う」というコマンドを一切持ち合わせていないという点については、どんなにぼんくらな教師であっても着任初日にして理解するだろう。
私立緋ノ宮学園は都内の高級住宅地に広大なキャンパスを持ち、幼稚園から大学までを擁する総合学園である。建学の精神を定めた教育四綱領のうち世間的に有名なのが「個性尊重の教育」であり、時の政権が全国的に「ゆとり教育」を導入する遥か以前から個性を重視したゆとりある教育を標榜している。
規律ある校則などとはほぼほぼ無縁にのほほんと育てられた恩恵からか、お坊ちゃまお穣さま然としたお気楽な自由人を数多く輩出するに至っている。
伝統ある緩い校風の賜物か、生来闘争本能に欠けた生徒ばかり集まる緋ノ宮学園高等部が七年前に二十八年ぶりに甲子園大会に出場したのは一種の奇跡と称された。奇跡には更なる奇跡が重なり、あろうことか甲子園を制してしまったという壮大なるオチもついた。
その奇跡のメンバーの中核を為したのが、母校の体育教師に身をやつした山口俊司と、大学進学後にプロ入りした世良正志の黄金バッテリーである。
グラウンドに四時間目の終わりを告げる鐘の音が鳴った。成人してから改めて聞くと、妙に懐かしい響きに感じるのは気のせいではあるまい。
ちらりと山口がバックスタンドの方を振り向く。
スタンドの上方に掲げられた時計は、十二時三十分を指していた。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら
PICK UP!
新着情報
-

【福岡大大濠】八木啓伸監督|試合に出られない者がいることを忘れてはいけない2025.6.25
学校・チーム -

【福岡大大濠】八木啓伸監督|大濠スタイルを一新させた浜地真澄の存在 すべてのきっかけは、2016年の夏にある2025.6.18
学校・チーム -

【書籍紹介】「熱中症を科学する スポーツの現場から見た、選手を守る最新の暑熱対策」2025.6.11
PR
-

高校野球界の監督がここまで明かす!守備技術の極意|岩井隆監督(花咲徳栄)2025.6.5
トレーニング -

【日大藤沢】山本秀明監督|大舞台、いつもの自分を信じきれなかったことから起こった失敗2025.5.28
学校・チーム -

【日大藤沢】プロ注目の遊撃手・半田南十、武器は感覚の良さと対応力2025.5.20
選手
-

高校野球界の監督がここまで明かす!守備技術の極意|小牧憲継監督(京都国際)2025.5.8
トレーニング -

高校野球界の監督がここまで明かす!守備技術の極意|野原慎太郎監督(横浜青陵)2025.4.28
トレーニング -

唯一無二のバットフィッティング Baseball Performance Lab2025.4.14
PR
-

メジャーリーグでのシェア率No.1!marucci & Victusでホームランを狙え!2025.4.14
PR -

糸井嘉男インタビュー|今だったら絶対アメリカの大学を目指す2025.4.4
PR -

高校生向け!根鈴雄次流MLBバッティング術2025.4.4
トレーニング
-

濱岡蒼太(川和)|甲子園出場が目標。そのうえでドラフト指名されるような選手になる2025.4.1
選手 -
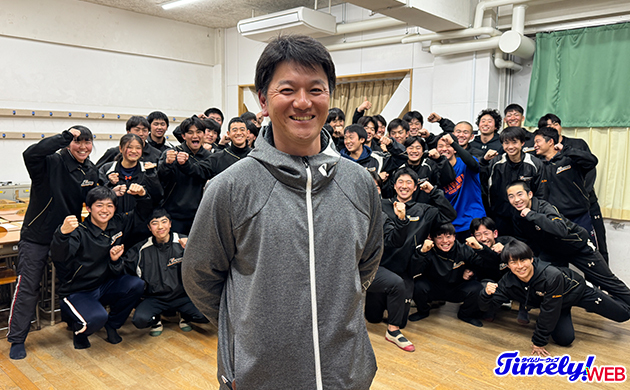
【川和】平野太一監督|野球への情熱、教員としての役割。ドミニカと大学院での学びと気付き2025.3.23
学校・チーム -

【書籍紹介】「高校野球界の監督がここまで明かす! 守備技術の極意」2025.3.21
PR
-
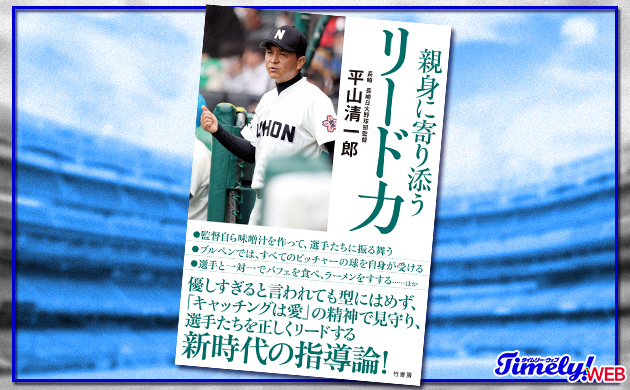
【書籍紹介】「親身に寄り添う リード力」平山清一郎(長崎日大野球部監督) 2025.3.13
PR -

【武相】豊田圭史監督|グラウンドの中では「昭和」、外では「令和」2025.3.1
学校・チーム -

【武相】豊田圭史監督|大学監督時代に学んだマネジメント能力の重要性2025.2.22
学校・チーム
-
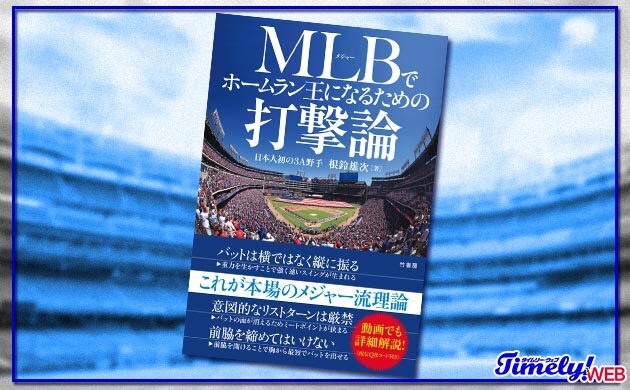
【書籍紹介】「MLBでホームラン王になるための打撃論」2025.2.17
PR -

【都市大塩尻】長島由典監督|特定の選手に頼らないチームづくり2025.2.7
学校・チーム -

【都市大塩尻】長島由典監督|自分の型に選手をはめようとし過ぎていた前任校時代2025.1.25
学校・チーム
-

【静岡】池田新之介監督|上手くなるコツがあるならそれはコツコツやること2025.1.19
学校・チーム -

【静岡】池田新之介監督|選手に教わった、歩幅を合わせる事の大切さ2025.1.7
学校・チーム -

【市立松戸】広瀬結煌|やらされているのではなくて、楽しみながらやっている2024.12.21
選手