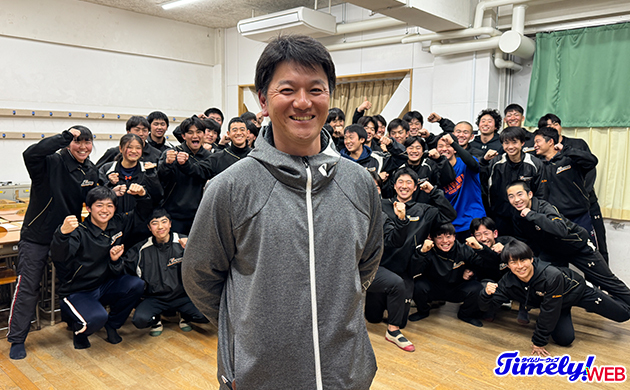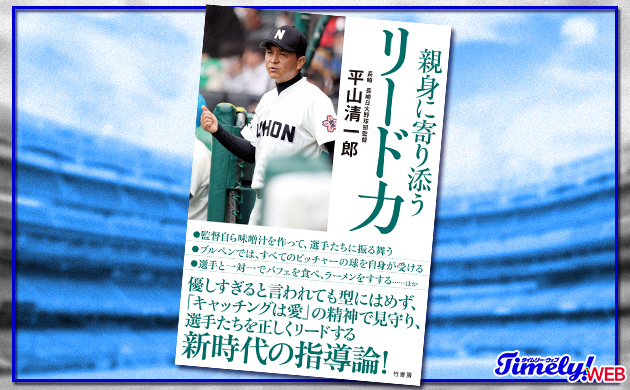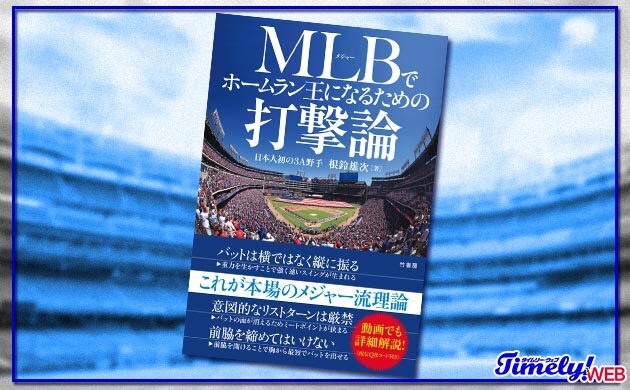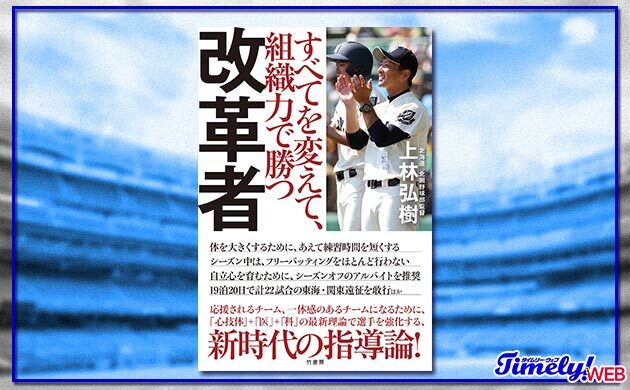〜第32回〜
緋ノ宮学園駅前から徒歩五分の場所にあるファミリーレストランのL字型の席で、山口俊司は霧島綾と内田真紀の二人に囲まれながら、浮かない顔で食後のコーヒーをすすっていた。傍目から見れば美女二人を左右に侍らせて大層よい御身分に映るだろうが、気分的には後宮に仕える宦官のそれであった。
「はい、真紀ちんパフェも来たよー」
山口は内田真紀が空にしたスイーツの皿を見つめながら、
「どんだけ食うんだよ、内田」
と小声で囁いた。テーブルの下で財布の中身を確認する。真紀は昼ご飯としてサーロインステーキと和風ハンバーグを平らげた後、デザートにタルトタタンとストロベリーショートケーキ、キャラメルのかかったパンケーキを胃に流し込んでいる。
「ご注文はすべてお揃いでしょうか」
ピンクの制服に白いエプロンの女性店員がホットファッジサンデーをテーブルの上に置き、追加オーダーの有無を問うた。
「あと、クリームあんみつ追加で」
内田真紀はホットファッジサンデーに細長いスプーンを突き刺しながら答えた。
「んじゃ、あたしコーヒーゼリーサンデー」
デザートメニューをめくっていた霧島綾もどさくさに紛れて追加オーダーする。店員は手に持ったハンディー端末のキーを叩き追加注文の品を入力すると、バックヤードへと下がっていった。山口は店員がテーブルの伝票立てに置いていった伝票を恐る恐る眺め、「破産だな」と諦めたような声を上げた。
「う? ヤマちんどしたの。浮かない顔だねえ」
霧島綾はコーヒースプーンで内田真紀の食べていたホットファッジサンデーの側面部を掠めながら、山口に話しかけた。お前らのせいだよ、とはさすがに口にしなかったが、山口は口元に引き攣ったような苦笑いを浮かべていた。
「例の強請り記者、捕まったんでしょぉ?」
「ああ。そうみたいだな」
山口はコンビニで買ったスポーツ新聞を広げながら言った。一面の見出しには「北海道ガンナーズ恐喝犯、銀座のクラブで緊急逮捕」とあった。
「あの川村ってエロ記者、そもそもなんで火野君を名指しで中傷したわけ?」
口の周りにチョコレートをつけた真紀が山口に尋ねた。
「エロ記者ね。たしかにマキコちゃんは災難だったな」
山口がそう冷やかすと、真紀がぎろりと睨んだ。マキコは真紀がクラブLに潜入した時に名乗った源氏名である。
「うっさいわね。もうそれ以上言わないでよ。ほんと、気持ち悪かったんだから」
山口の隣で「マキコちゃん、……ぷぷっ」と霧島綾が口元を押さえて笑っていた。
「うっさい! 何よ、あんたも『霧島綾に似てるってよく言われますぅ』とかなんとかノリノリで言っちゃってさ。私まで行く必要ぜんぜんなかったじゃないの」
内田真紀が霧島綾の方に一歩詰め寄った。
「いやいや、すべては親父キラーのマキコちゃんのお手柄だよぉ。……ぷぷっ」
霧島綾が腹を抱えて笑い始めた。間に座る山口が邪魔だったのか、真紀は綾をひとしきり睨むと、残ったホットファッジサンデーを抱えるようにして平らげた。
「ま、いちばんお似合いだったのは山口君の黒服姿よね」
「う、店長さんがぜひ転職しないかって言ってたお」
真紀が茶化すと、綾がついでのように転職を勧めてきた。
「考えとく」
山口は照れ隠しのつもりか頬をかいた。
「そういえば、川村が火野周平を貶めた理由だけど。このスポーツ新聞によると、球団が金の支払いを渋ったから、その見せしめだってことらしい。選手に手を出されたくなければ、金を払えってことなんだろうけど、そもそも球団がなぜ強請られていたのかについては触れられていないな」
山口がスポーツ新聞を丸めながら言った。
「えっ、副社長の不倫現場を押さえたってやつは? 川村にそのネタで強請られてるって、私クラブで聞いたわよ」
内田真紀が疑問の声を上げた。
「いや、その辺は特に何も書かれていないな」
「何よ、それ。隠蔽じゃないのよ」
真紀は半ば憤ったような口調になっているが、そこはいかんともしがたい裏取引というやつだろう。川村の逮捕理由は、表向きには銀座の某高級クラブの黒服の若い男の態度に苛立って、つい暴行に及んでしまったところをたまたま巡回中で通りかかった警察官が発見した、という筋書きとして処理されたらしい。
「ま、そのへんは葛ちんに頼めばいくらでも火つけてくれるでしょ」
霧島綾が笑いながら物騒なことを口にした。
「世良のいる球団だしな。世良が在籍しているうちは何もしないよ」
「わあ、ヤマちん大人ー」
綾がぱちぱちと乾いた拍手をする。
「ただ、火野への疑いはすぐには払拭されないだろうな。いちどあれだけ大きく騒がれたんだ。中身を斟酌せずに鵜呑みにしているファンだって少なくないだろう」
山口が心持ち神妙な顔つきになった。
「う?」
「遺伝子ドーピングがどうとかいう脅迫文章があっただろ。当の川村は、そんな文章は送ったことがないって突っぱねてるらしいからな。往生際の悪いヤツだよな。家宅捜査とかして、物的証拠が揃えば逃げ切れねえとは思うけど」
「球団を強請っていたこと自体は認めているのに?」
「ああ」
山口が伏し目がちに言った。山口がコーヒーをすすっていると、さっきとは別の店員がクリームあんみつとコーヒーゼリーサンデーを運んできた。
「ご注文はすべてお揃いでしょうか」
店員がマニュアル通りに問うた。
「はいー、大丈夫ですー」
綾が答えると、店員は追加の伝票を伝票立てに差し込みテーブルを離れた。
「すべてお揃い、……じゃないのかもしれないな」
山口がぽつりと小さく呟いた。
「あり? ヤマちんも最後に何か食べたかったのかにゃ」
霧島綾が目敏く山口の呟きを聞きつけ、デザートのメニュー表を差し出した。店員を呼ぶコールボタンに手をかけている。
その目は「お店の人、呼ぶよ。呼ぶよ。呼んじゃうよ」と告げているようだった。
山口は慌てて首を振り、「いや、コーヒーのお代わりが欲しかっただけだ」と言った。緋ノ宮学園駅前のファミレスはドリンクバーではなく、店員がいちいちお代わりのコーヒーを注ぎに来るシステムである。
「うにゃ。それは気づきませんで」
霧島綾はそう言ってから、早押しクイズの要領でコールボタンをぱしりと叩いた。ややあってから、笑顔を貼り付けた女性店員が本日七杯目のコーヒーを注ぎに来た。かったるそうに片手でコーヒーを注ぐその目は「まだ粘るつもりかよ。早く帰れよ」と告げているかのように見えた。俺も女性店員の内なる声に全面的に同意を表明する。
俺も早く帰りてえ。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら