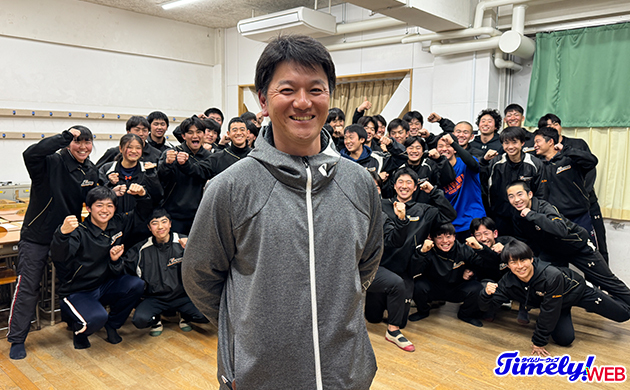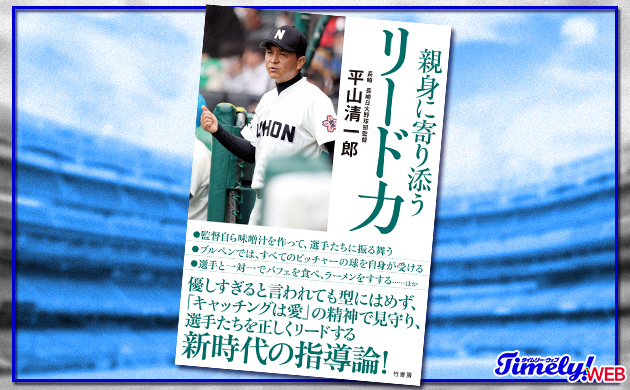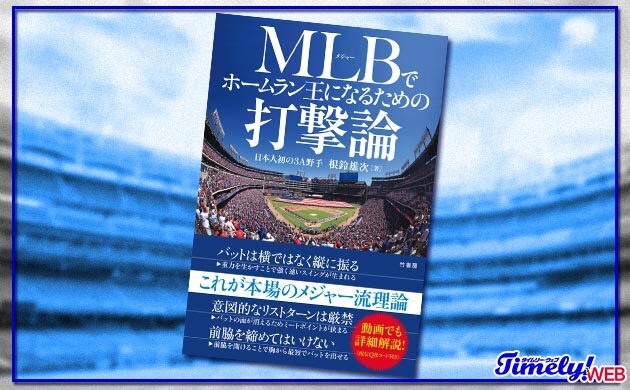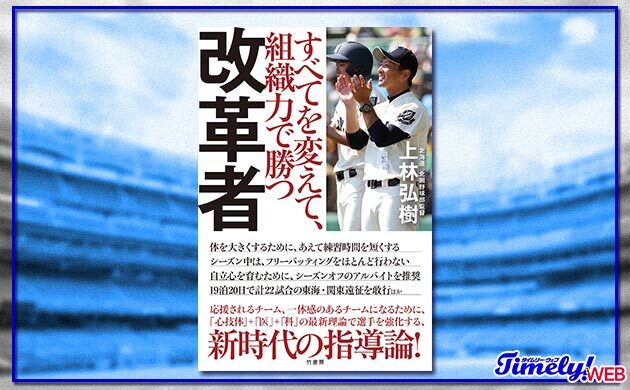〜第23回〜
千葉県鎌ケ谷市にある北海道ガンナーズの二軍本拠地、通称鎌スタは一軍登録抹消後の火野周平を一目見ようというファンでごった返していた。バックネット裏スタンドはすでに満席で、外野の芝生席は朝の満員電車を思わせるようなすし詰め状態だった。収容人数二千四百人のこじんまりとした地方球場に似つかわしくない大入りであった。
外野席には「お帰り、火野選手」「俺たちは周平を信じている」といった文字が掲げられた横断幕がそこかしこに踊っていた。火野周平は、芝目の美しいグラウンドの芝生を感慨深げに踏みしめていた。センター付近に立つ火野は、レフトポール近くに立つ世良に向かって山なりのボールを投げた。ボールは世良の待つ遥か手前で失速して地面に落ち、スリーバウンドして世良の足元へと届いた。世良は足元に転がったボールを拾うと、火野に向かって投げ返した。ボールは糸を引くような滑らかな軌道を描いて火野のグラブに収まった。
火野周平はゆったりとした動作で世良にボールを投げた。動作の一つ一つを確かめるかのようだった。すっぽ抜けたのか、ボールは三塁方向へと大きく逸れた。世良は慌てた様子でボールを追い、左手を伸ばして捕球した。投げ終わった直後の火野は首を傾げ、右肘のあたりをしきりに撫でている。茫然とした表情でその場に立ち尽くす火野は、投げ方を忘れてしまったかのようであった。
世良は火野の元に小走りに駆け寄ると、囁くような声で言った。
「周平、今日はこのまま上がろう」
火野は目を瞬くと左右に大きく首を振った。世良が困ったような顔をする。
「室内練習場で実践的に投げ込みたいんだ。目慣らしも兼ねて打席に立ってよ」
世良の提案に、火野周平は無言のまま俯いていた。
「投げられないって、辛いんですね」
ぽつりと、いつになく弱気な言葉を漏らした。
「俺、このまま野球できなくなるんでしょうかね。病院の先生もそんなこと言ってたし」
火野の呟きに今度は世良が沈黙する。
「右腕に感覚がまったくないんです。自分の腕じゃないみたいに」
どうやら火野は、診察にあたった主治医から、
「俗に言う投球イップスですね。心理的なものが原因であると思いますので、ある時ふっと治ることもあります。ですが、以前の競技レベルまで戻らない可能性もある」
と告げられたらしい。
「ともかく焦らないことですね。お大事に」
主治医からは、最後にそうも言われたそうだ。怪我でもないのに投げられないという状況が、プロ選手にとってどれほどの苦痛か。その心性を想像した上での言葉でないことだけは、隣で話を聞くだけしかできない世良の耳にも明らかであった。
「投手はともかく、打者ならできるだろ」
低くて細い声が聞こえた。火野周平と世良がお互いに顔を見合わせ、声のした方向を向いた。だらしなくユニフォームを着こなした笠松の姿があった。
「世良は投げ込みたいんだろ? 火野も少し付き合いな」
笠松が顎をしゃくる。室内練習場に移動しろ。そんな合図に見えたのか、火野と世良は三塁側ベンチに向かってゆっくりと歩く笠松の後ろを慌てて追った。グラウンド中央では球団マスコットの小熊のカルビンがバク転と怪しげなダンスを披露し、観客席から喝采を浴びていた。
「笠松先輩、なんで二軍にいるんですか」
笠松に併走した世良が問うた。
「ローテーションからいきなり二枚ピッチャーが消えたからな。二軍(した)から投手を補充するために野手を落とした」
日本プロ野球機構が定める一軍登録選手の人数は二十八名、ベンチ入りが二十五名である。この二十五名のうち投手登録と野手登録の振り分けは球団の自由である。試合出場資格のないベンチ外の三名はローテーション投手の休養日や、次回登板に備える投手の調整日として割り当てられるのが通例だ。北海道ガンナーズは通常捕手三人体制であるが、投手陣が手薄になると捕手を二人体制にして、その分投手を二軍から補充することがあった。
「……っていうのが表向きの理由だな」
笠松がつまらなさそうに、そう言った。
「表向き?」
火野周平が不思議そうな顔をして聞き返した。
「本当の理由は」
笠松は、ベンチの上に置いてあったキャッチャーミットを掴む。
「ガキどものお目付け役だな、要するに」
笠松がガンナーズ#27の刺繍の入った赤と白のキャッチャーミットをぽんぽんと叩く。
「監視してねえとすぐサボる王子様と、ちょっと目を離すとオーバートレーニングする生き急ぎの若造が同時に二軍だからな。面倒くせえったりゃありゃしねえ」
そんな憎まれ口を叩くベテラン捕手の顔は、どこか楽しげだった。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら