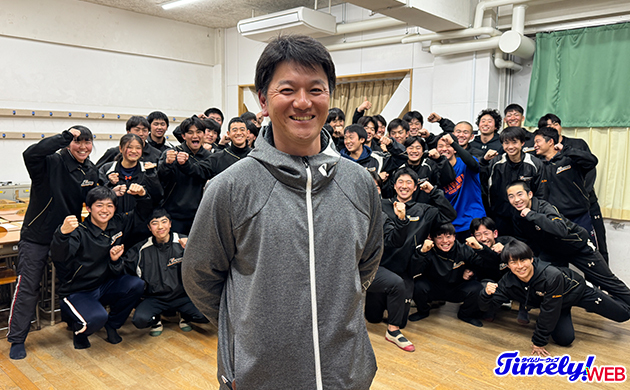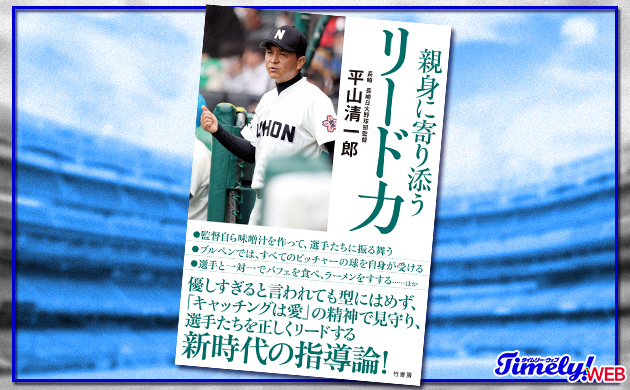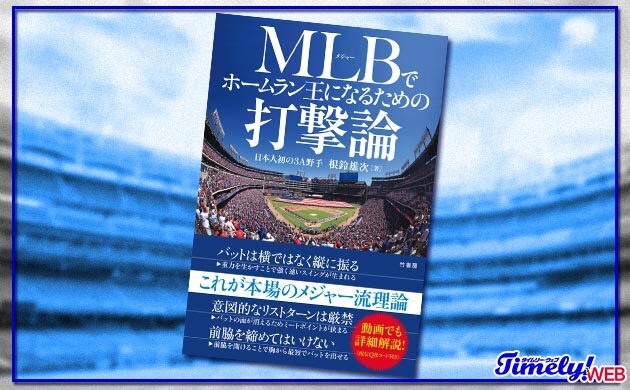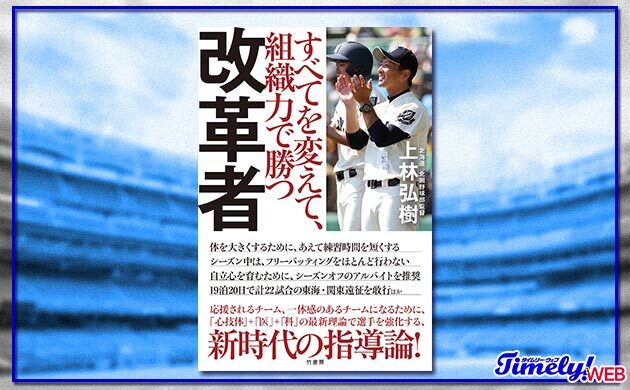〜第1回〜
七年前のあの日のことは、今でも鮮明に思い出すことができる。
対局後の棋士はすべての手筋を一手たりとも過たず記憶しているなどと言うが、あの試合に限れば、すべての配球とその意図を造作もなく列挙できるだろう。
甲子園球場のアルプススタンドは世紀の決勝戦を一目見ようという観客で埋め尽くされていた。うだるような暑い夏の日だった。内野席を覆う銀傘に、わずかに傾いた陽の光がじりじりと照りつけている。耳をつんざくような大歓声はいつの間にか止んでいた。
観客の視線はマウンド上のやや小柄な投手に注がれていた。
1番を背負ったエースはセンターバックスクリーンのスコアボードを振り返る。
九回裏二死走者なし。ツーストライク、ワンボール。スコアは四対三。緋ノ宮学園、一点リード。
相手チームのエース田仲将雄はタイムを解いて右打席に入り直し、バットを高く掲げて打つ構えを見せた。鬼のような形相でマウンド上のエースを睨みつけている。明らかに一発狙いだった。
前日に延長十五回を一人で投げ抜き、今日の引き分け再試合にも志願の先発で臨んだエースは、打ち気にはやる田仲とは対照的にどこか涼しい顔をしていた。
捕手の山口俊司がサインを出すと、珍しくエースは三度も首を振った。帽子を脱ぎ、息を一つ吐いて、右手で汗をぬぐった。一連の動作の後、改めてサインを覗きこんだ。
ああ、もうこの夢のような時間が終わってしまうんだな。
そんな感傷にでも浸っているかのような微笑を顔に浮かべて、エースはこくりと小さく頷いた。プレート上にすっと立つ美しい立ち姿は、どことなく神々しささえ漂わせていた。
決め球のサインが決まった。
「いいぜ、最後はもう見え見えで来い」
阿吽の呼吸。サインを通じて、何も喋らずとも意思疎通が出来た気がした。
サインを受け取ったエースはグラブを構え、投球モーションに入った。
まだ余力を残しているのか、左足がベルトの位置まで高く上がった。右腕が後方に引かれる。左足が地面に音もなく着地し、スパイクの歯が砂を噛んだ。右腕が鞭のようにしなる。指先で切るようにしてボールを押し出した。
途中までは糸を引くような直球の軌道だった。
だが、ボールはプレート上で小さく、鋭く落下した。長年バッテリーを組んできたが、今までに一度も見たことのない軌道だった。
田仲のバットが虚しく空を切る。
山口は一瞬不思議そうにミットを見つめたが、主審のゲームセットの掛け声を聞くやいなや、マウンドに向かって駆け出していた。
マウンドに駆け寄り、二日間で二十四イニングを一人で投げ抜いたエースを抱き上げた。華奢な身体は、全精力を使い果たしたかのようにふわりと軽く持ちあがった。
エースは空を見上げて、はにかむような笑顔を見せた。
山口俊司とエースの世良正志は、内野から、外野から、そしてベンチから集まる選手の輪に飲まれ、あっという間に揉みくちゃにされた。
試合終了後の整列が済むと、相手チームのエースである田仲将雄が、お互いの健闘を称えるためにであろうか世良に握手を求めてきた。田仲の大きな掌が世良の差し出した右手を強く握った。
「おう、プロじゃ負けねえからな」
その一言だけを言い残すと、田仲はくるりと背を向けてチームメイトの待つ三塁ベンチへと肩を怒らせてのしのしと帰って行った。山口の隣で世良は曖昧に微笑んでいた。
「プロ……か」
エースの小さな呟きを山口は聞き逃すことはなかった。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら