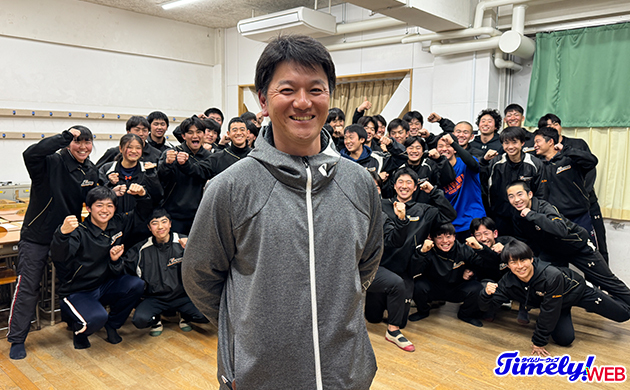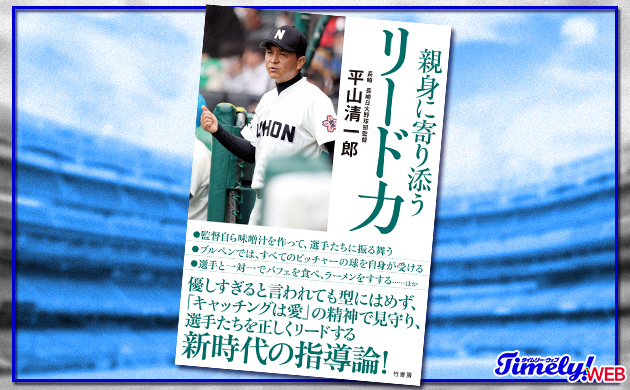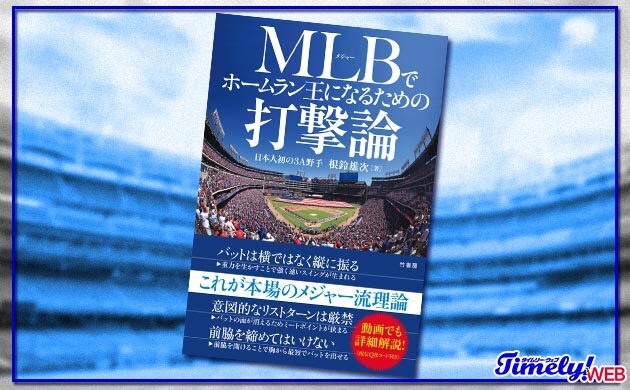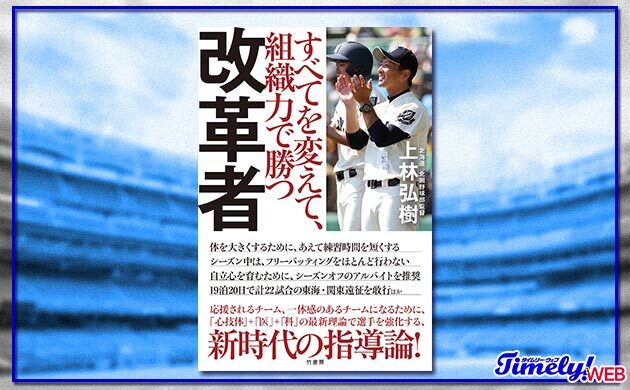〜第26回〜
緋ノ宮学園駅前のフランチャイズのコーヒーショップの奥まった席で、二人の男がひそひそと小さな声で会話を交わしていた。煙草の煙が充満する喫煙席に客はまばらだった。
「例の脅迫文の文章鑑定を三島クンに依頼しとる最中なんやけどな。文章の内容以前にいくつか不可解な点があるゆうてたわ」
「不可解な点?」
炎上マーケタ―葛原正人の中間報告に、山口が身を乗り出して聞き返した。
「せや。そもそもからしてメールの受け取り手がなぜ球団副社長だったのかっていう点や。球団自体を告発するのであれば球団の公式アドレス宛にメールが届くはずやしな。球団のトップを直々に強請るちうなら球団社長を真っ先にターゲットにしそうなもんや」
氷が解け、グラスの周りには水滴がついている。
「それが社長をすっ飛ばして副社長へ連絡を送っとるわけや。そんな芸当、社内で実権握っとんのは誰かを知らん外部の人間ができるとは思えへんわな」
「ああ。まあ言われてみればそうだな」
山口がどことなく感心したように頷いた。
「裏返せば、副社長の連絡先を知る立場にあった人物が怪しいちうワケや。可能性としては球団職員あるいは報道関係者、もしくは球団への出入り業者といったところやろな」
山口は黙って葛原の推論に耳を傾けていた。
「つーことで、提案なんやけど」
葛原がにたりと不気味な笑みを浮かべる。中学時代からほとんど変わらない底意地の悪そうな表情だった。
「副社長室に盗聴器でも仕掛けたろか? その場合、世良工作員にちょいと協力を願わにゃならへんけど」
「それは止めてくれ。露見した場合のリスクが大きすぎる。球団に楯突いたなんてことになったら、世良が球界から永久追放されかねない」
山口が懇願するように言った。
「どうせ戦力外なんやろ。だったら手っ取り早く、危ない橋渡ろやないか」
葛原は相変わらずにたにたと笑っている。
「もう一度だけ言う。盗聴だけは止めてくれ」
山口がそう言うと、葛原は「やれやれ」とでも言いたげなポーズを取った。
「クソ真面目なところは相変わらずみたいやね、ぐっさん」
葛原が名刺入れから一枚名刺を抜き取った。
「せやから、副社長がよく密会に使うてるらしい店を探っといたわ」
山口が名刺を眺めた。一切の自己主張が感じられないモノクロのシンプルなデザインだった。
「クラブL? なんだ、こりゃ」
「銀座にある高級クラブらしいで。北海道勤務のはずの副社長がここ数ヶ月、毎月第三土曜日に通ってる姿が確認されとる」
「お前、なんでそんな情報まで掴んでんだよ」
山口が呆れたような顔をして葛原を見返した。
「ま、炎上マーケタ―やし? 暇を持て余しとるネット民にエサを放れば、警察顔負けのローラー作戦ぐらいやらかすで。具体的なやり方は企業秘密やけどな」
葛原正人が勝ち誇るように言った。
「こっちの店なら盗聴オーケーやろ?」
葛原がにたりと片頬を歪めて笑う。山口は気を落ちつけるためにかコーヒーをすすった。
「学校教師の薄給で、銀座の高級クラブになんか行けるわけねえだろ」
葛原が人差し指を立てて左右に振った。
「いやいやいや。適材適所いいますやろ、旦那」
山口が首をひねる。
「霧島がおるやんけ。しがない細々女優が」
「……えっ、霧島が協力してくれるのか?」
山口が意外そうな顔をした。
「そらあ、もちろんやろ。霧島に聞いたら『えー、Lでしょー。女の子の友達がいっぱい働いてるよー。あとねー、店長もお友達ー』言うてたで」
葛原は胸ポケットから取り出した煙草に火をつけ、吸い始めた。
「まあ、今のところの捜査状況はこんな感じやな。副社長の身辺はもう少し洗ってみるわ」
葛原は紫煙を吐き出しながらそう言った。
「ああ、いろいろありがとな。……ありがてーんだけど、その、なんだ」
山口が言いにくそうに口ごもる。
「ん? なんやねん、ぐっさん」
葛原が不思議そうな顔をした。
「いや。なんか犯人探しがもはやごっこレベル超えててすげえなあ、って思ってな。本物の裏稼業じみてて、若干怖い気もするけどよ」
「一本いるけ?」
葛原が煙草を山口に勧めた。
「いや、俺は吸わねえんだ」
山口がやんわりと断った。
「ま、裏稼業かどうかはともかくやな。捜査方針に関しては、ぜんぶ三島クンの入れ知恵やけどな」
葛原正人が柄にもなく謙遜した。葛原が吐き出した白いもやのような煙草の煙が二人を包んだ。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら