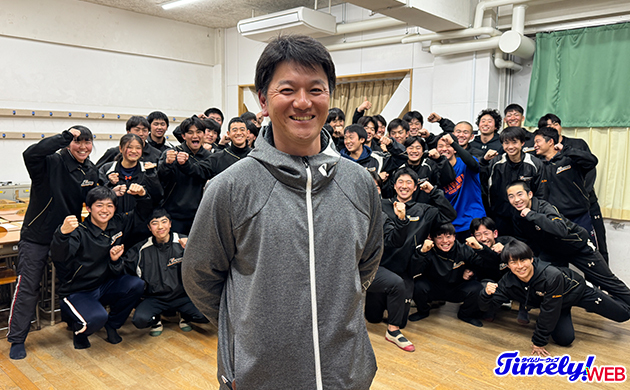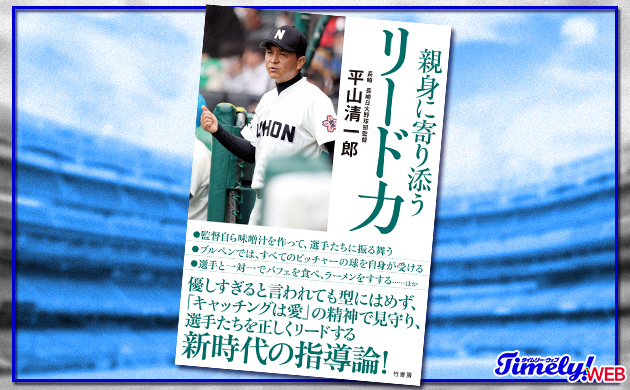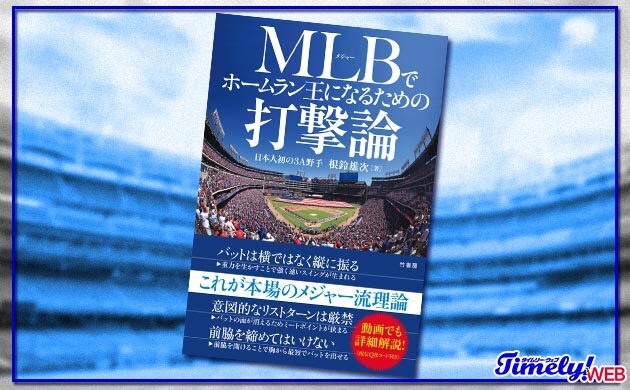〜第22回〜
「火野を貶めた犯人を捕まえたい。出来れば警察抜きで」
山口が淀みなく告げた言葉に葛原が吹き出した。
「そら難儀やで。なんでぐっさんが探偵ごっこしとるんや」
爆笑する葛原に「無理か?」と山口が一言だけ聞き返した。ぴたりと笑い声が止んだ。
「出来なくもあらへん」
葛原はきっぱりとそう言い切った。
「頼めるか? 男の依頼は受けねえみたいだけど」
山口は断られることを前提で聞いてみることにした。調査費用をどれだけぼったくられるかも想像がつかない。
「ええで。探したるわ」
あまりにもあっさりとした口調での安請け合いだった。山口は携帯電話を握りながら、面食らった顔になった。
「いいのか? お前、別に火野と知り合いってわけじゃないだろ」
「直接の面識はあらへんけどな。困ってる後輩がいたら助けてやるのは当然やねん」
あまりに葛原正人らしくない発言に、何か裏でもあるのかと訝ってしまった。進んで他人の役に立とうなどという仏心を毛ほども持ち合わせていない人間が口にすると、胡散臭いことこの上ない台詞だ。
「お前、妙に殊勝なこと言うようになったな。なんか変なもんでも食ったか?」
山口が本音をオブラートに包んで投げ返した。ひとまず様子見で牽制球を放ってみることにする。
「純粋なる善意を疑うもんやないで。ま、オレもぐっさんには借りがあるねん」
予想に反して、ど直球が返ってきた。虚飾に彩られた七色の変化球使いだったはずなのに、何が葛原をこうも真人間に変えたのだろう。
「……借り? 何かしたか、俺」
「せや、ぐっさんがオレを止めてくれなきゃ今頃殺人鬼になってたかも知らん。そらあ、あん時はムカついたけど、あれぐらいの荒療治が必要やったんやろ。おかげで目覚めたわ」
思い起こせば、あれは中学三年生の時の話だ。ざっくり言うと十年前。葛原正人が何を思ったのか同級生の三島シンジにバタフライナイフで斬りつけようとしたところを山口が軟式球を投げつけて制圧した、という事件のことである。
なぜあの時三島に刃を向けたのか。教室内に居合わせた誰もが理解に苦しんだ。だが、どんな衝動が葛原の胸の内に渦巻いたにせよ、級友を刺すことだけは誰かが止めなければならない状況だった。
山口はナイフを手にした葛原に一応の停戦交渉を試みたが、収まりがつかないのか交渉は不調に終わった。ならば仕方あるまいと、山口は日頃から所持していた軟式球を葛原目がけて投げつけた、という次第である。
ナイフの殺傷能力に比べれば遥かに穏当ではあるが、きちんとコントロールされた軟式球とて凶器の類には違いあるまい。どてっ腹あたりを狙ったはずが、図らずも顔面にクリーンヒットしてしまった点については若干の申し訳なさすら感じていた。
「そうか、目が覚めたか。そりゃ良かった」
らしからぬ謝意を口にする葛原に対して、山口はどこか歯切れの悪い返事をした。
「つーか、なんであの時三島を刺そうと思ったんだ?」
山口が何気ない口調で尋ねた。
「あれやで、尾崎豊も歌っとるやろ。窓ガラス壊してまわったとか、盗んだバイクで走りだすとか、要するに若気の至りちうやつや」
葛原がしみじみと昔を懐かしむかのように言った。はて、あの時の葛原少年は何から自由になりたかったのだろうか。中学生や高校生の頃の記憶は山口にとってはまだ日めくり一枚程度の過去でしかない。鮮明なままの当時の記憶をあれこれと探ってみるが、葛原正人がバタフライナイフを持ち出して三島シンジに斬りかかろうとした動機は今もって理解できずにいたが、それもそのはずだ。ナイフを持ち出した本人でさえその動機をきちんと把握していないのだから、傍目からその行動原理を理解できるはずもなかった。
「美しい記憶に水差して悪いんだけど、俺ら尾崎世代じゃねえから。それにバタフライナイフで斬りつけて……なんていう歌詞もねえ」
「ま、似たようなもんやで」
過去に自らが犯した凶事に一切拘泥しない様子の葛原は電話越しにからりと笑った。なるほど。校舎のガラスを割って歩くことも、盗んだバイクで走りだすことも、バタフライナイフで斬りかかることも、「あの頃は若かった」と魔法の言葉を唱えさえすれば、すべてが水に流れるらしい。
「とりあえず火野絡みの調査をすりゃあええわけやろ。なんか分かったら報告入れたるわ。連絡先は学生時代のと変わっとるけ?」
「いや、特に変わってない」
山口がそう言うと「そか。分かったで」との声が聞こえるや否や通話が途絶えた。実に慌ただしい電話だったが、どうやら犯人探しを手伝ってくれるらしい。変人の改心と、亡き尾崎豊に感謝せねばなるまい。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら