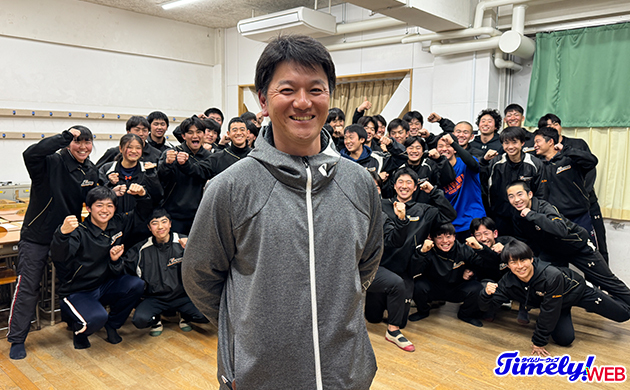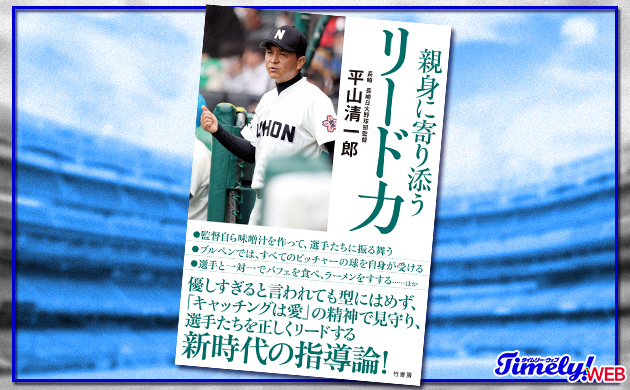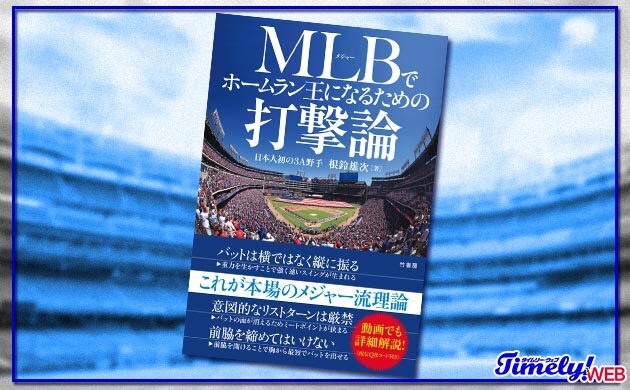〜第10回〜
「こちらでございます」
店員に芸能人のお忍びのような個室に通された。先客は小峰先生を含めて四名。
「おう、久しぶり。中学卒業からだと十年ぶりぐらいか?」
懐かしい顔が揃っていた。今日は小峰先生の三十九歳を一ヶ月遅れでささやかに祝う会、とのことらしい。連絡が来たのは昨日の深夜だったので、当然のように集まりは芳しくない。
集まる名目は中学時代の担任の誕生日を祝う会ということであったが、見た目よりも目端が利く小峰先生のことである。世良の二軍降格後、めっきりと口数の減った副担任を心配して、気分転換がてらに旧友との食事会をセッティングしたという可能性もある。
いや、さすがにそれは考え過ぎだろうか。恐妻の目を逃れて、たまには好き勝手に食事をしたいがための口実にされただけのことかもしれない。教え子との食事や結婚式への参加であれば、志乃さんのお許しが出るのだと、いつだったか聞いたことがある。
「で、こちらの美人さんはどなたでしたかな」
山口のとぼけた問いに、栗色の髪をした小柄な女性が答えた。
「あっ、ども。細々としがない女優業をやっております霧島と申しまあす」
「……いや、知ってるから」
山口は思わず、ぷっと吹き出した。霧島チビーズの姉、綾。たしかに、こうして見ると目鼻立ちがそっくりだ。
「変わらねえなあ、霧島も。お前が女優っていまだに信じられねえんだけど」
肩まで伸ばした黒髪の内田真紀が、それとなく肘でつついてきた。
「ちょっと、あんた。気をつけなさいよ」
「えっ、俺なんかヤバいこと言った?」
山口は目を瞬かせる。
「素直に美人なんて褒めると、霧島好感度メーターが止めどなく上昇中なんだからね」
あっ、そういうことね。納得した顔で山口はちらりと霧島綾の横顔を眺めた。
「いや、好感度大事っしょ。女優に限らず」
「付きまとわれるわよー。スネークよ、スネーク」
真紀は何やら手をうにゃうにゃとくねらせて、蛇の真似のような仕草をしている。
「えっ、スネークってメタルギアか?」
メタルギアは中学生時代に流行った、主人公のスパイが敵に見つからずに潜入するという斬新なステルスゲームだ。クラス内で攻略を競ったものである。
当時から学内最強の使い手は霧島綾だったことは言うまでもない。
「はあ、まーだゲームやってんのか。霧島は」
真紀は溜め息をつきながら言った。
「ま、ゲーム脳は相変わらずなのよ」
「で、内田は今何やってるんだ?」
山口の素朴な問いに真紀ではなく、霧島綾が答えた。
「真紀ちんはシャチョーよ、シャチョー」
「んな、良いもんじゃないわよ。こいつらのお守りよ、お守り」
こいつら、と複数形で答えた真紀の隣にはちんまりと三島シンジが座っていた。コーラらしき泡立つ黒い飲み物をちびちびと飲んでいる。アイスコーヒーでもなさそうだし、ラム・コークでもなさそうだ。酒、呑まねえんだな、三島は。
どことなく気配を感じさせないのは相変わらずだった。
「ちなみに、シンジ君は作家でありまあす」
なるほど、世間との接触を絶っても務まる職業を選択するあたりがいかにも三島らしい。かつての同級生が成功している様を見るのは、嬉しくもあり少々複雑でもあった。
「そういえば世良君は元気してる? なんか、戦力外通告って報道聞いたけど」
真紀がどこか言いにくそうにプロ入り後、鳴かず飛ばずの世良正志の近況を尋ねた。
「ああ、まだ戦力外って正式に決まったわけじゃないらしいんだけどさ。ちょっと前に会ったけど、やっぱりだいぶへこんでたわ」
「甲子園優勝したのにプロで活躍できないって、とんでもない世界なのね」
言いつつ真紀は甲斐甲斐しくサラダを取り分け、グラスが空くや追加のドリンクをオーダーした。なんて気の利くやつ。まさしく捕手の鑑。投手は一匹狼ないしはお山の大将という言葉が象徴するように、妙な拘りを持っていたり、極端な個人主義者が多いポジションである。対する捕手は、よく正妻という言葉をもって評価される不思議なポジションだ。目端が利いて、ピッチャーを自然と盛り上げるのが良いキャッチャーの必須条件だ。ときおり俺様なキャッチャーも存在するが稀だろう。
なんでもかんでも野球に例えてしまうのが俺の悪い癖だな。山口は内心自嘲した。
「世良はまあ典型的なお坊ちゃん育ちだからな。ガツガツ上を目指そうって闘争心に欠けるんだわ。なんせ、高校時代のあだ名は『ゆとりの国の王子様』だからな」
山口の発言に、大根サラダをつつきながら小峰先生が相槌を打った。
「緋ノ宮学園のゆるーい校風で育ったやつがプロ入りするだけ凄いけどなあ。プロはどうしたって個人能力値の勝負って世界でもあるしな。大変だろう、世良は華奢だし」
小峰先生の言う通りである。世良に田仲将雄や火野周平のような重戦車並みの身体と豪速球があれば、正直キャッチャーに頭は要らない。だが、世良のように球威で圧倒できない球質の軽いピッチャーとバッテリーを組む場合は、捕手のインサイドワークが何よりも重要だ。投手を生かすも殺すもキャッチャー次第というわけだ。
海を渡った田仲クラスともなれば捕手の水準に関わらず一定の活躍が出来るものだが、世良の場合はまた話が違うのだろう。事実、世良は三年経ってもプロの水に馴染めないでいる。好投したと思ったら、次の登板では滅多打ちにされるという不安定さに、世良本人はどれほどの歯痒さを感じているのだろうか。
炎上か、好投か。
どちらの目がでるかは、正直投げてみなければ分からない有り様だ。
「そう考えると、浅野監督はやっぱり名伯楽だったのよねえ」
七年前に世良正志と山口俊司の黄金バッテリーを擁して甲子園制覇を成し遂げた浅野監督は、高校球界には珍しい対話型の指揮官だった。「過去最高傑作」と名高い五学年下の火野周平は、監督の最後の教え子である。笛吹けど踊らない、闘争心に欠けた緋ノ宮の生徒を変革したのは、浅野監督の徹底した動機付けだった。
世良正志は監督に「とにかく勝ちたい」と訴えた。
火野周平は監督に「160kmを投げたい」と無邪気に言い放ったそうだ。
高校三年時に世良の宿願は最高の形で成就し、火野はプロ入り後一層の努力によって自らの目標を達成した。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら