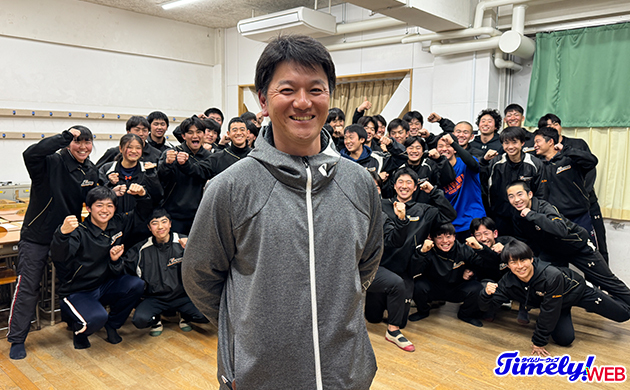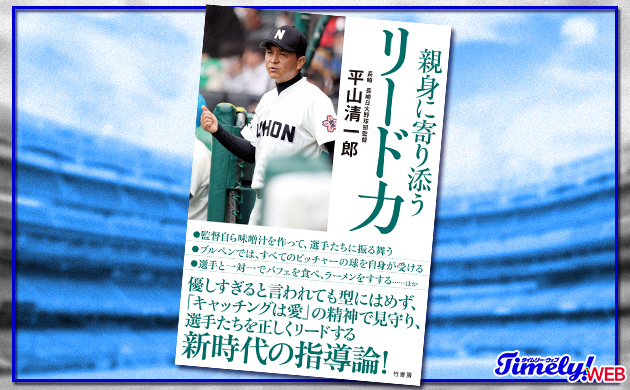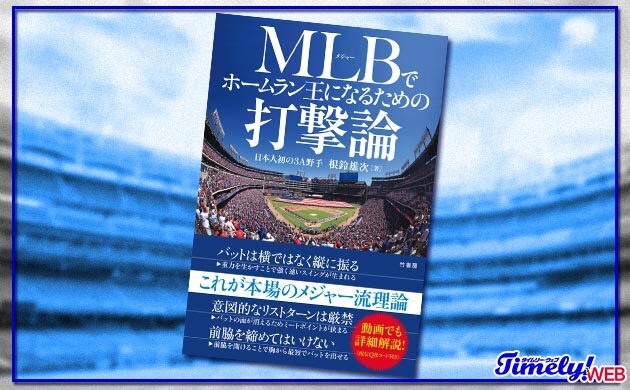〜第10回〜
数年ぶりに再会したかつての英雄の姿は、思っていた以上に色褪せて見えた。
高校時代からほとんど変わらない端正な顔立ち。だが、目の前に座る生気の感じられない青白い顔は、当時の精悍な面影を消し去ってなお、人生に苦闘している様子を窺わせた。
……まるで抜け殻だな。
七年前に甲子園を制し、一躍時代の寵児となったエースの姿は、残念ながらもうどこにもなかった。
あの焦がすような夏の日の記憶は今でも鮮明に思い出すことができる。七年前の甲子園大会決勝戦はまさに劇画のような展開だった。規定の延長十五回をもっても決着がつかず、翌日の再試合が決定。全二十四イニングを一人で投げ切った小柄なエースは、マウンド上で人目もはばからず号泣した。
キャッチャーマスク越しに見守り続けた在りし日の栄光の姿と、目の前の人生に疲れ切った男の姿をどうしても重ねることができないのは、きっと贔屓目もあるのだろう。
お前の才能はそんなものじゃないはずだ。たとえ世間がお前の存在を忘れ去っても、俺はまだお前の可能性を信じているんだからな。
そんな安直な励ましは実際に口に出す前に、吐く息に紛れて消えた。
冷めたコーヒーの隣に置かれたスポーツ紙の三面記事に『栗原監督連日の背信投球に大激怒! 世良、無期限二軍落ちが決定。今オフにも戦力外通告か』という文字が躍っているのを今朝がた目にしたばかりだった。くしゃくしゃに折り畳まれた新聞を脇目に見ながら、言葉の接ぎ穂を見つけるべく、ひとまず曖昧に笑いかけることにした。
甲子園を制し、大学野球でも華々しい実績を残した世良正志は満を持してドラフト一位でプロ野球界に身を投じた。一方の自分はと言えば、大学卒業後プロの選から漏れる始末。山口俊司は所詮エースの付属物でしかない、というのがプロ筋の共通見解だったようだ。
曰く、プロ向きの資質ではない。非情だが、要するに結論はそういうことらしい。
「プロ向きの資質」というものがあるとすれば、きっとこういう奴なんだろうなという標本が常に目の前にいたから、不思議と悔しいという感情は湧いてこなかった。それは端的に言って努力でどうにかなるような差でないことは、当時の自分にも理解できていたと思う。
三年前のドラフト会議の結末は、いまだに飲み込めたとは言い難い。
それでも、プロの選に漏れた悔しさと共に、若干の安堵を覚えていたこともまた事実だった。お前にはプロになる資格も才能も無い、だから野球以外の道を目指せ、と暗に諭されたような気もしていたからである。
一般人とプロになるべき選民との懸隔。
チームの勝利のために二日がかりで二十四イニングを淡々と一人で投げ抜いたマウンド上の傑物の姿は、今振り返るならば、プロの世界をきっぱりと諦めさせるに十分過ぎるほどのパフォーマンスだったように思う。
プロ野球選手になる道を志半ばで諦めた身となってからは、請われてプロの世界に身を投じた世良正志のその後の活躍を伝える報を心待ちにしていた。
だが、実際に伝え聞いたのは度重なる故障と不本意な投球内容であり、僅か三年の実働を経ての戦力外通告という名の最後通牒だった。
もちろんまだシーズン途中なので戦力外が確定した訳ではないだろうが、栗原監督の過去の用兵を考えてみても、無期限の二軍落ちの烙印から這い上がるのは望み薄と断じても差し支えないだろう。
数年の時を経て再び向かい合ったエースの消沈した姿に、なんの言葉もかけられないでいた。苦境のエースにひと声かけるのに気兼ねするなんて、バッテリーを組んでいた当時であれば想像すらしなかったことだった。
マウンド上の投手を勇気づけ、奮い立たせること。
それが捕手に課せられた最大の使命である。少なくとも、自分はそう信じて試合に挑んでいた。手負いのエースを励ませないなど職場放棄も甚だしい醜態であろう。
だが、今の自分の立場はもはや往時の捕手役ではない。単なる傍観者に過ぎない立ち位置にいる。その自分がどんなアドバイスをすればいいというのだ。
いったいどれほどの時を、沈黙が支配したか知れない。
注文したコーヒーはすでに冷めきっていた。不意にエースが重い口を開いた。
悲壮感を漂わせた雰囲気は相変わらずだったが、決意に満ちたような目に見えた。
「中学の野球部はどう? プロになれそうな子はいる?」
馬鹿言うな。お前みたいに、光り輝くような才能はそんじょそこらには見当たらないよ。
「ぜんぜん。俺たちの頃より酷いね」
生意気なやつばっかりだぜ。水原みたいなバカしかいなくて苦労してるよ。
それでもまあ、楽しそうにはやっているかな。
振り返ってみれば、俺たちの中学時代だって似たようなものだったよな。
「ヤマ、キャッチャーミットとか捨ててなかったんだね」
無理に軽口を叩こうとするエースに、心の中でこう答えた。
捨てるはずがあるもんか。あの時のミットは今も大事にとってあるよ。戻りたいと願っても叶わない栄光の日々を克明に刻みこんだ俺たちの記憶そのものだから。ただ、もう一生使う機会はないだろうとは思っていたけどな。
冷めきったコーヒーを一口すする。
砂糖を三つも入れたはずなのに、やけに苦い味がした。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら