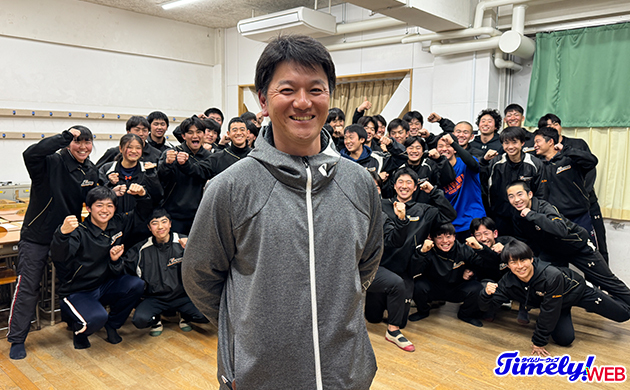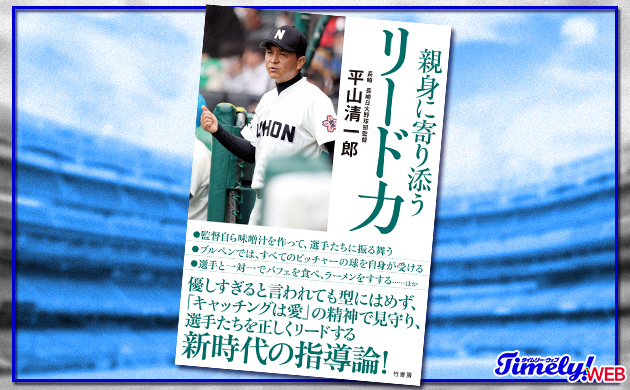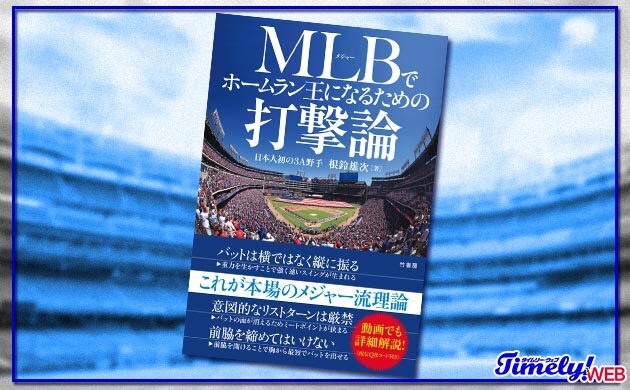〜第7回〜
背番号18は打球の行方を茫然と見送ると、マウンド上で膝に手をつき、硬直したかのようにしばらくのあいだ動けずにいた。
「潮時だな」
北海道ガンナーズの栗原監督はジャンパーに両手を突っ込んだまま、仏頂面で主審に投手交代を告げた。
うなだれてベンチに戻る世良に、ピッチングコーチの今中が声をかけた。
「後で監督室に出頭するように……だとさ」
ベンチに座る野手陣が世良に声をかけることはなかった。
三イニング持たずに炎上した世良とは視線を合わせようともしない。大差をつけられたベンチには、どことなく白々しい空気が流れていた。大勝した昨夜とは大違いだった。
世良はちらりと、無表情でベンチに座る栗原監督の横顔を覗き見た。
戦況が芳しくないと途端に口数が少なくなる癖がある。監督は先刻から、ベンチに備え付けられた置物であるかのように微動だにしていなかった。
どうやら口数が云々どころの騒ぎではないらしい。
世良正志はうなだれたまま、ベンチを後にした。
栗原監督が開幕投手に抜擢した大卒三年目の世良正志は、今季六試合に投げて0勝5敗と完全に期待を裏切った。25イニングを投げて18失点、防御率は6.48と散々の出来だった。未完のエースである世良が開幕からズッコけたわりに、北海道ガンナーズは首位と3.5ゲーム差の3位と決して悪くない順位にいる。
開幕から波に乗れない世良正志の穴を埋めたのが、高卒二年目にして覚醒した感のある火野周平であった。一年目の昨季は打者と投手を兼務する二刀流に挑戦したものの調整に戸惑い、打者として打率は二割三分、三本塁打、投手としては三勝というやや低調な結果に終わった。無論、高卒ルーキーであれば一年目から一軍の試合に出るだけで通常なら褒めるべきであろう。
だが、火野の抜群のポテンシャルを持ってすれば、打者ないしは投手どちらかに専念してさえいれば、もっと素晴らしい成績が残せたはずだという周囲の雑音は多かった。
二刀流などという珍奇な策は、目新しいことが大好きな栗原監督の玩具だと公然と批判する識者も少なくはなかった。
それが今季の火野は蓋を開けてみれば、開幕から破竹の五連勝である。同じ高校の出身で、同じドラフト一位、六歳年下の後輩が急激な勢いで伸びてくれば、先輩の世良が焦って調子を崩すのも無理からぬことではあった。
「お前もうかうかしてると火野に置いてかれるぞー。次、頑張れよ」
ピッチングコーチの今中が、音もなく歩み去ろうとした世良の後ろ姿に発破をかけた。声をかけられた世良は振り返り、小さく会釈を返した。
「置いてかれるどころか、もう違う次元でしょ」
世良の姿がベンチから消えたのを確かめてから、世良と同期入団の松本が軽口を叩いた。ドラフト六位指名の叩き上げで、今季から一軍に定着した外野手である。
「次があるといいんだけどな」
控え捕手の笠松がぼんやりとした口調でそう言った。
「ですよねー。ガンナーズのエースは、我らが周平ちゃんですからね」
笠松の独り言じみた呟きに、松本が嬉しそうに言葉を被せた。
「はいはい。そうやって同期のエリートを僻まない、僻まない」
「やだなあ、僻んでなんかないっすよ。俺だってちったあ心配してるんすよ。世良のことは。でも、あそこまで不調なのは、なんか原因でもあるんすかね?」
投手交代後の戦況を見つめながら、笠松が口を開いた。
「焦ってんだろ。妙に投げ急いでるから、重心が前に行くのが早くて、ボールに勢いが乗っていない」
笠松は至極一般的な回答をした。
「ふーーん。何に焦ってるんすか、世良の野郎は?」
笠松がまじまじと松本の顔を眺めた。
笠松は「それは本気で聞いているのか?」と言いたげな顔つきをしていた。
「そりゃあ160㎞を連発するような高卒新人が入団してくれば、同じピッチャーなら誰だって焦るだろう。むしろ、お前に恐怖心はないのか?」
笠松の問い掛けに松本は不思議そうな顔をした。
「え、俺すか? 俺、怖いもんなんかないすよ」
「ああ、そう」
セインツドームの歓声がぴたりと止んだ。
世良をリリーフした中継ぎ投手が、無難に後続を抑えたようである。
「うちの外野陣なんて、週二日か三日しかシフトに入れないアルバイトの高校生が一番打撃成績が良くて、特に正社員の松本君はあんまり働かないもんだからさ。もうちょっと焦りなり緊張感をもってやって欲しいよねー、って俺は見ていて思うんだけどさ」
笠松は中六日のローテーションの合間に、週に二、三試合程度を打者として出場する火野周平を「アルバイト」に例えた。打者として毎試合は出場しないので、パートタイマーだと言いたいのだろう。
「そうかそうか。松本君には追われる恐怖心はないのか。幸せなことだね」
対する松本は毎試合レギュラーで試合に出ているので、立場としては「正社員」ということになる。だが、実際によく働いているのはアルバイトの方だと笠松は主張した。
「かっさん、もしかして俺をディスってます?」
「今さら気付いたのか。そういうお気楽な鈍感力が世良にも必要なんだ。俺は俺だぜ、周りは関係ねーぜっていう感じのさ。良い意味での開き直りっていうのかな」
「やっぱり、俺を褒めてるじゃないすかぁ」
いやあ照れるなあ、と松本は頭をぽりぽりと掻いた。
先の文脈のどこに松本を褒める要素があったのかは不明だが、本人がそう解釈して気を良くしているならそれもそれでよかろう。笠松は松本との不毛な会話を中止した。
「お前そろそろ打席だろ。さっさと準備しな」
笠松はしっしと犬を追い払うような仕草をした。
「いや、もうツーアウトっすから。たぶん俺には回ってこないっすよ」
松本はベンチ脇に無造作に置かれた外野手用のグローブに手を伸ばす。
打席に入る気配は毛頭なく、チェンジ後に守備に就く準備を始めていた。
「まだ三回か。先、長えなあ」
笠松はベンチ内の誰にも聞こえないような小さな声で呟いた。
スコアボードは三回途中で一対八と表示されていた。
ガンナーズ七点のビハインドである。
「ああ、もうどうせ今日は負け試合だ。アルバイト君はお休みの日だし、正社員様も適当にサボればいいさ。シーズンは長丁場だ。先の無い高校野球とはそこが違う」
捕手として出場した際、キャッチャーマスク越しにぶつぶつと呪文のような小言を囁くのが笠松の癖だ。普段はわりと寡黙だが、試合の時だけは饒舌になるため球界では「お喋り将軍」という異名をつけられている。隣に座っていた松本が一瞬怪訝そうな顔をして、長居は無用とばかりに何も言わずに席を立った。
笠松はせめてもの暇潰しに世良の不調の原因を解析し、聞きとりづらい低い声でぼそぼそと呟いていた。無論、独り言である。
「プロ野球選手にとって重要なのは割り切りだ。諦めと言い換えてもいいかもしれない。自分の能力と折り合いをつけることもそうだし、自分の立場をわきまえることもそうだ。チーム内の誰かと能力を競ったってしょうがないんだ。自分の手持ちの能力で闘うしかないんだよ」
先発捕手の白鳥謙作がサードへのファールフライを打ち上げた。
「でも、そういうことは誰かが言ったって聞きやしないさ。自分で気付かなきゃ意味ないんだよ。万年控え捕手で引退間際のおっさんの助言など、聞きやしないだろうがよ。世良、お前さんの不調の原因はボールそのものじゃない。早くそれに気付け。そろそろ気付かないと、もう次はないぞ」
三回表のガンナーズの攻撃は三者凡退に終わった。
「ま、俺なんかがとやかく言うことでもないけどな」
笠松の呟きはセインツドームの大歓声によって掻き消された。
主審の「スリーアウト、チェンジ」のコールを聞くやいなや松本は左手にグローブをはめ、元気よくダグアウトを飛び出していった。
降板後、青ざめた顔で監督室の前を辞した世良正志は、視線を下げたままロッカールームに通じる扉に手をかけた。世良はちらりとあたりの様子を窺う。
中央通路にはいつものようにグラウンドに出ていない記者が何人かたむろしていた。
気軽な感じで談笑していた何人かの記者は、世良の姿を認めるとぴたりと話をやめた。
世良との間に見えない防御障壁でもあるとでもいうのか、誰も世良に近寄ろうとはしなかった。チラチラと窺うように世良を見て、お互いに意味ありげな視線を交わしている。
東京セインツの本拠地セインツドームの地下一階にある監督室はロッカールームの隣にあるが、直接繋がってはいないため選手がロッカーロームへ向かうには、いったん中央通路に出なければならない。その通路はマスコミの人間も往来が自由なので、何らかの取材がある際は試合中でもそうでない時でも、この場所で受けることになっている。
「世良選手、監督とはどのようなお話を」
取材許可証を首からぶら下げ、薄い色のサングラスをかけたスキンヘッドの男がロッカールームへ消えようとする世良を呼び止めた。岸田と名乗る古参の名物記者だった。
「次はない、と言われました」
世良は記者の方を振り向かずに短く答えた。
「後輩の火野投手に対しては、どうお思いですか」
迫力のあるだみ声には、わずかに笑みが交ざっているようだった。
「特に、何も」
悔しさを滲ませぬように短く言い残すと、世良はロッカールームへと姿を消した。
「いよいよ進退窮まったらしいな」
中央通路には、そう言って笑う岸田の場違いなだみ声だけが響いていた。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら