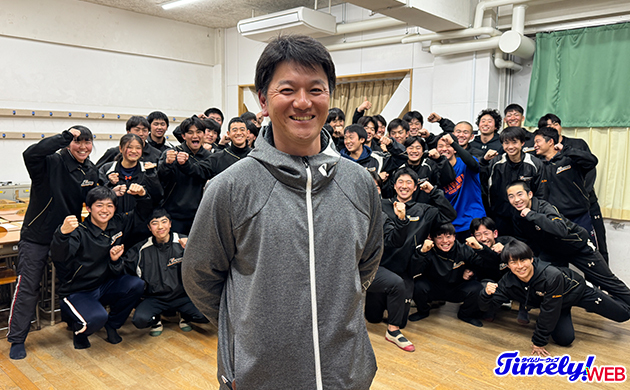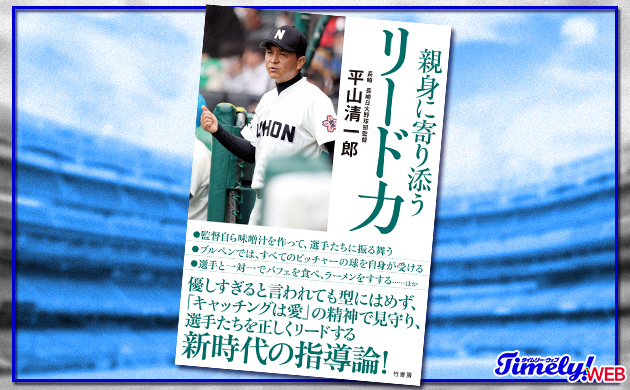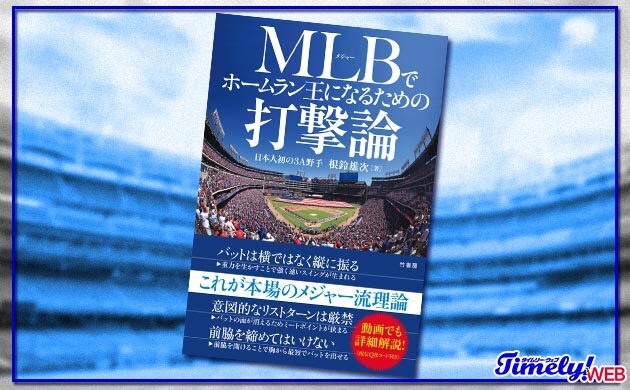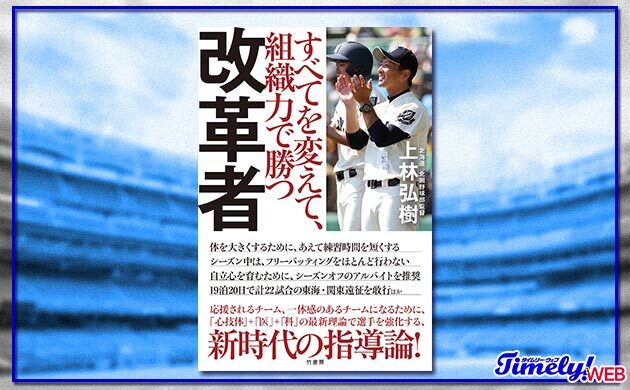〜第3回〜
職員室で愛妻弁当をつつきながら、小峰先生が山口に話しかけた。
「どうだったよ。本日の双子ちゃんは」
双子と言えば、もちろん霧島チビーズのことである。
「やっぱり兄は生意気ですね。弟の方は大人しくて、わりと可愛げがある気がします。体力ないのか、よく寝てますけど」
「ま、あれの弟だからなー。そりゃあ、似るよなー」
あれ。霧島双子の姉もまた、双子に輪をかけての問題児であった。
黙っていれば可愛い顔をしている、という評も姉弟で共通するらしい。
「ええ。あれの弟ですもんねー」
購買部で買った焼きそばパンをかじっていた山口は、ちらりと小峰の弁当を見る。
妙に小さな弁当箱に、山口であれば一口で食べられそうな量のご飯、卵焼き一つとプチトマト、ささみフライ二切れが詰められていた。赤、黄、白。色彩的なバランスは概ね申し分ないが、量はかなり控えめだった。
「だいぶ質素っすね。足りるんですか?」
「……ぜんぜん足らん」
小峰先生は不満げに答えた。
「志乃さんの愛を感じる弁当ですね」
小峰がじろりと恨みがましく山口を睨んだ。
「本心か、それは?」
「いや。……まあ、はい」
山口が言い淀む。どうやら虎の尾を踏んでしまったみたいだ。
小峰先生は養護教諭の旧姓緑川志乃先生と五年前だか、六年前ぐらいに職場結婚している。
元ヤンだの女番長だのと噂される女傑として名高い志乃先生の尻に敷かれまくっているらしい、とどこかで聞いた記憶がある。恐ろしくて、その先は聞いていない。
「まあ、いい。コロッケパンひとつで許す」
小峰はそう言うと、山口の好物のコロッケパンをひょいと取り上げた。
「……志乃さんに言いつけますよ」
一瞬、小峰先生の肩がびくりと撥ねた気がした。
「後生だ。見逃せ」
コロッケパンひとつ分のカロリーまでコントロールされているのだろうか、この人は。山口はかつての担任を憐みの目で眺める。
「そういや、世良はプロでだいぶ苦労してるらしいなあ」
小峰は弁当の量から話題を逸らしつつ、山口から徴収したコロッケパンを美味しそうにほおばった。小峰先生は食事に苦労なさってるみたいですね、とはさすがに言わない。
「基本のんびり屋ですからね、あいつは。ガツガツした上昇志向とは無縁ですし」
山口が言葉を返す。
「まあ、エンジンのかかりが遅いっていうのはあるでしょうね」
小峰先生はわずか二口でコロッケパンを食べ終えると、余韻を楽しむかのようにゆっくりと咀嚼している。名残惜しそうにパンの包装紙を見つめながら、小峰先生が言った。
「世良もまあ、高校三年になるまではパッとしなかったというか、ボンヤリしてたというか。最終学年になって自分がすべてを背負う立場にならないとモチベーションが沸かなかったとか、まあ、そんなとこか」
たしかに、高校三年生になるまでの世良はしょっちゅう風邪はひくわ、ランニングはサボるわ、筋トレはしないわで、あまり真面目だったとは思えない。それが、いったいどこでスイッチが入ったのか、高校三年時の甲子園大会だけはすべてが神懸かっていた。
ツボにハマった時はほんとうに芸術的なピッチングを見せる天才肌だった。
ただ、いかんせんヤル気に波があって、絶頂期は概ね三年から四年周期ぐらいなのである。頂点はたぶん高校三年の夏と大学四年だ。大学進学後の三年間は、高校時代の余技で凌いでいたようなものだろう。
大学四年間という時間で、甲子園決勝を争った田仲将雄のように別人のように逞しくなった訳でも、超人的な馬力を身につけた訳でもない。体型に関して言えば相も変わらず華奢なままだった。
腹周りだけに限れば世良よりも、余程小峰先生の方が成長している。いや、まあ小峰先生の場合は筋肉じゃなくて、全部贅肉なのだけども。
「何が違うんだろうなあ。プロに入って爆発的に成長するやつと、燻ぶるやつと」
「さあ、何が違うんでしょうねえ」
俺はプロにすら入れなかったので分からないです、とはさすがに女々しいので口には出さずに当たり障りない返事を返した。
「ああ、お腹減ったなあ」
小峰先生は、孤島に漂着した遭難者のような声を上げた。
「俺もさすがに焼きそばパン一個じゃ足らないです」
小峰先生の目がキラリと光った。
「……行くか、購買部」
「ええ、行きましょう」
世良にもこういう貪欲さの欠片でも欲しいよな、と山口は心の底で呟いた
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら