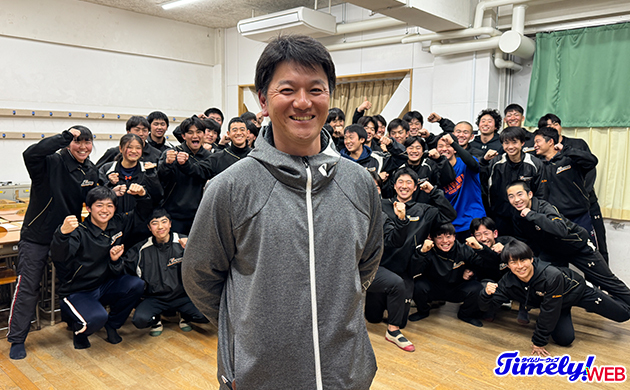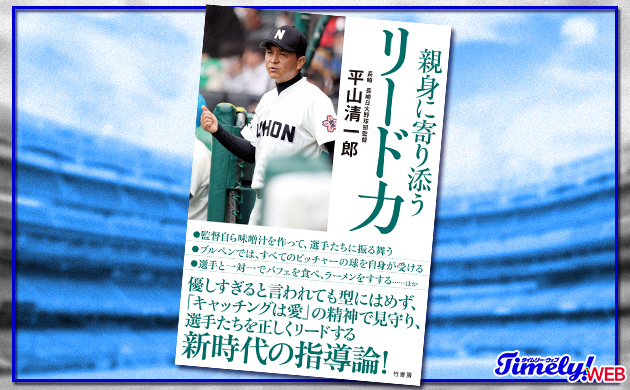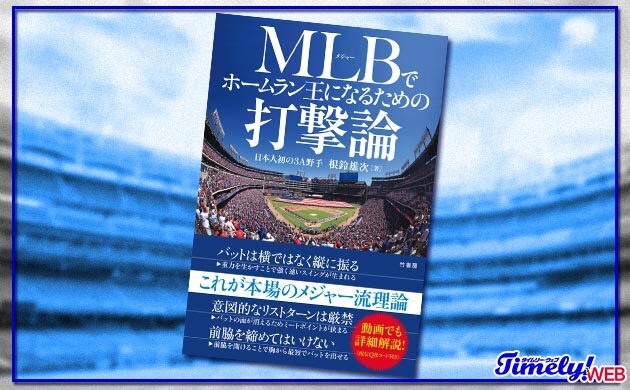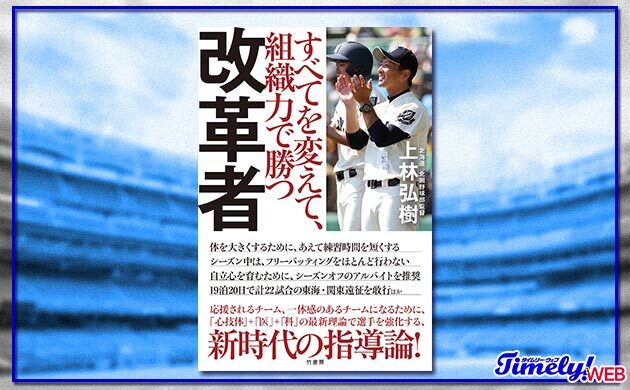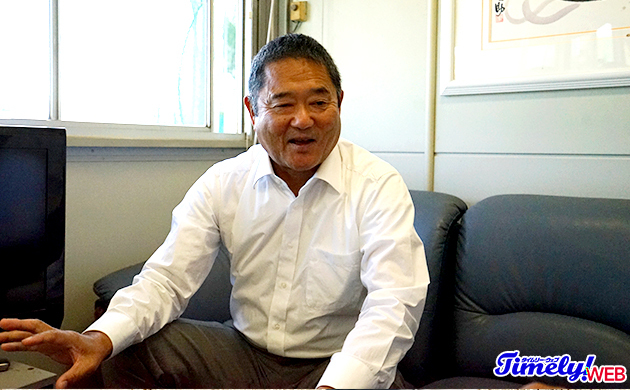
2009年夏の甲子園で母校である中京大中京を43年ぶりの優勝に導いた大藤敏行監督。前編ではそれ以前の失敗、後悔について紹介しました。後編では一度監督という立場を離れて気づいたことや、現在の指導に生かしていることなどを紹介します。(聞き手:西尾典文)
最後の最後の、最後までやり切らないと勝てない
——なかなか監督自身が自信を持つことができず、それが選手にも伝わって思った以上の結果が出なかったという反省があるというお話でしたが、このチームは自信があったみたいな年はなかったですか?
僕が中京大中京の監督になったすぐ後に商業科がなくなって、一気に部員数が減ったんですよ。ちょうど学校としても転換期で、大学進学に力を入れて、野球以外のスポーツも強化するタイミングだったんですね。理事長からも「向こう10年、結果が出なくても文句を言わないから我慢してくれ」って言われました。一番少なかった時は、学校全体で一学年200人切ったこともありました。
監督としてのスタートがそういう時期で、能力の高い選手が多いわけでもなかったんですよ。だから中京大中京で監督をしていた時にとんでもないピッチャーって1人もいなかったです。ピッチャーでプロに入ったのは深町(亮介/元・巨人)だけですね。その深町も高校時代は二番手でストライクもなかなか入らなかったですから。
——戦力的に今年は充実している、と思えることはなかったんですね。
言い訳になってしまいますけど、ずっとそんな感じでした。ただ反省なのはそういう中で、練習でやってきたことに対しても自信が持てず、弱気の虫が出てしまうというのはありましたね。
力のある選手が揃っていて、強いって言われているチームがコロッと負けることもよくあるので、自信を持つことと繊細にならないといけないのは表裏一体だと思うんですけど、だから監督というのは時には自分をだまして強気になったり、上手くいっている時には緻密になったり、そういう引き出しは必要だなと常々思いますね。

——お話に出た2000年や2004年は惜しい試合をしながら勝ち切れませんでしたが、そこから2009年の全国制覇に向けて変わった点や、反省を生かせたと思う点はどんなところにありましたか?
一つは監督しての心の持ちようですかね。「練習でやってきたことが全てなんだから、たとえ失敗しても思い切ってやろう」と思えたこと。
2009年に関しては春の選抜で負けたことが大きかったですね。9回ツーアウトまで報徳学園に勝っていて、そこからデッドボールぶつけて最終的にはサヨナラタイムリー打たれて負けました。その経験があったから、自分も選手たちも「最後の最後の、最後までやり切らないと勝てないんだ」というのを身を持って分かったので、練習での取り組みも変わったと思います。僕が言わなくても選手たちがそういうことを言うようになりましたからね。選抜から帰ってきて4月、5月、6月と夏までの約100日間の練習が本当に充実していました。全国には150キロ以上投げるピッチャーもいたので、マシンで170キロくらいのボールも打ったりして、やれることは全部やりました。
夏の愛知大会は準決勝まで全部コールド勝ちで、決勝も5対0で勝ったんですけど、優勝を決めてもピッチャーの堂林(翔太/現・広島)とキャッチャーの磯村(嘉孝/現・広島)が軽くグラブとミットをポンっと合わせただけで、全然喜んでなかった。それくらいやってきたことに自信があったし、甲子園出場を決めただけでは喜べないくらいの意識に選手たちが自然となっていたんですよね。
甲子園では菊池雄星(花巻東/現・ブルージェイズ)や今宮(健太/現・ソフトバンク)など、いいピッチャーがゴロゴロいたので簡単に勝てるとはもちろん思っていませんでしたけど、甲子園で優勝するんだっていう気持ちで臨めたのは大きかったですね。そういう時はくじ運も上手く回って、いいピッチャーが疲れたタイミングで当たれたというのもありましたね。
——日本文理との決勝はおっしゃるような『最後の最後の、最後まで』という言葉を体現するような試合でした(9回に5点を返されて10対9で勝利)。
堂林も河合完治も怪我していたというのもあって、8回くらいからちょっとおかしかったんですよね。精神的にもやっとここまで来たという思いもあって、不安定だった。それでも勝てたから良かったですけど、優勝して帰ってきたのにOBには怒られましたからね(笑)。
ただ毎年毎年そこまで追い込めるかというと、そういうわけではないんですよね。やっぱり身を持って体験した悔しさがあるからできる部分もあるのかなと思います。