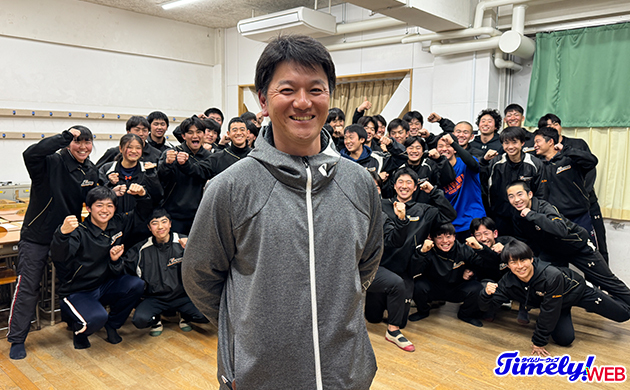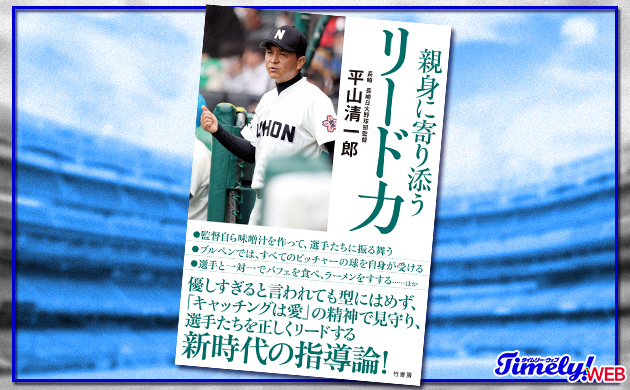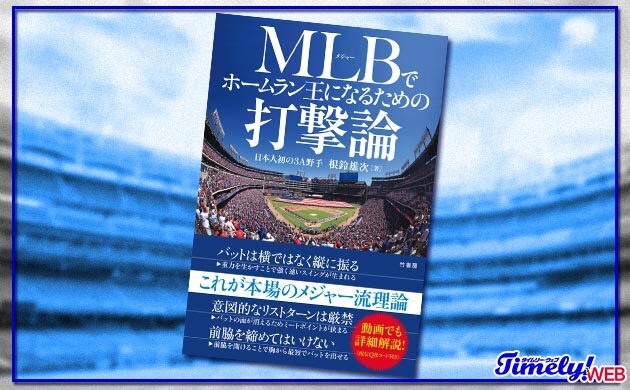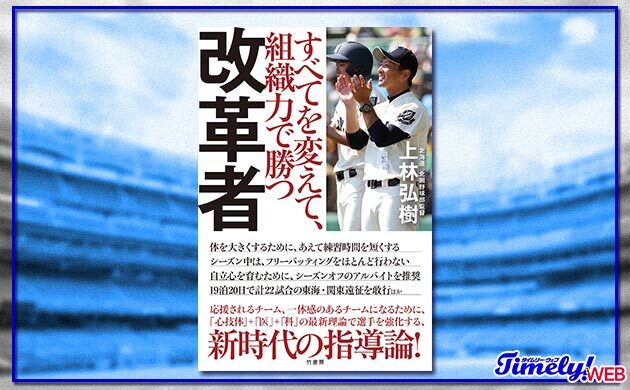〜第45回〜
「三番ショート水原」
ガンナーズドームにウグイス嬢のアナウンスが響いた。
右バッターボックスに入った水原隼人は、足元の土をスパイクで踏み固めた。白木のバットを高々と掲げて小刻みに揺らす。水原は鋭い眼光でマウンド上の火野周平を睨んだ。
「来いや、火の球ボーイ!」
バックネット裏に座る山口にも聞こえてくるかのような大声で水原隼人が吠えた。
相変わらずバッターボックスでうるさい。鳴り物応援にすら負けない騒音じみた遠吠え。負け犬はなんとやら、だ。
「水原、今度こそ空気読めよ」
山口は大舞台に立つかつての級友に向かって呟いた。
今シーズンの序盤、水原隼人は世良正志の二軍落ちを決定付けるスリーランを放つという前科を有している。ガンナーズファンに投票を募れば、抹殺リストの最上位にランクされることは間違いないだろう。天性の空気の読めなさは、他球団から見れば脅威の的だ。大人しくアウトになってくれそうな気がしない。
マウンド上の火野周平は横目でちらりと一塁ランナーを確認し、セットポジションに入る。小さなモーションから初球を投じた。水原が初球からバットを振り抜く。打球は痛烈な当たりとなって三塁線を襲ったが、わずかにフェアゾーンを外れた。
三塁塁審がファールを宣告する。
バックスクリーンの電光掲示板に火野の投じた第一球の球速が灯った。143㎞。最速から20㎞も遅く、ピッチングフォームには投球イップスに罹る以前の力感がなかった。
マウンド上で火野周平はわずかに首を傾げた。故障明けの復帰登板だ。感覚的にしっくり来ないのかもしれない。山口は、火野の動作に滲む焦燥を遠目から読み取っていた。
火野はロージンバッグをつけると、軽く手にふっと息を吹きかけた。マウンド上から捕手のサインを覗きこむ。水原はバットをゆらゆらと揺らしている。
火野周平の指先から閃光のようなボールが放たれた。二球目もストレートだった。
水原は微動だにせず見送った。主審がストライクをコールする。球速表示は160㎞と表示された。にわかに球場内がどよめく。
火野は捕手の笠松からボールを受け取ると、先の一球に納得したのか小さく微笑んだ。球場内に「あと一球」コールがこだました。
ツーナッシングから火野周平が投じた三球目は、ベース上でやや沈んだように見えた。水原は腰砕けのスイングとなったが、なんとかボールに食らいつく。打球はピッチャー前へのボテボテの当たりとなって火野の前に転がった。火野周平が難なくゴロをさばく。全力疾走する水原を嘲笑うように、火野は一塁へと糸を引くような送球を繰り出した。
ファーストを守るオルティスがミットを差し出す。火野からの送球を掴んだ……かのように見えた。水原が一塁に駆け込む。傍目には余裕でアウトのタイミングに見えたが、一塁塁審が大きく手を広げてセーフを宣告した。
どうやらオルティスがボールを取り損ねたらしい。電光掲示板にはE(エラー)の表示が灯った。ドームに失望の溜め息があふれた。
「オルティスの下手くそー! ちゃんと掴め、阿呆が」
山口の隣の席で葛原正人が大声で野次っている。それはガンナーズファンの誰もが思ったことだろう。一点勝負の展開でオルティスに守備固めを出していなかったのは栗原監督の明らかなミスだ。往々にして、こういう些細なミスが勝敗を分ける分岐点になるものだ。
山口は首にかけた双眼鏡を覗いて、一塁ベース上に立つ水原の表情を観察した。
「おいおい、水原の野郎。あんだけドン詰まりのピッチャーゴロ打っといて、ドヤ顔してやがる。……バカってすげえ」
霧島綾が山口の手から双眼鏡をひったくった。
「にゃはは、なにあれ。ムカつく顔ーー」
オルティスは火野を拝みながら、転がったボールを拾って火野へ投げ渡した。
火野周平はボールを受け取ると、ひらひらと手を振って答えた。
「パピー、気にしないでよ」
そう言っているかのような仕草に見えた。
「四番DH小笠原」
球場内にアナウンスが響く。
九回表二死一、二塁。一点差でチャンスに滅法強いベテランの強打者小笠原信彦を迎えた。DH制のないセ・リーグでは代打が主な役割となっていたが、日本シリーズではDHでスタメン出場している。小笠原が静かに左打席に入った。
ガンナーズドームが一瞬にしてぴりりとした緊張感に包まれた。
野武士を思わせる面構えと対照的な静かな佇まいに熟練の風格が漂う。
一塁ベース上にドヤ顔で立つ水原隼人があと十年ほど現役を続けたとして、こんな国宝級じみた雰囲気を身に纏えるものだろうか。いや、まあ無理だろうな。山口は脳内でその可能性をあっさりと否定した。打者としての格が違い過ぎる。事実、小笠原は五月の交流戦では火野周平の唸る剛球を一振りで仕留め、ライトスタンドに放り込んでいる。
小笠原は一球目のカーブを涼しい顔で見送った。バッテリーは意表を突いたつもりだろうが、わずかに内角低めに外れてボールとなった。
二球目はアウトコースに155㎞の速球が決まった。ワンストライク、ワンボールの平行カウントとなる。狙い球とは違ったのか小笠原は二球目も手を出さなかった。
バッテリー間で三球目のサインが決まった。火野は小さく振りかぶり、投球モーションに入った。左足が高く上がる。弓のように後方に引かれた右腕がしなる。放たれた剛球が小笠原の胸元を襲った。勝負球はインハイのストレートだった。初球の入り方と二球目の組み方に違いはあるが、山口の目には五月の交流戦を再現するかのような配球に見えた。
小笠原のバットが一閃する。目の覚めるような当たりが一塁線を急襲した。
小笠原はバットを放りあげると、一塁ベースに向かって走りだした。
山口が打球の行方を追うと、一塁塁審が両手を広げてファールのジェスチャーをした。
不格好な横っ跳びを見せたオルティスが悔しそうに拳を打ち付けている。
一瞬、状況が飲み込めなかった。あの悔しがりようを見る限り、オルティスは一塁ランナーの水原隼人が帰塁するまでフェアゾーンに打球が飛んだと思い込んでいたようだ。
小笠原は放りだしたバットを拾うと、バッターボックスにゆっくりと戻った。あと一球に追い込まれたというのに、あまりにも淡々とした足取りだった。
ヘルメットを目深にかぶった小笠原はバットを担ぐようにして構える。
バッテリー間で四球目のサインはなかなか決まらず、火野周平は五度も首を横に振った。
ちらりと一塁に視線を送った火野はクイックモーションで四球目を投じた。
途中までは糸を引くような直球の軌道だった。
だが、ボールはプレート上で小さく、鋭く落下した。
その鋭角な軌道は七年前のあの日、甲子園の決勝の舞台で世良正志が投じた一球に酷似していた。
実際にはただの直球だったのかもしれないが、山口俊司の目にははっきりとそう映った。
小笠原のバットはぴくりとも動かなかった。
主審は腰を捻りパンチを繰り出すボクサーさながらに力強く拳を突き出し、見逃し三振のポーズをとった。バックスクリーンに映し出されたリプレイ画像を見る限り、ストライクかボールか微妙な高さだったが、小笠原はストライクのコールに異議を唱えることもなく、何事もなかったかのようにベンチへと引き上げていった。
オルティスの横で、水原隼人が茫然とミットの中に収まった白球を見つめていた。
「あり? これで優勝?」
霧島綾の惚けた一声がドーム中の観客の声を代弁しているようであった。
ベンチへと引き上げていく小笠原の背中を見送った主審がゲームセットを宣告する。
火野周平は雄叫びを上げると、高々と右腕を突き上げた。二刀流の奇跡の復活劇としてはいささかいわく付きの幕引きとなったが、優勝のかかった大一番である。過程などもはや問題ではない。形はどうあれ優勝は優勝だ。
火野周平の喜びようは改めてそれを実感させるに十分だった。
一塁からオルティスがのしのしと火野の元に歩み寄った。捕手の笠松も火野の元に走り、ウイニングボールを火野の手に握らせる。内野から、外野から、ベンチからガンナーズの選手が飛び出した。背番号十八の姿も見えた。
のそりと勿体をつけて最後にベンチから現れた栗原監督の姿が全部で七回、宙に舞った。
「優勝のシーンを直接見るのはこれで二回目だね」
作家の三島シンジが感慨深げに呟いた。
三島の言う一度目の優勝シーンとは、おそらく七年前のあの日のことだろう。
「俺はバックネット裏から見るのは初めてだ」
山口は俯き、不覚にも目に伝う光るものをごしごしと拭った。
「あれぇ。もしかして泣いてるの、ヤマちん?」
霧島綾がチェシャ猫のような笑みを浮かべている。
「うるせえ。こっち見るんじゃねえ」
山口は左手で顔を覆った。右手でしっしと何かを追い払う仕草をする。
「ヤマちんさあ、選手としてあの輪の中に加わりたかったんじゃないの」
山口は霧島綾の問いには答えず、しばらく黙ったままだった。
「今日は母校の先輩がはるばる北海道まで応援に来てくれたので、どうしても抑えたかったです。途中バタバタしましたが、何とかなって良かったです」
ヒーローインタビューに謙虚に答える火野周平の顔がバックスクリーンに大写しになった。とそこへ、試合終盤のドタバタ劇を演出した張本人オルティスが巨体を揺らしながらのしのしとお立ち台に近寄ってきた。
満面の笑みを湛えながらずかずかと勝手にお立ち台の上に登り、火野周平の真横の位置に立った。公称193㎝、95㎞の火野周平と195㎝、110㎏のオルティス。デカいのとゴツいのが一緒に並ぶと、いかにもな威圧感である。
もう一人のヒーローとしてお立ち台の脇でちんまりと所在なさげな様子で突っ立っている世良の姿が微笑ましかった。
オルティスは火野周平と肩を組み、「俺にもマイクを寄越せ」というような仕草をした。パンツスーツの女性インタビュアーが慌ててオルティスにマイクを手渡した。
「シューへ―サンハ、ニホンイチノピッチャーヨ」
オルティスのたどたどしい片言の日本語にドーム内が沸いた。
火野周平の投手としての実力が現時点で日本一かどうかは不明であるが、今季の日本一を決める試合の最後のマウンドに立っていた火野周平は「2016年度における日本一のピッチャー」である、という意味として解釈すればオルティスの指摘は正しい。
山口がぼんやりとそんなことを考えていると、オルティスが二の句を継いだ。
「デモ、エースハセラサンネ」
茶目っけたっぷりの表情でオルティスがそう言うと、歓声に包まれていたスタンドは一斉に爆笑に包まれた。さすがに元メジャーリーガー。マイクパフォーマンスも達者らしい。
オルティスはそそくさとお立ち台から降りると、主を迎える執事かのように恭しくお辞儀をして、世良をお立ち台の上へと誘った。
火野周平はオルティスに倣うようにしてお立ち台から降り、王にかしずく従者のような面持ちで胸に手を添え直立姿勢を保持している。
いつだったか、作家の三島シンジは世良の後半戦の復活をして「忘れ去られた男が帰還した」と書いた。いかにも作家らしく、仰々しい表現だとその時は思ったものだ。
だが、目の前の光景はまさしく、忘れ去られた男が玉座へと帰還した瞬間そのものであった。
妙齢の女性インタビュアーにマイクを向けられた世良正志は、どこか気恥ずかしそうな顔つきでヒーローインタビューに応じていた。
「開幕からずっとボロボロでしたが、最後の方はちょっとだけですけど貢献できたかなあ、と。個人的には本当に帳尻合わせなシーズンでしたけど、優勝できて本当に嬉しいです。来年は一年通して活躍できるように努力したいと思います」
お立ち台の上で世良正志はそう語りつつ、はにかんだ。
緊張感から解放されたふやけた笑顔だった。やりきったという顔ではない。どこかに余力を隠し持っているような柔和な笑顔だった。山口が高校時代にマウンド上でよく見た顔だった。プロの世界に身を投じてからは、初めて見る表情でもあった。
「ファンの皆様、一年間、あっ、僕は一年間通しては闘っていないんですけど」
ごにょごにょと世良は歯切れの悪い言葉を紡ぐ。
観客席から大きな笑い声が漏れた。
「まあ、いいや。とにかく、一年間ご声援どうもありがとうございました!」
ガンナーズドームに万雷の拍手が轟いた。
世良はぺこりと小さくお辞儀すると、インタビュアーにマイクを返した。お立ち台を降り、小走りにチームメイトの待つベンチ前へと帰って行った。
ふと足を止めると世良正志はバックネット裏を見やり、拳を高々と突き上げた。
山口はそんな世良の一挙手一投足を金網の向こうから見守っていた。
かつての天才は、天才ばかりがひしめき合うプロの世界で凡人へと堕ちた。
往時の輝きを失った。再起不能。誰もがそう口にした。その主張は大筋では間違ってはいない。誇るほどの戦果や確かな足跡を残したとは言い難い。残した結果だけを見れば、そう結論付けられても仕方のないところだ。
それでも、あえて俺は言いたい。
世良正志は、たとえ凡人であったとしても天才の集う世界で輝けることを、身をもって証明した。俺は、そういう人間をこそ天才と呼ぶに相応しいと思うのだ。
――一度堕ちてから、また這い上がった人間
凡人たる俺は「天才」をそう定義することにする。
そう。俺なりの定義に従えば、間違いなくお前は天才だよ、世良。
天才はいつだって孤独だ。一面の真実ではあるだろう。
だが、堕ちた天才はもっと孤独だ。世間は目を背けがちだが、それもまた真実だ。
天才であるためには一度どん底まで堕ちなければならないとすれば、天才を際立たせるものとは即ち、堕ちてからまた這い上がる物語そのものにあるのかもしれない。
もちろん、堕ちた天才の紡ぐ物語以上に心動かされるものはない、などと思ってしまうのは、きっと凡人にありがちな勘違いなのだろう。天才も自分とさして変わらないただの人間だと思えるから。それも一種の僻み根性であるに違いない。
やはり天才はあくまでも天才であり、特別な存在である。
そういった分かりやすい天才観が世間を覆っているような気がする。
残酷だが、きっと世界は少数の天才と無数の凡人によって成り立っているという構図が変わるものではない。ただ、天才も時には必死に足掻く、ということがあるだけだ。
「やっぱりお前は天才だったよ」
山口俊司は噛みしめるように、そう小さく呟いた。
ドーム内に響いたまばらな拍手の音はしばらくの間止みそうになかった。
主役の去ったグラウンドには祭りの後の寂しさが漂っていた。
「さて、ぐっさん。球団事務所の方に挨拶に行こか」
これからが一仕事やで。葛原正人は大きくひと伸びしてから、淡々とそう告げた。
「祝勝会のビールかけでも見に行くつもりか?」
優勝決定後、祝賀会会場での恒例のビールかけ。
葛原がそんなものに興味があるようには到底思えなかった。それに、後片付けが大変そうだから球団事務所内ではやらず、室内練習場の駐車場の特設テントとかが多いようだが。しかも球団関係者と報道陣以外、出席できないと思うぞ。
「ちゃうちゃう。言うてへんかったか? オレ、来季からガンナーズの特別アドバイザーになるねんで」
言ってねえし、聞いてねえ。
「アドバイザーって、なんのアドバイスするんだよ」
葛原正人が北海道ガンナーズのアドバイザー?
三島がプロ野球についてのコラムを書く以上に違和感たっぷりだぞ、それ。
「そこらへんの腐れ記者にウマい汁吸わせてやるぐらいなら、もちっと手持ちの情報を有効活用しよやないか、ちうてな」
葛原正人が気色の悪い薄笑いを浮かべている。
「BOS(ベースボール・オペレーティング・システム)みたいな情報管理システムに億単位の金を使うてる割には、選手の悪評につながりそうなネタに無頓着すぎんねん」
――悪評。遺伝子ドーピングによって〈作られた子供〉だと中傷された、火野周平のことを指しているのだろう。あんな大それたネタを強請りに使う方も使う方だし、ネット界隈でそのような話題が散見されたとして、事前に予防など不可能であっただろう。
「ま、あの川村いうクソ記者も強請り方が下手やねんな。センスあらへん」
強請りにセンスを求める時点で、どうかしていると思うが。
「あれは金をむしるだけの単なる寄生虫やからな。球団から排除されて当然やで。Win―Winとかいうビジネス用語は大嫌いやが、関係はそうでなきゃあかん。お互い利用しつつ、利用されつつ。ビジネスちうのは、そういうもんやろ?」
水原隼人ばりのドヤ顔で、いったい何を言い出すか、こいつは。
「あのエロ記者が寄生虫なら、あんただって似たようなものじゃないの」
内田真紀が冷ややかな目で葛原正人を見下ろしていた。
「ちゃうで。オレの場合は癒着や」
ふふんと鼻を鳴らした葛原正人は、いかにも得意げな様子であった。
寄生か、癒着か。どちらにせよガンナーズ球団としては、強請られる相手が川村記者から葛原正人に代わっただけの気もする。
立花球団副社長が、よくそんな訳の分からない雇用条件を呑んだものだ。
「おいっ、葛原。もしかしてお前……」
今更ながらに、その可能性に気付いて愕然とする。
「ん? なんや、ぐっさん」
葛原正人のにやけた笑顔を直視できなかった。
そうか。だからこいつは、男の依頼は受けないとかいうポリシーを曲げ、調査費用を一円も請求しないタダ働きでありながら、俺に協力してくれたのか。
「お前、球団の内部情報に潜り込むために、俺に協力したのか?」
「人聞き悪いのう、ぐっさん。オレはそんなにあくどそうけ?」
いや、褒めてねえから。なんでそんなに嬉しそうに照れてんだよ。
「うん、どうせ葛ちんのことだから、遺伝子ドーピングが蔓延するような社会になったら、選手のパーソナルデータがいちばん情報価値を持つやろって、前々から目をつけてたんでしょー」
ガンナーズのベースボールキャップを引っくり返してかぶっている霧島綾が、意味ありげな笑みを片頬に浮かべている。おぬしも悪よのう。いやいや、お代官様ほどでは。ほほほほほ。まさしく、そんなような表情に見えた。
「おっ。分かっとるやないけ、霧島」
やっぱり裏稼業だ、こいつら。会話が危なすぎる。
「炎上の芽を事前に摘む特別アドバイザーちう名目やな。お陰で球団の持ってる情報に自由にアクセスできるようになったで。もちろんBOSにもアクセスフリーや」
最初からそれが狙いだったのか。葛原にとっては、球団の内部情報こそお宝に等しいのだろう。葛原正人にBOS、考え得る限り最悪の組み合わせだ。
「あとは、どっかの製薬会社に潜り込めれば完璧やな」
そういえば、葛原正人から転送されてきたメールの内容を今更ながらに思い出した。文章自体は三島シンジが書いたというが、小難しい文章だったので読み飛ばしていた。
携帯電話のメール画面を開く。そこには確かにこう書いてあった。
極論として「遺伝子ドーピングを合法化すべき」だと主張する科学者も一部存在する。
極論ついでの一つの仮定として、未来が遺伝子ドーピングが合法化された社会になった場合に、もっとも利益を得る人間はどんな人物であろうかについても推論する。
ドーピング用の薬剤を頒布する製薬会社、ドーピングを施す医療者、ドーピングを施された競技者、競技者を仲介して手数料を得る代理人といった類であろうと考える。
数ヶ月前の段階で三島シンジが未来を予言していたではないか。
つまり葛原正人は三島シンジの書いた絵図に従って、競技者を仲介して手数料を得る代理人のポジションを先取しに行動しただけという訳か。
葛原が突撃兵なら、三島はチームの頭脳たる扇の要ということだろう。
「お前、また人の道を外れるつもりじゃねえだろうな?」
「オレは忘れっぽいからなー。昔のことは忘れたで」
ざっくり言うと十年前、中学三年生の時の話だ。
葛原正人が何を思ったのか、三島シンジにバタフライナイフで斬りつけようとしたところを、かろうじて軟式球を投げつけて制圧した事件である。
それをこいつは、あっさり忘れたという。
お前、いつぞやの電話で言ったよな。ぐっさんがオレを止めてくれなきゃ今頃殺人鬼になってたかも知らん。そらあ、あん時はムカついたけど、あれぐらいの荒療治が必要やったんやろ。おかげで目覚めたわ……って。
それが舌の根も乾かないうちに忘れた、だと。ふざけるのも大概にしろよ。
「お前がやろうとしていることは社会に弓引く行為だよ、葛原」
遺伝子を弄くって、競技能力を向上しようだなんて、そんなことは考えちゃいけねえんだ。どんなにそれを望んでも、手を出しちゃいけない禁断の果実だ、それは。
「クソ真面目なところは相変わらずみたいやね、ぐっさん」
クソ真面目で結構。逃げのリードで結構。
人工的に作りだした天才なんてまがい物が世に溢れたら、俺はきっと世の中に絶望する。
努力して、人知れず自己を磨いて、思うような結果を出せない茨だらけの日常ともなんとかかんとか折り合いをつけて。そうやって、常人ならざる能力を身につけるに至った一握りの天才を冒涜することだけは、やっちゃいけねえ。
「ま、オレが道を踏み外す方向に暴走しそうになったら」
葛原正人が「やれやれ」というポーズを見せ、わざとらしく溜め息をついた。
「ぐっさんがオレにボールをぶつけに来るんやろう? 中学のあの時みたいに、な」
意外と根に持ってるじゃねえか。なにが忘れっぽいだ、この野郎。
「ああ、何度でもな」
ちょろちょろと小うるさいランナーを刺すのは捕手の仕事のうちだからな。
「今度は軟式球やのうて、硬式球か? 下手すりゃ死ぬで」
大丈夫、その心配は要らねえよ葛原。火野周平みたく160㎞が放れるわけじゃねえから、当たりどころが悪くても死にはしねえよ。
「副社長に会ったら、アドバイスついでにひとこと言うといてやるわ」
葛原のことだ。どうせ、まともなアドバイスじゃあるまい。
「山口俊司を捕手として指名しなかったんは節穴やったな。そう言うとくわ」
ああ、やっぱりまともなアドバイスじゃなかったな。
「今更だぜ、そのアドバイス」
「そうけ? 今からでも、遅くはあらへんやろ」
ほんとうに今更すぎるぜ、葛原。
「ねえ、ヤマちん、ヤマちん」
振り向くと、霧島綾にガンナーズのレプリカユニフォームの袖を引っ張られていた。
「コミコミがねー」
……コミコミ? ああ、小峰先生のことか。
霧島綾の差し出したスマートフォンの画面に、小峰先生からのメールが一通届いていた。
そこには一言、「無念だ」と書かれていた。国語教師のくせに、いったい何を書いているんだ、この人は。舌足らずにも程があるだろう。
美味いものづくしの北海道旅行に同伴できなかったのが無念だ、とでも言いたいのか。
「北海道のお土産は、カニとウニとエビとホタテがいいって、リクエスト来たのー」
コミコミ、いくらなんでも、あんた欲張り過ぎだよ。
「人間、そんなに欲張っちゃいけねえよな」
才能も、エビもカニもホタテもな。
ああ、あとウニもだったか。
-------------------------------------------------------
▼里崎智也氏よりコメントを頂戴しました
「華々しい世界の裏ではプロになれなかった者たちも数多くいます。人生山あり谷あり、いろいろな困難が待ち受ける中で、自分と仲間を信じ続けた彼らは素晴らしいですし、最後まで諦めないで前に進む姿に感動しました」
里崎智也(さとざき・ともや)/鳴門工業高校から帝京大学を経て、98年のドラフト2位で千葉ロッテマリーンズに入団。2005年、10年には日本一を経験。2006年のWBCでは正捕手として日本を世界一に導く。2014年、現役引退。現在は千葉ロッテマリーンズのスペシャルアドバイザーを務める。