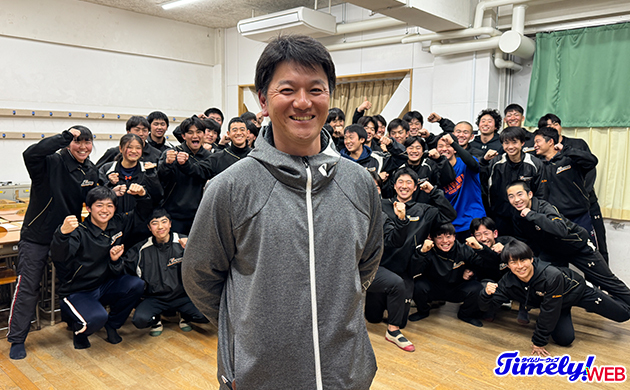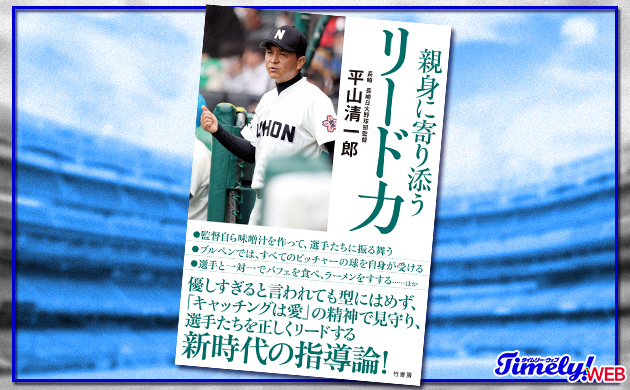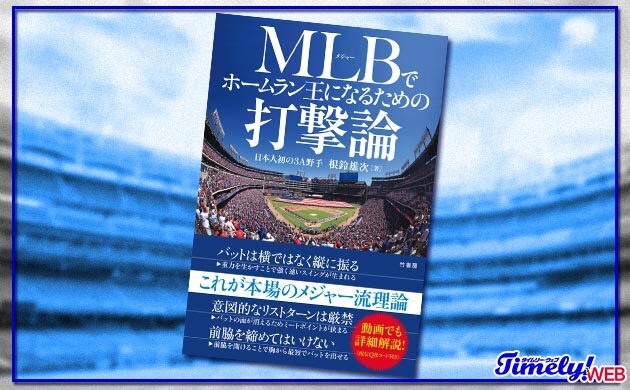〜第12回〜
野球部の話を中心に、中学時代の思い出話に花が咲いた。
「えっ、でも私も山口君のイメージちょっと変わったかも。もっとガチンコの体育会系のイメージあったのよね。それこそ軍隊みたいな? 甲子園も優勝してるし」
私、山口君もプロに行くんじゃないかと思ってたわ、と真紀はさり気なく付け加えた。ナチュラルに古傷を抉るな、古傷を。どうせ俺はプロの器じゃなかったよ。山口は心の中で舌打ちする。
「いや、どう調教したところで、緋ノ宮に軍隊は作れないよ。基本足並み揃わないし、監視してないとすぐダレるし。ゲーム脳多いし。ま、監督が志乃さんみたいな人だったらプチ軍隊になってたかもしれないけど」
志乃さんは小峰先生の奥さんだ。かつて緋ノ宮学園中等部で養護教諭を務め、一試合だけ中学野球部の臨時監督を務めたこともある威圧感ハンパない女傑である。
「結婚は人生の墓場だぞ、三島」
なんだか妙に実感のこもった一言を小峰先生は唐突に呟いた。三島シンジが珍しく相槌を打つ。
「はあ、その心は?」
「眠る場所は決まっているが、心が安らがない」
「まま、センセ―どぞ」
霧島綾が片手で雑なお酌をした。女優らしく台詞をつけるとしたら「小峰の亡霊よ、安らかなれ」あたりだろうか。もしくは魔法の杖を振って「エクスペクトパトローナム」とかだな。たぶん。
「痩せろってうるせえんだよ、志乃のやつ」
小峰先生はぶちぶちと日頃のストレスを愚痴り始めた。愚痴の半分はノロケに聞こえたが、あえて追及することもあるまい。内田真紀は何も言わず、冷めた焼き鳥を皿に盛って差し出した。嫁の監視の目はない。こんな場所だから気兼ねなく食え、とでも言いたいのだろうか。こういうのを内助の功と言うのだろうか。いや、違うな、きっと。たんなる残飯処理が関の山だ。小峰先生は少し潤んだ目で、冷めきったねぎまをもぞもぞと咀嚼している。
「たしかに志乃さん、家でも竹刀持って監視してそうですもんね」
山口が苦笑する。なんとなく囚人と監守の関係を想像してしまったことは口にしないことにした。内田真紀が心なしか暗くなってきた話題を変えた。
「そういえば、山口君が葛原の顔面にボールを投げ込んだ事件、覚えてる?」
「ああ、もちろん」
何をトチ狂ったのか、生物部の変人葛原正人が同級生の三島シンジにバタフライナイフで斬りかかろうとした事件である。山口が軟式球を葛原の顔面に向かって投げつけて制止し、事なきを得たという中学時代の懐かしき一幕だ。
「あれ、ちょっとした見せ場だったらしいな」
志乃から聞いた、と小峰先生は焼酎を呷りながら言った。
「俺ちょっと疑問だったんだけどさ。葛原が三島に斬りかかる前に『三島は殺人鬼だ』とかなんとか騒いでたじゃん。あれ、どういう意味だったの」
瞬間、三島シンジの顔が分かりやすいぐらいに引き攣った。一方、内田真紀は笑いを噛み殺すのに必死な様子だ。
「あー、そっか。皆は知らないんだよね。もう時効だし、いいかな」
真紀はちらりと三島シンジの横顔を眺めてから、訥々と語り始めた。
「シンジのやつさ、私に『君を殺したい』なんていうふざけた手紙を送ってきたわけよ。本人としては真面目な告白のつもりだったらしいんだけど、さ。で、それをどこかで葛原が聞きつけたってわけ」
真紀のあっけらかんとした告白に面食らったのは山口だ。
「はあ。葛原はともかく、三島は常識人に見えたけどなあ」
三島シンジは俯いてプチトマトのヘタをとり、しげしげとヘタの断面を見つめていた。何の儀式だ、それ。悪魔払いか?
「でも、三島って人間に興味あったんだな」
「いや、あんまり」
三島シンジは消え入りそうな声で言った。
「いろいろあったのよ。ねー、シンジ」
言いつつ、内田真紀は三島シンジの頭をわしゃわしゃと撫でた。三島シンジは完全に無抵抗で、されるがままの状態を受け入れている。無抵抗、非暴力。……ガンジーか? あれっ、非暴力、不服従だったけか。まあ、いいや。知らん。山口の酔っぱらった脳内に一世を風靡した「ありのままに~」という歌詞がリフレインした。
「いろいろあったよな」
小峰先生がしみじみと呟いた。
「そんな二人も結婚しまぁす。人生の墓場、おめでとー」
いえー、とジョッキを持った霧島綾が立ちあがってよく通る声で叫んだ。個室とはいえ周りの客に迷惑なことこの上ない。ここにも変人がもう一匹、か。
「何よ、いきなり。うっさい、座れ」
内田真紀が霧島綾に向かって凄む。だが、言葉とは裏腹にまんざらでもない表情を見せている。若干、頬が緩んでいる気もする。意外と分かりやすいんだな、内田。人物観察は捕手の習い性だ。のらりくらりと変化球でかわす軟投派ピッチャーと、ひねくれたピッチャーをリードするのに妙な高揚感を覚えてしまうキャッチャーだな、この二人は。けっこう良いバッテリーだと思うぞ、お前ら二人。
「で、今日は葛原は来ないわけ?」
「あー、なんか野暮用でちょい遅れるって言ってたわね」
「んー、葛ちんのヤボ用って、なに燃やしてんだろうねぇ」
……野暮用?
……燃やす?
何だ、この会話。駄目だ、さっぱり流れについていけない。
「すまん。やっぱ行かれへん、だって。ぐっさんによろしゅう言うとって、だって」
霧島綾がスマートフォンの画面を見ながら言った。
「逃げたな、許さん。こんど一食奢れ、って言っといて」
「ラジャー」
霧島綾がぴしりと軍隊式の敬礼をした。
「そういや、葛原はなんの仕事してるんだ」
「う? 炎上マーケタ―だよ」
「……何だ、そりゃ」
霧島綾は酔っぱらって少々呂律の怪しい口ぶりで、至極曖昧な説明をした。要約すると、葛原正人はネット上での炎上対策から各種情報操作、アリバイ工作、炎上マーケティングを介したプロモーションをワンストップで提供する『葛原ファイアスターター社』の取締役社長なのだという。
「怪しさ満載だな、その会社。ま、葛原らしいっつーか何というか」
山口は呆れたような感想を漏らした。
霧島綾は「はいっ、これ。葛ちんの連絡先ね」と名刺を山口に手渡した。
「なにかお役に立てることがあるんじゃないかにゃーと思って、さ」
「ん、ああ。サンキュー」
山口は手渡された名刺を無造作にズボンのポケットに突っ込んだ。酩酊した小峰先生はいつの間にか正体をなくして、テーブルに突っ伏しいびきをかいて気持ちよさそうに爆睡している。さて、この大荷物、どうやって上司殿の恐妻に引き渡そうかな。今まさにこの瞬間こそ、炎上対策班の出番なのではなかろうか。心地よい酔いが回る頭で、山口はそんな現実的なことをぼんやりと考えた。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら