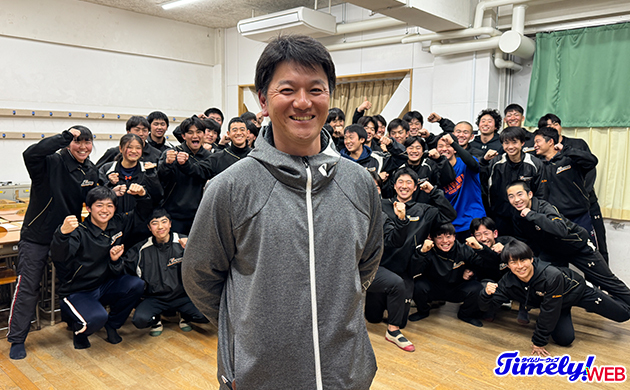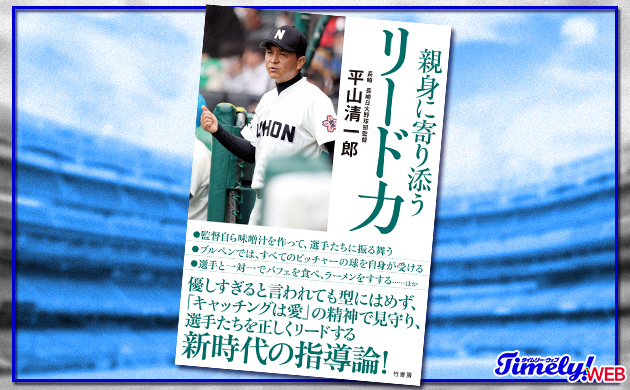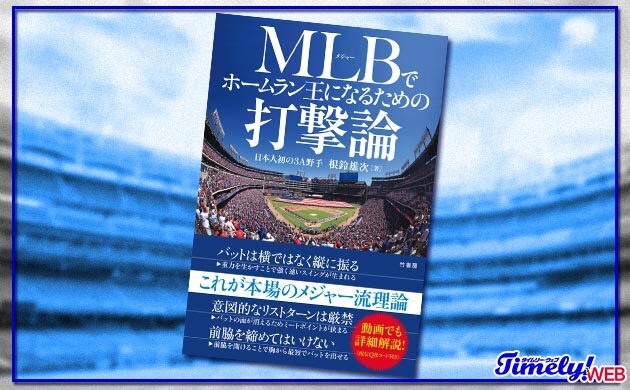〜第39回〜
世良の復帰登板から早二ヶ月近くが経とうとしていた。
六時間目の体育の授業が終わり、山口俊司はジャージ姿のまま、いったん職員室へと戻った。一五時十五分からの終礼のため、自席でくつろいでいるクラス担任の小峰先生に一声かけることにした。
小峰先生はなにやら週刊誌を読みながらニヤニヤとした笑みを浮かべている。
近付くと表紙には「週刊パトス」と書かれており、水着グラビアの美人がにっこりと微笑んでいた。エロネタや与太記事も多い小峰先生の愛読誌である。
某アイドルグループの推しメンとやらが水着姿になっているページを切り抜いて、夜な夜なコレクションしているとも聞いたことがある。そして、その秘蔵コレクションが妻である志乃さんに露見して、粗大ゴミとして呆気なく処理されたことも聞いた。
四十を前にして若干の痛々しさを感じる姿であるが、本人が満足しているならそれで良かろうと思うことにしている。パトスなのだから仕方がないのだ、と。
パトスとは、痛みや悲しみ、喜びや欲情といった快楽や苦痛を伴う一時的な心理状態、情念、感情を意味するギリシャ語だと小峰先生が国語の時間にしたり顔で生徒たちに講義していたのをよく覚えている。
講義姿は実に高尚だったが、たんに愛読誌の語源を語っているだけだという裏舞台を知る山口からすれば、吹き出すのを我慢するので精一杯であった。
「そろそろ終礼の時間っすよ」
山口は週刊誌に夢中の小峰先生に話しかけた。
「ん? ああ、そうか。そんなことより山口、お前もこれ見ろよ」
小峰先生がちょいちょいと手招きをする。中学生数人が部室でエロ雑誌を回し読みしているかのようなノリであった。中学生ならまだしも、さすがに神聖なる職員室で水着グラビアに熱いパトスを感じるのはどうかと思うが。
「何すか。巨乳のお姉ちゃんでもいましたか」
山口が溜め息交じりに冷やかに言うと、
「ちげーよ、バカ。三島が書いた記事が載ってんだよ」
と小峰先生が慌てたように言った。
……怪しい。
山口は音もなく小峰先生の背後に忍び寄ると、肩越しから雑誌を取り上げた。
小峰先生が開いていたページを見やる。そこには仰々しい極太の明朝体で「忘れ去られた男の帰還」と書かれていた。文末に三島シンジの名前があった。
「お前のことも、ちらっと書かれてるぞ」
立ちあがった小峰先生に、ぽんと肩を叩かれた。
「終礼はやっとくからゆっくり読めや」
とにかく今読め、ということらしいのでお言葉に甘えることにした。
山口は小峰先生の隣の自席に腰掛け、三島シンジの署名記事を読み始めた。
世良正志の後半戦での活躍が目覚ましい。彼はついに甲子園の亡霊と決別したようだ。
世良投手が過ごしたプロ入り以来の二年半という歳月は、すなわち甲子園の亡霊と闘ってきた二年半でもある。対戦するのはプロのバッターではなかった。
甲子園のアイドルとして偶像化された自分との闘いであった。
前半戦の不調から無期限の二軍落ちを言い渡され、偶像は地に落ちた。誰もが次世代を担う二刀流の天才に夢中になり、偶像は単なる偶像であったことを露呈した。
そして、男は忘れ去られた存在となりかけた。
だが、そこからの復活は見事としか言いようのない出来であった。
復帰第一戦でのわずか八十六球の初完封劇。二十六イニング連続無四球無失点。八戦投げて七勝一敗、54イニング5失点、防御率0.83。前半戦終了時点で8.48と壊滅的だった防御率はシーズン通算で3.42まで下がった。バッティングピッチャーのようだった前半戦とは打って変わって、格調高い大人のピッチングを披露している。
何が彼をここまで変えたのだろうか。正捕手である白鳥選手がオールスター前に右肩を痛めてDH専任となったこととも無関係ではないだろう。世良投手は後半戦からベテランの笠松捕手とバッテリーを組むようになった。しかしながら、キャッチャーをすげ替えただけでこれ程までに事態が好転するものであろうか。
たしかにそれも一つの要因であるとは思う。だが、亡霊退治の手柄を捕手の変更のみに帰するのはさすがに安直というものであろう。技術的な話は専門家に委ねることとするが、何より変わったのはマウンド上での表情である。
「一試合、一試合最後だと思って投げています」
いつだったか、試合後のヒーローインタビューで世良投手が答えた言葉だ。きっと本音であるだろう。堕ちた天才は追い詰められて初めて狂気じみた輝きを放った。
顔つきも、まとう雰囲気も明らかに変わっていた。前半戦と比べると別人かのような変貌である。マウンド上で見せる顔はもはやかつての弱々しい草食動物の目ではない。
戦う猛禽の目、形振り構わず相手を食い殺そうとする目である。
「真のエースが還ってくるまでの露払い役ですから」
勝利後のインタビューで世良投手は、そうも語っていた。その短い言葉に表舞台へと再び舞い戻ってきた男の矜持が垣間見えた。前半戦は廃車寸前のポンコツであったが、後半戦に限れば間違いなくエースの称号に相応しい働きである。
思い起こせば、高校時代、大学時代とバッテリーを組んだ山口捕手とのコンビはさながら心躍るようなポップスであった。プロ入り前の姿を国民の誰もが口ずさむ流行歌だとすれば、現在バッテリーを組む老獪な笠松捕手とのコンビはさしずめクラシックである。
派手さには欠けるが、調和のとれたピッチングは玄人筋を唸らせる芸術の域にまで高められている。至高のピッチングを観に、ぜひとも球場へと足を運んで頂きたい。
さて、忘れ去られた男は玉座へと帰還した。
(著者:神原月人)