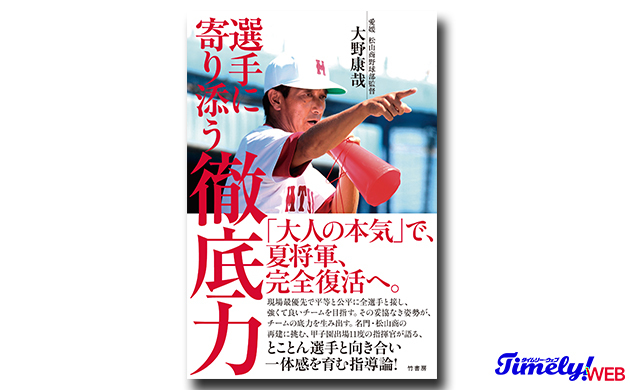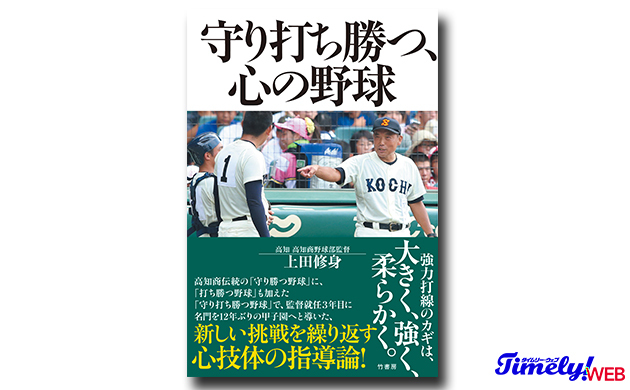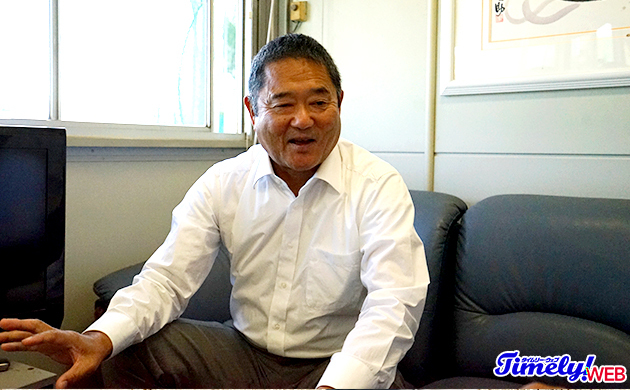〜第18回〜
「ああ、ヤマ。ちょっと相談があるんだけど、今電話大丈夫かな」
六月も終わりに近づいた土曜日の午後、世良正志からの電話を受け取った。五月の終わりに世良が二軍落ちした際に会って以来だから、三週間ぶりぐらいであろうか。いちいち恐縮するところがまた世良らしい。
「今授業が終わって、職員室で飯食ってるところだから平気だぞ」
山口は食べかけのカツ丼をテーブルに置きながら答えた。隣の席で愛妻弁当を食べ終えていた小峰先生が「お、なんだ女か?」としつこく茶化してきた。相手をするのも面倒だったので、席を立ちベランダに出た。
二階職員室のベランダから外を見ると、手を振る生徒の姿があったので適当に手を振り返しておいた。これもまた教師の務めである。背後で「カツ丼、食べないなら食べちゃうぞー」という怨嗟の声が聞こえた気がしたが、こちらは無視することにする。
「さっきまで火野と話していたんだけど」
世良の声は体育会系育ちのわりに普段からあまり大きくはないが、電話越しだと余計に小さく聞こえた。自然と山口の答える声も小さくなった。
「急に投げられなくなったらしいな、火野」
逡巡しているのか、世良が返答するまでに少し間があった。
「MRIとかの検査結果では、特に異常はなかったみたい」
火野は肘を痛めたのではないか、いや腰ではないか。あるいは肩ではないか。十九歳の育ち切っていない肉体に、二刀流などという過負荷をかけるから選手生命が危ないのではないかという報道まであったので、検査結果に何かしらの異常がなかったのであれば、そこまで重症ではなかったということだろう。
「そうか。そりゃ良かったな」
山口が安堵の声を漏らした。
「うん、そうなんだけど」
世良は何か言いにくそうなことでもあるのか、歯切れの悪い返答をした。
「誰かに相談しづらいような内容か?」
正確に言えば、俺以外の誰かに相談しづらいような内容か、という意味であるが、そこらへんは言わずとも分かるのが長年バッテリーを組んだ阿吽の呼吸というやつだ。
「うん」
電話先の世良の姿はもちろん見えはしないが、ピンチを迎えてマウンド上で少し弱気になっている時の姿がありありと思い浮かんだ。こういう時はぐだぐだと何か発破をかける必要はない。ただ黙って、一拍置けばいいだけだ。
「たぶん、イップスだと思うんだ」
山口が沈黙を守っていると、世良がゆっくりと話しだした。だが、その内容は山口の予想したようなものではなかった。山口はとっさに口元を押さえながら問い返した。
「悪い、順を追って説明してくれないか」
「えーと、どこから話そうかな。ネットの掲示板に、火野は〈作られた子供(デザインベビー)〉だって書かれているみたいなんだけど」
ぽつぽつと世良が話し始めた。その話なら聞いたことがある。根も葉もない噂だ。火野周平が遺伝子ドーピングによって、人体改造を生まれながらに施された〈作られた子供〉だと? 玉石混交の情報が渦巻くネット掲示板とて、冗談にも程があるだろう。
「火野はそんなことを気にする性質じゃないだろう?」
大柄な体格もそうだが、図太い神経をしていそうだ。そんな泡沫の書き込みに左右されるような、やわな性格ではないだろう。
「うん、それはそうなんだけど」
根拠の欠片も無い憶測だ。放っておくしかあるまい。
「浅野監督の自宅に、匿名の電話があったみたいなんだ。あんたは火野の過去を知った上で、高校時代に火野を重用したのかって。〈作られた子供〉だと知った上で、それを隠して、甲子園で投げさせたのかって」
それは初耳だった。少なくとも、ネット掲示板やまとめサイトの類では一切報じられていなかったように思う。
「それで、先生は何て?」
「電話に関しては、そんな事実はないって一蹴したみたいだけど」
一瞬の間があった。その先は聞かずとも分かる。そういう電話があったと、浅野先生から火野の耳に入ったということか。
「世間に何を書かれたって構わない。でも浅野先生にだけは、ほんのわずかにでも疑いの目を向けられたくはない、って火野が言うんだ。だから、俺はほんとうに〈作られた子供〉じゃないって、誰にでも分かる形で証明しなければならないって」
火野が言っていることも、世良が言いたいであろうことも大筋で理解はできる。高校野球時代の恩師である浅野先生が匿名の電話やネット上の流言を鵜呑みにして、教え子にほんの一瞬であっても疑いの眼差しを向けることなど、絶対にあり得ない。
だが、そうは言っても浅野先生とて人間だ。火野の調子が悪くなっても、反対に、調子が良すぎても、もしかしたら遺伝子ドーピングの影響があるのだろうかと、かすかにでも脳裏に浮かんでしまうこともあるだろう。
ピッチングやバッティングの結果がどうであろうと、ドーピングをしていない証拠足り得ない。好成績を残せばドーピングを疑われるし、成績が落ちたら落ちたで、それまでにドーピングをやっていて、ドーピングが露見するのを恐れて途中でドーピングをやめたから成績が落ちたのだろうと糾弾することもできる。つまりは、どちらに転ぼうと、ドーピングをしていないという証拠にはならない。
「遺伝子ドーピングって、何かの検査で引っ掛かったり、体に何らかの痕跡が残るものじゃないらしいね」
世良は高校の後輩である火野のために、自分なりに調べたのだろう。付け焼刃の知識だろうが、それで十分だった。
「つまりは、遺伝子ドーピングなんかしていませんって、胸を張って無実を証明できる代物じゃないってことだよね。検査の方法自体が確立されていないんだもの」
「そうか。検査法自体がそもそも無いってことなんだな」
確たる検査方法自体が存在せず、有罪も無罪もそもそも判定できないのであれば、どうやって無罪を勝ち取れと言うのか。つまりは、遺伝子ドーピングなる冤罪は、難癖をつけた者勝ちの、無罪証明の方法すらない勝ち目の無い闘いということか。
「だから、掲示板に書き込んだ張本人か、匿名電話の主を見つけ出そうってことになったんだ」
たしかに、悪意の大元を突き止めれば、お前が真の犯人で、従って自分は無罪だと主張することができる。電車内で痴漢の冤罪をでっち上げられた際に、真の痴漢の犯人を突き止めれば、自身の罪は晴れる。それに似た理屈だ。犯人を炙り出したところでドーピングをしていない完全なる証拠にはならないかもしれないが、根も葉もない噂を流布した元凶を断てば、いずれ事態は収束に向かうだろう。
いや、収束に向かってもらわねば困る。だが、雲を掴むような話だ。
「言いたいことはよく分かるよ」
分かるけど、どういう案件の相談だ。山口は世良の次の言葉を待った。
「火野が泣きそうな顔して言うんだよ。先輩は俺と違って大卒だからいろいろ知ってると思うんですけど、こういう場合どうすればいいんですかって。どうにかして書き込んだ犯人を挙げられないですかねって」
無茶苦茶な相談だった。ネット界隈での風評被害以外にこれといった実害のない現段階においては、警察は積極的には動いてはくれないだろう。家族や知人、自分の身に危害が加わったりすれば本腰を入れて警察は捜査してくれるだろうが、現段階ではあまり頼りにはなるまい。
警察の助力を仰がずに、民間人が火野をドーピング犯だと貶めた犯人を捕まえるにはどうしたらいいですか。要するに、火野が世良に問うた質問はそういうことだ。野球漬けの日々を送ってきたであろう火野にとって、大学とはどこか遠い国のように思えるのかもしれない。だが、高卒だろうが大卒だろうが世間知は正直大差ないし、火野の質問は世間知の範囲内で処理できるような代物ではなかった。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら