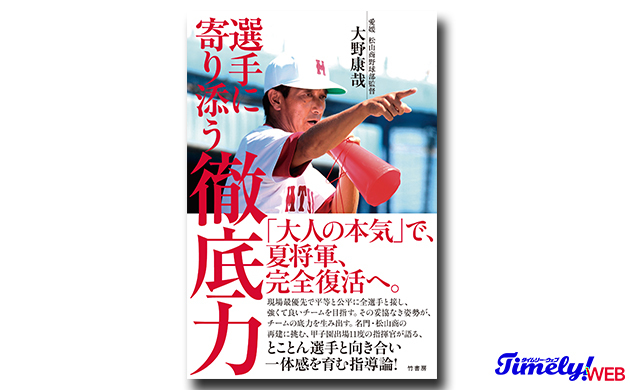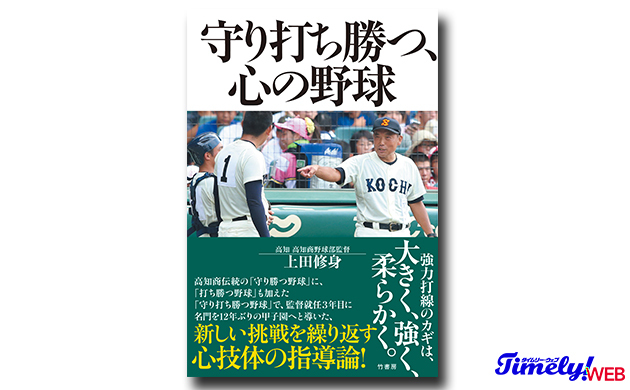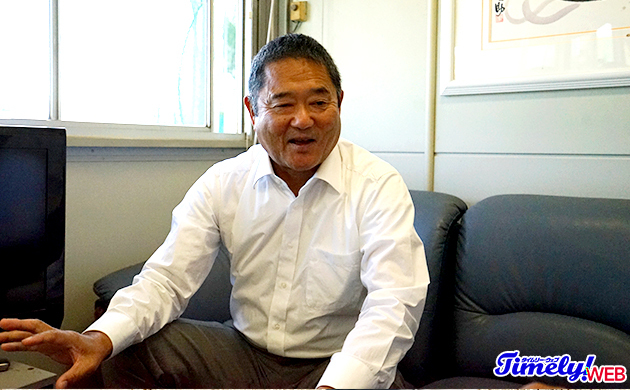〜第5回〜
右腕から放たれたボールが、ロケットのような勢いでキャッチャーミットに収まった。
東京セインツの五番打者佐々木が茫然とした顔で見送る。主審が三振をコールすると、背番号11がくるりとバックスクリーン方向を振り返った。
バックスクリーンの電光掲示板に、白い数字で「162㎞」と表示された。
日本最速タイ記録。球場内がにわかにどよめいた。
九回裏二死走者なし。昨年度セ・リーグ覇者の東京セインツ対パ・リーグの北海道ガンナーズの交流戦第一試合。スコアは五対〇でガンナーズリードとほぼ大勢は決していた。
東京セインツのホーム球場であるセインツドームを埋め尽くした満員の観衆の興味は、一九歳の若武者・火野周平の初完封に注がれていた。
セインツの岡田監督がベンチを出て、主審に代打・小笠原と告げた。小笠原信彦は過去に本塁打王を二回、首位打者を一回獲得している百戦錬磨のベテランだ。年齢による衰えは見えるものの、代打稼業となってからは類い稀なる集中力で試合を決する一打を何度も放っている。
小笠原が静かな佇まいですらりと左打席に立った。バットを構える様には剣豪を思わせる迫力が滲む。火野はキャッチャーのサインに頷き、右腕を目いっぱいに振った。初球は外角低めのストレート。二球目は大きく割れるカーブで早々とツーストライクと追い込んだ。小笠原のバットはぴくりとも動かない。
バッテリー間で三球目のサインが決まった。火野は小さく振りかぶり、投球モーションに入った。左足が高く上がる。弓のように後方に引かれた右腕がしなる。放たれた剛球が小笠原の胸元を襲った。勝負球はインハイのストレートだった。ボールがキャッチャーミットに収まりかけたかのように見えた刹那、小笠原のバットが一閃した。
小笠原はバットを放りあげると、一塁ベースに向かって悠々と走りだした。打球はゆったりとした弧を描いて、ライトスタンドに突き刺さった。セインツのスコアボードに一点が刻まれた。
完封目前で一発を喰らった火野は思わず舌をペロリと出した。帽子を脱いで頭を掻く。マウンド上で火野周平は苦笑いした。その顔は「いやあ、すげえ飛んだなあ。プロのバッターはやっぱり違うなあ」と言っているかのような素直に感心した表情だった。
打球の行方を見送った後、火野はマウンド上で二、三回素振りのような動作を見せた。
「すげーな、あのコースをスタンドまで運ぶのか」という意志表示であろうか。何度かのスイングの後、「おっ、こんな感じで打つのかな」と得心したような満足げな表情を浮かべた。火野は淡々とベースを一周する小笠原の姿を憧憬の眼差しで追っている。
思わず小笠原に拍手でもしかねないような勢いだった。
「ああいう勝負師らしくない表情はやめさせないといけませんね、監督」
ベンチに座って戦況を眺めていた北海道ガンナーズのピッチングコーチの今中が、溜め息交じりに栗原監督に話しかけた。
栗原はマウンド上の火野と同じような苦笑いを浮かべている。
「いいんじゃないの。ふてぶてしくてさ」
怖いもの知らずでいいじゃないの、と栗原は続けた。
「世良も高校時代はあんな表情してたっけな。それが今じゃ悲壮感たっぷりだ」
「明日はその世良の先発ですが」
栗原監督が静かに言った。
「ああ。世良にもかつてのふてぶてしさを取り戻して欲しいものだね」
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら