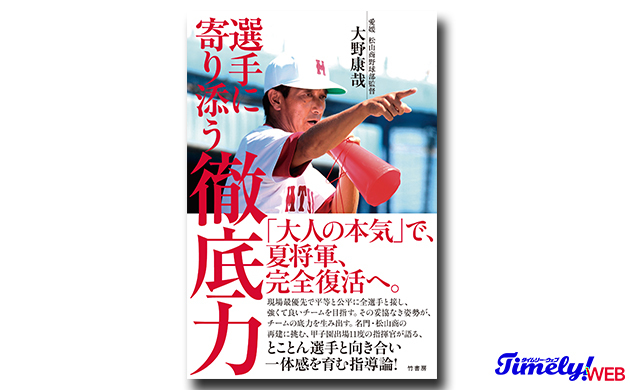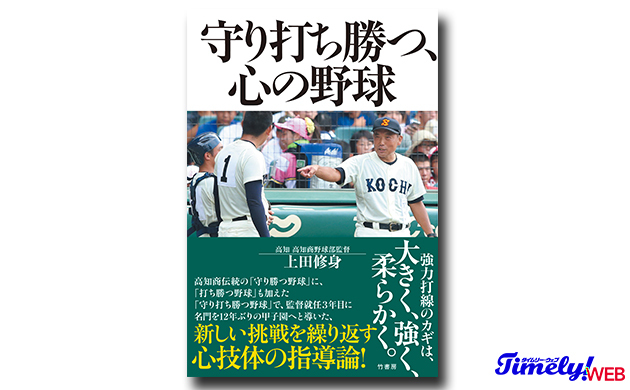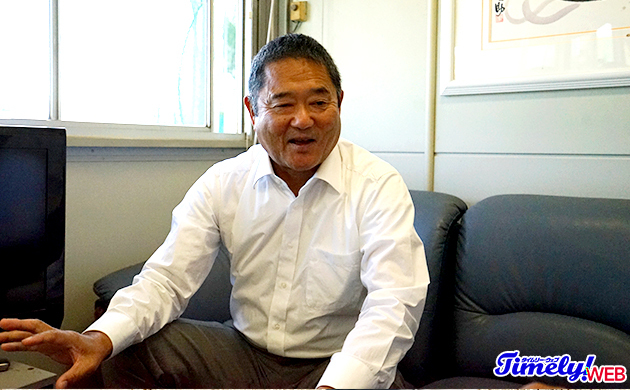〜第6回〜
先日の快勝から一夜明け、栗原は監督室で先発投手・世良と書きこまれた自軍のメンバー表を眺めていた。栗原は壁にかけられた時計をちらりと確認する。試合開始まで、あとたっぷり二時間もあった。
メンバー表の交換は試合開の約四十分前に行われるのが慣例であり、セインツのオーダーはまだ不明のままだ。今夜のセインツはオーダーを入れ替えてくるだろうか。
名将と評されつつも、落ち着きのない岡田監督のことである。ころころとオーダーを弄って来るに違いない。今季四五試合を消化時点で二十九通りものオーダーを試したとのことだ。まさに猫の目打線と呼ぶにふさわしい。
五月二十日から六月二十二日にかけて行われる交流戦も、2016年で導入十二年目を迎えた。今季からはリーグ戦とは逆に、セ・リーグ主催試合でDH制が採用されることになっている。昨夜代打でホームランを放った好調の小笠原をDHで起用してくるだろうか。
栗原がゲームプランを黙考していると、監督室のドアを叩くノックの音が室内に響いた。
「どうぞ」
監督室のドアが開き、球団副社長の立花洋一が茶色のブリーフケースを手にして入ってきた。メタルフレームの眼鏡に七三分けした黒髪、球団公式の紺色のスーツを着こなしている。球団社長は親会社から派遣されてきたお飾りに過ぎないため、立花は球団運営における実質的なトップである。
「これはこれは、副社長。アウェーゲームの視察にいらっしゃるなんて珍しいですね。先日の周平の快投、ご覧になられましたか?」
栗原は微笑を交えつつ、慇懃な挨拶をした。
立花は球場に隣接した球団事務所の副社長室にいることが多いため、本拠地ガンナーズドーム以外の球場に観戦に来ることは極めて稀だ。
「彼には、最近よくない噂も耳にしますが」
立花は眼鏡を持ち上げ、扉の近くから動こうとはしなかった。
「周平が何か?」
「いえ、ご存じないなら結構」
立花はブリーフケースを隠すように小脇に抱えた。
「わざわざいらして頂いて恐縮です。どうぞ、こちらへ」
栗原は丁寧に言い添えて、室内の中央にあるソファをすすめた。立花はすすめられるままに革張りのソファに着座した。栗原はちらりと立花の顔色を窺う。
多忙であるのか、立花はいつになく青白い顔をしているように見えた。
「今日はどういったご用向きでしょうか」
栗原の問い掛けに、立花は視線を落とした。
「先日は素晴らしいゲームでしたね」
立花は通り一遍の挨拶の言葉を口にしたが、なかなか用件を切り出そうとはしなかった。
「世良君に関することなのですがね」
「世良がどうかしましたか?」
栗原が世良正志を特別扱いしていることは、プロ野球関係者の間では周知の事実である。
高卒二年目の若き火野周平が一本立ちする一方で、栗原の秘蔵っ子と目されている世良にはいまだ本格化の兆しが見えずにいる。
「彼も今年で約束の三年目です。フロントにも納得のいく結果が伴わなければ、今後の処遇について検討しなければなりません」
それを言うためだけに副社長自らわざわざ出向いてきた、という事実そのものが特別扱いの何よりの証左であった。
「ええ、存じております」
「本日の結果次第では、世良君も分類対象となりますので」
立花は深々と礼をすると、踵を返して監督室を後にした。
「言われずとも、端からそのつもりですよ」
堅く閉ざされた監督室の扉に向かって、栗原が苦々しげに呟いた。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら