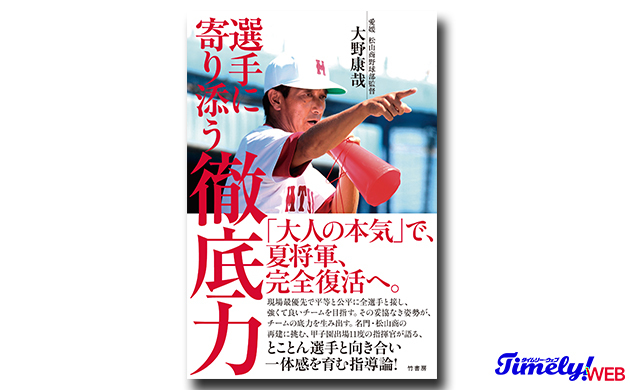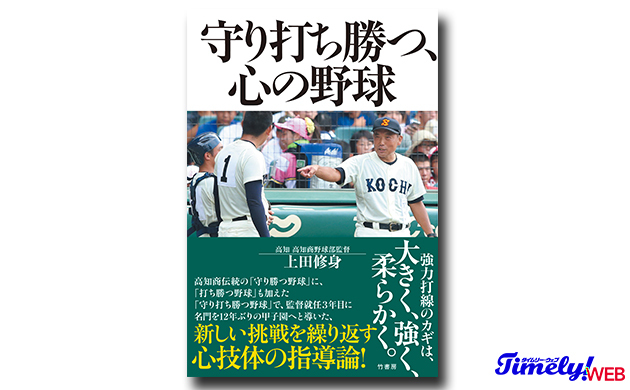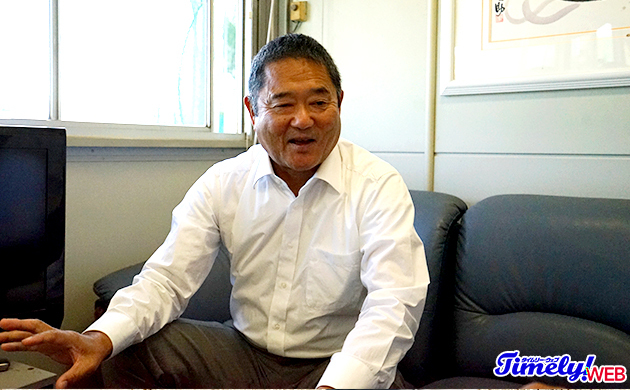〜第28回〜
ピアノの生演奏が静かに流れる薄暗い店内の奥まった角の席に四十代ないしは五十代と思しき男性が二人並んで座っていた。片方の男は横柄な感じで足を組み、もう片方の男は俯き、柔らかな絨毯の毛並みを眺めている。
「どうぞ」
黒服の若い男が中年の男性客二人に温かいおしぼりを差し出した。客がおしぼりをテーブルに置いたのを見計らって、黒服の青年は「Club L Ginza」の筆文字の刺繍が施されたメニュー表を手渡した。
「ボトル出して」
襟の空いたワイシャツにジャケット、スラックスというカジュアルな装いの無精ひげの男がメニュー表を受け取らずに答えた。隣に座る眼鏡をかけた男はスーツにネクタイというフォーマルな格好をしていた。
「すみません、お名前頂戴してよろしいでしょうか」
黒服の男が申し訳なさそうに言った。
「ああ? 客の顔ぐらい覚えとけよな。立花だよ、立花」
無精ひげの男が足を組み替え、不機嫌そうな顔をした。黒服の男が一礼しキープボトルを取りにバックヤードへと下がった。しばらくしてから黒服の男が戻ってきた。
「申し訳ありません、お客様。立花様のお名前ではボトルがございませんでした。たいへん恐縮ですが、お連れ様のお名前か、お名刺を頂戴いただけますでしょうか」
男は面倒臭そうに鞄から名刺入れを取りだすと、黒服の男に投げつけるようにして名刺を手渡した。
「川村だよ。今度はちゃんと探せよな」
両手を差し出して名刺を受け取った黒服の男は、しげしげと印字された文字を見つめた。
「川村様、只今ボトルをお持ちいたします」
黒服の男が席を離れるのと入れ替わりに、ドレスを着た女性二人が席の前に立った。
「アヤカでぇす。宜しくお願いしまあす」
胸元の開いた赤いロングドレスに身を包んだ女が微笑み、無精ひげの男の隣に浅く腰掛けた。
「お隣、失礼しまあす」
革張りのソファに座る際、シャギーのかかった栗色の髪が揺れた。
「君はあれだね。えーと名前はなんて言ったかな。女優のあの子に似てるね」
頭の中の記憶を探るかのように、川村と名乗った男はこめかみを押さえた。
「きり、なんだっけ? きりしま?」
「あ、もしかして霧島綾ですかぁ? えー、よく言われますぅ」
アヤカが嬉しそうに言った。
「あっちがマキコちゃんでーす」
アヤカが川村を挟んだ反対側に座る白いドレスの女を紹介した。黒服の男が焼酎のボトルを抱えて戻ってきた。ボトルをテーブルの上に置くと、黒服に身を包んだ長身の男はテーブルから数歩離れた位置に影のように寄り添っていた。
「今日は、お二人でいらしたんですかあ?」
アヤカが何気ない口調で聞いた。
「そう。副社長が奢ってくれるって言うんでね」
川村がマキコの隣に座る眼鏡をかけた七三分けの男を指差した。副社長と呼ばれた男は、マキコが作った水割りを美味くもなさそうにちびちびと飲んでいる。
「えー、副社長ですかあ。すごーい」
アヤカが甲高い声で相槌を打った。
「別に凄くなんかねえよ、副社長なんて」
川村が心底つまらなさそうに言った。吐き捨てるような口ぶりだった。
「こっちの彼女は控えめだね」
男が不意にマキコの胸を鷲づかみにした。一切の遠慮のない手つき。マキコの肩が小刻みに震えている。男は、マキコの耳元に顔を寄せると低い声でささやいた。
「おっぱいも控えめかな」
胸を揉みしだきながら男は薄笑いを浮かべていた。黒服の男が音もなくテーブルに近寄るが、アヤカがひらひらと片手を振って追い返す素振りをした。
「駄目ですよぉ、社長ー。おイタしちゃあ」
アヤカが男のシャツの袖を引っ張りながら言った。
「高え金払ってんだから、ちょっとぐらい良いじゃねえか」
男はそう言うと、マキコのドレスの裾に手を突っ込み弄りはじめた。
「ひっ」
マキコが小さく呻き、身を引いた。マキコの片足が露わになり、黒いレース模様のショーツが露わになる。
「中身は意外とエロいじゃねえの」
男は満足げに呟くと、ショーツのラインを不遠慮に撫で回した。マキコの隣に座る立花は無視を決め込んでいるのか、川村の狼藉に何の反応も示さずにいる。
「あんまり調子乗るんじゃないわよ」
低い声が漏れた。地の底から聞こえてくるような重々しい響きだった。一瞬、川村の手が宙に浮いた。マキコは唐突に立ち上がるとテーブルの上に置かれたグラスを掴み、グラス内の酒だか水だかの液体を男に向かってぶちまけた。マキコはグラスをテーブルの上に置くと、ドレスの裾を持ちながら足早に歩み去った。川村は突然のことにしばらく茫然としていたが、平静を取り戻したのか険のある声で言った。
「おいおい。どうしてくれるんだよ」
川村は水を浴びせられた服を指差している。「弁償しろよ」とでも言いたげな様子だ。
「てゆーか、あたしにもかかったしー」
男の隣でアヤカがむくれた声を発した。
「申し訳ございません。クリーニング代はお支払いさせて頂きますので」
バックヤードのあたりから引き返してきた黒服の男が片膝をついて謝った。
「クリーニング代が足りなかったり、汚れが落ちなかった場合、お宅どうしてくれんの」
川村が力任せにテーブルを叩いた。テーブル上に置かれたボトルとグラスが振動する。黒服の男は片膝をついたまま視線を上げず、何か封筒のようなものを差し出した。
「お召し物の代えと、お着替え用にホテルの一室をご用意しております。もしよろしければお使いくださいませ」
川村がぞんざいに封筒を受け取った。封筒を開け中身を検分する。
川村は三枚の万札を抜き出し、指で弾いた。
「あっそ、そこまで言うならしょうがねえ。受け取ってやるけどよ」
男がアヤカの方を見て顎をしゃくった。
「そっちの姉ちゃんにもかかったみてえだぜ」
黒服の男は視線を上げずに答えた。
「彼女の着替えも同じ部屋に用意してありますので、申し訳ありませんがお着替えをご一緒させていただいてよろしいでしょうか。もちろんご無理であれば控室の方で着替えさせて参りますが」
黒服の男がやっと視線を上げた。
「いいよ、一緒で。服が濡れて冷てえから、さっさと部屋に案内してくれや」
黒服の男が立ちあがり応じた。
「恐縮です。ではホテルのお部屋までご案内させて頂きます」
席に一人取り残された立花は居心地悪そうに座り、水割りのグラスを傾けていた。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら