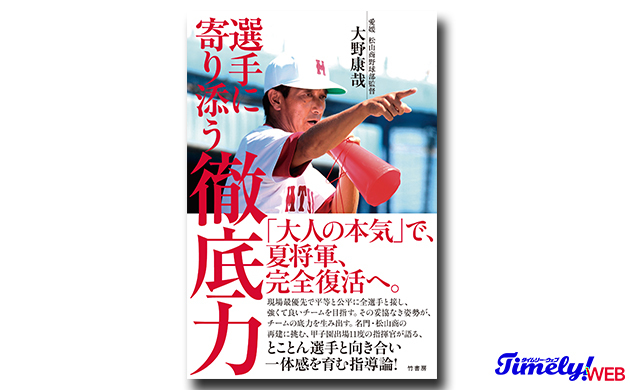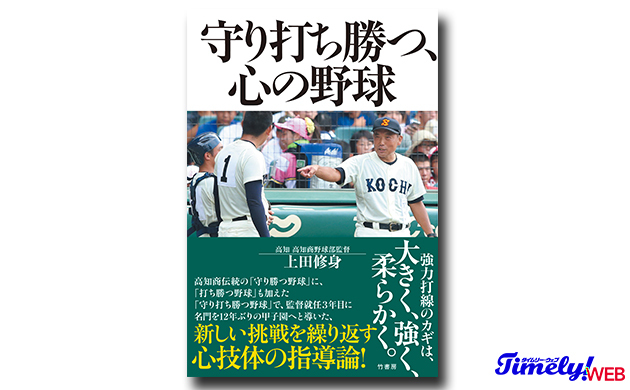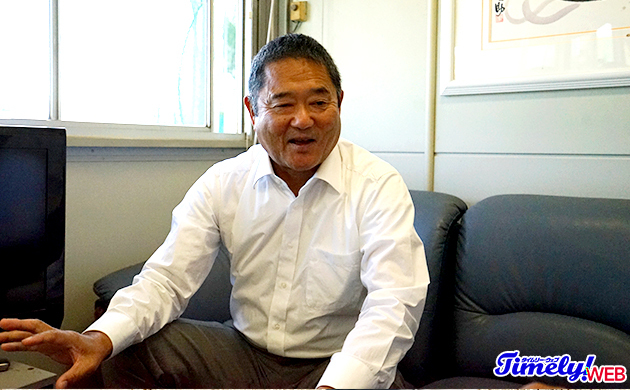〜第19回〜
さて困った。山口はベランダの鉄柵に体重を預けながら、さしたる意味もなく空を見上げた。抜けるような青空が眼前に広がっていた。
「それで、なんて答えたんだ」
山口は取り繕うような調子でそう言った。きっとこういう態度を「逃げのリード」と称されるのだろう。勝負に行く場面で安全第一の策を選ぶ捕手に押される烙印だ。だが、この瞬間は逃げていい場面だ。断言する。ここは強気に攻めるような状況ではない。おいそれと踏み込めば選手生命すらなくしかねない剣が峰に、わざわざ近付く必要はない。
「友達に探偵みたいなことをしているやつがいるんだ。そいつに頼めば、なんとかしてくれるかも……って火野に言った」
ブルペンかロッカーか寮の自室かは分からないが、火野と気まずい雰囲気で会話する世良の姿がありありと思い浮かんだ。きっと、塞ぎこんだ火野を見かねて犯人探しの希望ぐらいは持たせてやりたいと、「探偵みたいなことをしているやつと知り合い」などと口走ったのだろう。善意からの大嘘だ。
だが、実際に知り合いの可能性も多少はあるので、念のため確認してみることにする。
「探偵? そんなやつ知り合いにいたか」
山口がそう言うと、沈んだ声が返ってきた。
「うん、だからヤマの知り合いにそういう人いないかなって」
そうは言っても世良と山口は小学校から大学卒業まで同じ環境で育った仲である。知り合いはほとんど被っていると言っても過言ではない。プロの世界に入って三年を過ごした世良に探偵の知己がなければ、中学校教師となってからの山口の交友関係に頼らざるを得ないという構図だ。
「すぐには思い浮かばないけど、周りにも探偵の知り合いがいないか聞いてみる。こっちでなんとかするから、お前は余計なことに首突っ込まずに野球に専念しろよ」
お前、自分だって首が危うい立場なんだからな。悠長に他人のこと心配してる状況じゃねえだろう。その言葉は寸前でなんとか飲み込んだ。受話器の向こうで、世良が珍しく声を張った。
「ありがとう。悪いけど、よろしく頼む」
最後の言葉だけは、わずかに声の調子が明るくなっていたようだ。
「ああ、任された」
山口は通話の途切れた送話口に向かって小さく呟いた。
携帯電話をポケットにしまい、ベランダから自席に戻ると、空になったカツ丼の容器を発見した。空箱の隣に「たいへん美味しゅうございました」と書かれた置き手紙があり、緑茶の入った湯呑みが重石代わりに置かれていた。さて、火野を貶めた犯人はともかく、カツ丼を食い逃げした犯人をまず追い詰めねばな。
幸いにして容疑者の目星はついている。あまりにも自明過ぎて、犯人を特定するのに探偵は必要ないだろう。
「探偵か。どっかに都合よく転がってねえかな」
山口は空になったカツ丼の容器をゴミ箱に放りながら、そう小声で呟いた。
「なんか、アルジャーノンみたいな話になってるな」
職員会議を終え、帰宅前の一服がてらに缶コーヒーを口にしながら、小峰先生がぽつりとそんなことを口にした。
「何すか、アルジャーノンって?」
「アルジャーノンに花束を。ダニエル・キイスの書いた小説だ」
自販機からブラックコーヒーを取り出し終えた山口が不思議そうな顔で聞き返すと「野球オタクもいいが、たまには文学にも触れたまえよ」との国語教師らしいお小言が漏れなく付いてきた。内容は知らないが、タイトルだけは聞き覚えがある。
「ざっくり言うと、どんな話ですか」
たしかに小説など久しく読んだ記憶などない。小峰先生が何を言いたいのか判然としないので、小説の内容を素直に聞いてみることにした。
「幼児並みの知能しかないチャーリイが手術を受けて、めっちゃ天才になるって話。ちなみにアルジャーノンは、チャーリイの競争相手の白ネズミの名前な」
「天才になるのがなんかまずいんですか?」
何の手術を受けたのかは知らないし、しょせんは小説内の架空の世界のお話であろうが、手術によって誰もが天才たり得る未来が来るかもしれないと聞けば、そんなに悪いことではないとは思う。
「人間が軽々しく踏み込んじゃいけない領域もあるっている警句なんだよ、あの本は」
小峰先生はどことなく難しい顔をしている。
「人工的に天才を作りだす禁忌ってのは、まさに火野の置かれた立場だろ」
火野周平。作られし天才性。ようやく小峰先生の言いたいことに合点がいった。小説はともかく野球の話となれば、すんなりと分かる。
北海道ガンナーズの球団副社長である立花氏の会見以来、民放番組もネット界隈のニュースも火野周平の話題で持ち切りとなった。肘の違和感から二軍落ちしたされる火野の傷病経過よりも、火野周平は果たして〈作られた子供〉であるのかどうか、というのが話題の中心と化していた。
193㎝、95㎏の日本人離れした恵まれた体格。日本最速記録を樹立した162㎞の速球。投手と打者を兼任する二刀流。火野周平は日本プロ野球の誇る八十余年の歴史を鑑みても、過去に類例のない特異な存在である。特異なる存在は生まれからして特異な生まれ方をしたのではなかろうか。限りなく黒に近い灰色。そんな論調が大半を占めているようだった。
「小峰先生も、火野は作られた存在だって思ってるんですか」
山口は飲み終えた缶コーヒーを備え付けのゴミ箱に放り投げた。かつんと音がして、ひと気のない廊下に金属性の残響音がやけにもの悲しく響いた。
「そういう疑惑が持ち上がれば、考えなしの世間はとかく扇動されやすいからな」
学生時代から真摯に野球に打ち込んできたであろう火野周平に対して、その扱いはあまりに敬意を欠いているように思えた。能力値が高過ぎるゆえのやっかみや疑惑であるにしても、不当な言い掛かりであることは明らかである。眉目秀麗な芸能人の整形疑惑も同じロジックで語られがちだが、それとは根本的に違う。
整形手術には受診に際して大なり小なり本人の意思が介在するものが、〈作られた子供〉としてこの世に生を受けた人間には本人の意思など介在しない。生まれながらに特別な才能が備わっていたとして、そしてその才能が何らかの遺伝子操作による作為であったとして、火野周平に何の咎があるというのか。
「物語の最後で」
小峰先生がスチール缶を握り潰した。
「アルジャーノンは死に、チャーリイにかかっていた魔法が解ける」
小峰先生が放った空き缶はゴミ箱の縁に当たって跳ね返り、男子トイレの前まで転がっていった。山口はそれを片手で拾い上げ、空き缶の山で溢れそうなゴミ箱の上に静かにそっと積んだ。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら