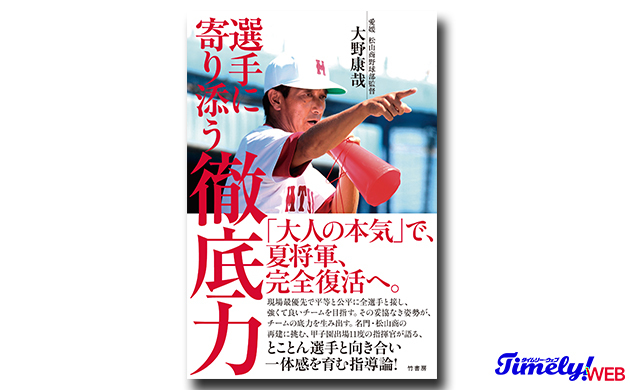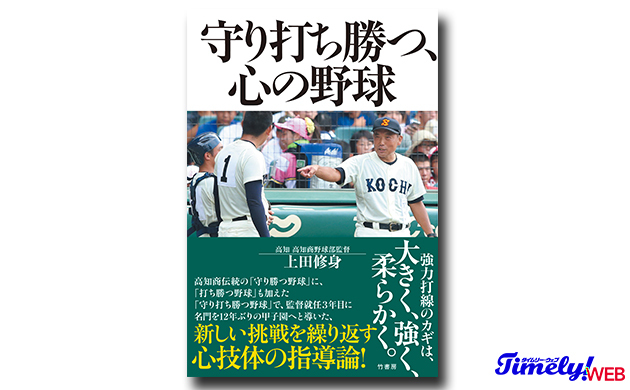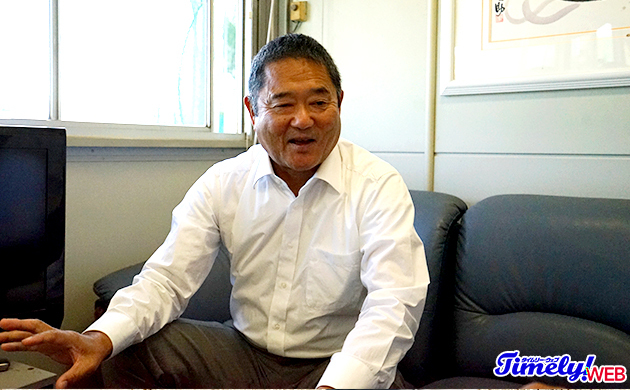〜第8回〜
山口俊司は前日の夜に録画しておいた野球中継をつけた。
北海道ガンナーズ対東京セインツの交流戦第二試合の先発を任されたのは世良だった。試合結果はネットニュースの速報で既に知っている。世良は三回持たずに八失点して降板し、今季勝ち星なしで六敗目を喫した。世良が無期限の二軍落ちを通告される契機となった試合である。
山口はリモコンを操作して、お目当ての場面まで早送りした。
「さあ、いらっしゃい。セリー」
そんな頓狂な声がテレビから聞こえてくるような気がした。
二回裏二死一、三塁、スコアは一対五でホームの東京セインツがリードしている場面だった。右バッターボックスに入った水原隼人が左手の人差し指をくいくいと動かして、マウンド上の世良正志を挑発するような仕草をした。緋ノ宮高校の同級生対決である。
高卒七年目の水原は常勝セインツの押しも押されぬ三番打者へと成長していた。昨オフに年棒二億円プレイヤーの仲間入りを果たした登り竜である。相変わらず守備での凡ミスは多く、塁に出たら出たで自らの走力を過信しての盗塁死も少なくない。そこらへんは高校時代から変わらぬお茶目な点である。こんな雑なプレイをしていながら二億円も稼げるのかと、山口としてはいろいろと納得しかねる部分も多い。俺の給料、何年分だと。
だが、水原のインコースを捌く技術は球界随一との評価もあるほど内角球にはめっぽう強い。ここ一、二年で右方向にも長打を打てるようになってきており、より穴の少ない打者へと近付きつつある。加えて、元来の空気を読めない性格からなのか、チャンスの場面でよく打った。何よりも水原が打つと球場全体が湧くのだ。現在はチーム事情から三番を打っているが、核弾頭役として一番に座っている方が適任だろう。
瞬間湯沸かし器と評されるほど短気な性格で、結果の出ない若手選手を数試合で見限ることで有名な岡田監督が珍しく我慢して使い続けたのが水原だった。
テレビ画面には世良の投じた落ち切らないフォークを、水原が強引に引っ張ってレフトスタンド中段まで運んだ場面が映し出されていた。
相変わらず空気読めねえやつだよ、お前。かつての盟友に引導渡してどうすんだよ。山口は、悠然とベースを一周する水原に向かって毒づいた。
「それにしても酷いな」
山口は被弾した場面をもう一度巻き戻しながら呟いた。世良がプロ入りしてからのピッチングをじっくり見たのは久しぶりだった。パ・リーグの試合は全国中継がほとんどないため、有料チャンネルにでも加入しない限り試合のハイライトではなく一球一球の投球映像を目にする機会は乏しい。
久方ぶりに目にした世良の投球動作はどこかぎこちなく、余計な力が入っているように見えた。全体的に投げ急いでいる感じがする。思わず見惚れてしまうような、高校時代の滑らかなフォームは完全に失われていた。
テレビ画面を通して見る世良のピッチングフォームは、出来の悪いロボットを思わせるぎこちない手投げに変貌していた。山口のよく知る世良の姿とはおよそかけ離れたものだった。
高校時代の世良は本当に楽しそうだった。心の底からピッチングを楽しんでいる、まさしく野球少年の顔だった。打たれた時でさえ「ああ、巧く打たれたなあ」とバッターを素直に褒めるかのように目を細めていた。そう、打たれた時でさえ楽しそうだったのだ。
それがどうだ。プロに入ってからの姿は悲壮感の塊である。
まずもってリズムが悪い。そのために自軍の打者からの援護点は極端に少ないものとなっていた。それはそうだろう。守備に就く時間が長ければ長いほど、切り替えて攻撃に移る意欲は削がれるのも当然だ。プロ入り後フォークの落差はいくぶんか増したようだが、その分球速は落ちているようだ。直球との違いを簡単に見極められるので、カウントを悪くして、苦し紛れにカウントを取りにいっては痛打されるというのがお決まりのパターンと化していた。ときおりピンポン玉のように軽々とスタンドまで運ばれた。
こんなはずじゃない。これは俺が思い描いたボールじゃない。世良はきっと内心でそう思っているはずだ。
果たして何が世良を狂わせたのか。
口の悪い専門家は、高校時代が世良の全盛期だったと吹聴した。確かに、高校時代の世良は構えたミットの位置を動かす必要さえなかった。まさしく精密機械のような正確さで、黙々と山口のミット目がけて切れのあるボールを放っていた。
その美しい姿は数年の時を経て完全に色褪せてしまった。直球は上ずって高めに浮き、コーナーを狙った球はシュート回転して打ち頃の球となった。プロ入り後の世良の投球からは高校時代を彷彿とさせるような躍動感がすっかり失われていた。
「なあ、世良。お前ほんとうにもう限界なのかよ」
明かりすら点けていない薄暗い自室で、テレビ画面に映る世良に向かって呟いた。
小さな身体を燃焼しつくすように。
一球投げる毎に選手生命の終わりが近づいてくるかのように。
そうして世良は全てを成し遂げた。高校生活を終えた段階で、世良の小さな身体にはプロの世界に向かうエネルギーは残されていなかったのかもしれない。
そんなあいつを俺が引きとめた。
大学でも一緒にやろうと。プロに行くのはそれからだっていいじゃないかと。
タンクにはもう燃料が残されていないように思えたから。頂点を極めて、なにもかも空っぽになってしまったように見えたから。
後から振り返れば、そんなのはたんなる女々しい口実だってことは、とっくに自覚していた。プロになるような才覚に恵まれない自分が、共に闘った天才が遠くの世界に行ってしまうのに嫉妬しただけだ。
一足先にプロ入りしたチームメイトの水原隼人はリーグを代表する遊撃手となり、決勝を闘った田仲将雄は百五十億円もの巨額の契約を手にして海を渡った。
緋ノ宮学園の後輩でもある六歳年下の火野周平には、実力で大きく水を開けられ、肝心の人気面でも追い抜かれたともっぱらの評判である。
世良正志の存在感は日に日に薄くなるばかりだった。
世良に四年間も回り道をさせてしまったという後悔が尽きる日はなかった。
七年前のあの日にもし時間を巻き戻せるとしたら、俺は世良に何と言うべきだったのだろうか。山口はただそればかりを考えて生きてきた。
高校時点でプロ入りしていたならば、田仲クラスとはいわないまでも、水原レベルの活躍はしていただろう。だからこそ、今の世良の姿を見ると歯痒い思いがした。
世良の目下の悩みはどうしたらプロで通用するかであるが、世界最高峰たるメジャーリーグへと活躍の場を移した田仲レベルともなると、どうやって相手を制圧するかである。そもそもからして悩みの次元が違うのだ。
七年前の世良であれば、そんな高みまで行けたはずなのだ。
あの頃の世良は、まさしく選ばれし民だったのだから。その天才の芽を、俺という凡人の一言が摘んだのだ。許されるはずもない。
山口はそんな負い目をどうにかして紛らわせるかのように、世良が水原隼人に被弾した場面を繰り返し、繰り返し何度も録画を巻き戻して見ていた。
当然、何度見てもホームランを打たれるという結論が変わることはなかった。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら