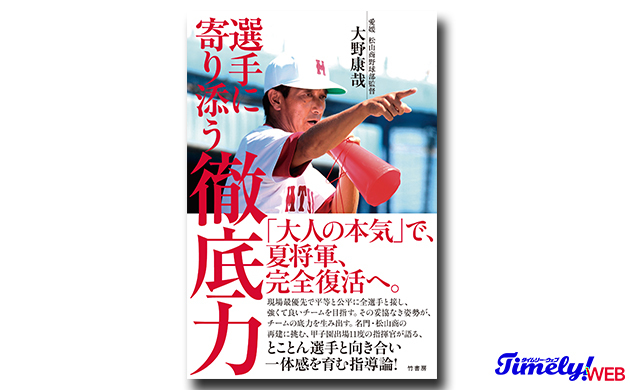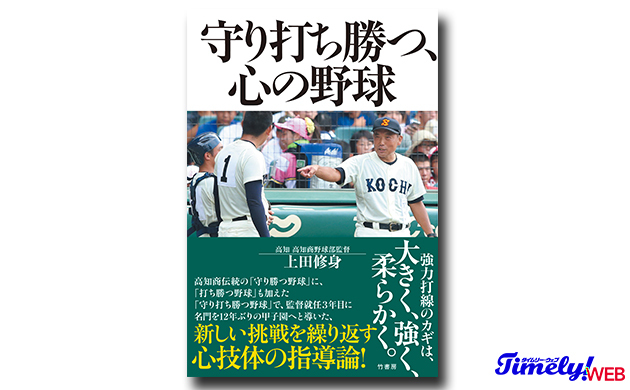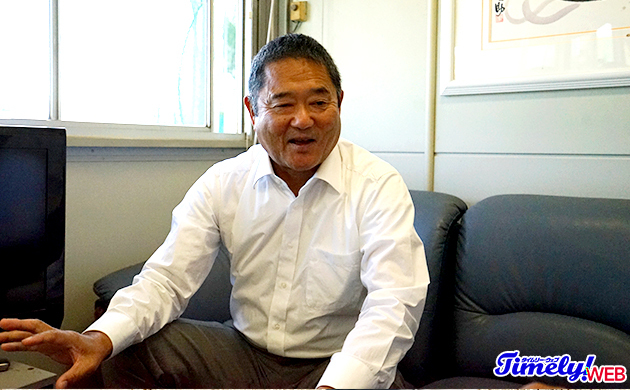〜第2回〜
熱気の冷めやらぬロッカールームで帰り支度をしていた世良に、山口が声をかけた。
「なあ。最後の球、あれ何投げたんだ」
俯いてスパイクの紐を緩めていた世良が顔を上げた。なんとなく不思議そうな表情を浮かべている。
「えっ、フォークのつもりだけど」
「いや、今までに見たことない軌道だったんだ。途中までは完璧なストレートだった。速さも、軌道もな。それが最後に小さく、鋭く沈んだんだ」
「握りそこなって変な回転したのかな」
世良は頭を掻いて苦笑いした。ま、この際どうでもいいか。三振も取れたし、結果オーライで万々歳だったしな。
「ようよう、どうした黄金バッテリー。辛気臭い顔して。二人ともプロに行くからって、お別れするのが辛いのか?」
一番打者で遊撃手のムードメーカー水原隼人が、山口に体当たりをかましつつ大声で話しかけてきた。チーム内でのあだ名は暴走超特急。相変わらず情緒の欠片もねえやつだ。ちょっとは甲子園優勝の味に浸らせろっつーの。
水原は「何だ、離婚するのがそんなに悲しいのか」といちいち騒がしい。成田離婚ならぬ、甲子園離婚だなー、などと囃している。
「俺は世良専属キャッチャーみたいなもんだから、プロの指名はないだろ」
多少の謙遜はあるものの、言葉自体に嘘はない。強肩は魅力だが、いかんせん打力に乏しいというのがプロ筋の山口評だ。叶うならば、世良と同じチームでまた闘いたいと思ってはいるが、プロの世界でやっていける程の実力が自分にあるとは到底思えなかった。
「ひょっとするとドラフト五位とか六位ぐらいで指名されるかもしれねーじゃんよ」
ちなみに俺は一位だろうけどな、と水原の予想はどこまでも楽観的だった。
「東京セインツに行きてーぞ、俺は!」水原が大声で叫んだ。東京セインツはリーグの盟主たる地位を欲しいままにする老舗の人気球団であり、礼儀作法や上下関係にも厳しいと聞く。
山口は、プロ志望を大会前から公言していた水原に釘を刺した。
「ミズ、お前が『セインツは常に紳士たれ』の精神を守れるとは到底思えねえけど」
山口の冷めた意見に水原は分かりやすくうろたえた。
さっきまでの威勢のよい発言は一気にトーンダウンしたようである。
「じゃあ俺、ガンナーズで我慢する」
北海道ガンナーズは去年のパ・リーグの覇者だ。活きの良い若手選手が多く、野球解説者出身の栗原監督は既成概念に囚われない柔軟な采配をふるうことで有名だった。チームカラーだけを見れば、水原は明らかにセインツよりもガンナーズ向きだろう。もちろん指名されれば、の話であるが。
「で、セリーはやっぱりプロ志望なんだよな?」
水原は世良をなぜだかセリーと呼ぶ。チームメイトは誰もその名で呼ばないが、水原本人は響きが気に入ってるらしい。世良正志はいつものように曖昧に微笑んでいた。
「うん、まだ考え中」
世良の返事を聞くなり、水原はオーマイガーとでも言いだしそうな外人ばりのオーバーリアクションをした。慣れていることだが、やはり少しウザい。いや、相当にウザい。
「はあ、ほんとにセリーは山口ラブだよなー。なんつーの、精神的双子?」 水原の好奇の目が山口に向いた。
「で、愛しのヤマはどうなさるおつもり?」
「ふつうに大学に進学するよ。四年間鍛えて、プロになれる実力かどうか見極める」
山口の堅実な人生設計に、水原が驚きの声を上げた。
「おう、さすが石橋を叩いても渡らない堅実派キャッチャー。イカしたリードだぜ」
うるせえ、堅実なリードは後天的な学習だ。山口は内心で毒づく。
「ヤマが進学するなら、僕も大学に行こうかな」
ぽつりと世良が言葉を漏らした。
「セリー、マジで? 今なら何球団が競合するか分からない売り時だぜ」
契約金一億円は確実だぜ、と水原が下世話な話をした。
「今プロに入っても通用しないと思うんだ。田仲みたいに身体も大きくないし、ストレートだって速くない。特別な決め球があるわけじゃないし……」
世良の自己分析はだいぶ評点か辛いようだった。
少なくとも、甲子園優勝投手のそれではない。
「いや、そーかもしれないけど。それでも優勝できたじゃん、俺たち」
「うん、だから全部ヤマのお陰だ」
世良は捕手冥利に尽きる泣かせる言葉を吐いた。本当に、素直で良いやつだよ、お前。山口はタオルで顔を拭くふりをして、零れたひと筋の涙を拭った。汗などとうに乾いていた。
「残念だぜ、セリー。じゃあ四年後プロで会おうぜ、アディオス・ブラザー」
ハードボイルドを気取ったのか、水原は二本指で敬礼のポーズをとった。何だ、そりゃ。世界のイチローか? お前がやると、ぜんぜん絵にならねえな。イチローはやはり偉大だ。
驚くほど様にならない間抜けなポーズだったが、山口俊司も手に持ったタオルを大きく左右に振って答えた。
「俺も楽しかったぜ、ブラザー」
能天気な一番バッターに幸多からんことを願って乾杯だ。プロで待ってろ、この野郎。
(著者:神原月人)
バックナンバーはこちら
電子書籍での購入はこちら