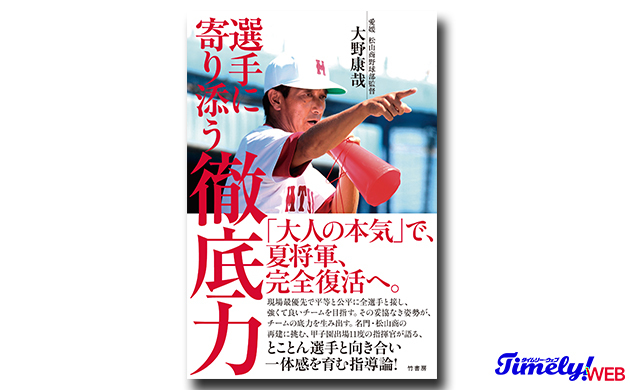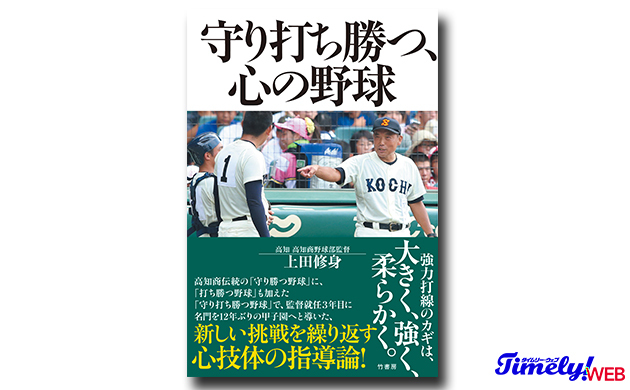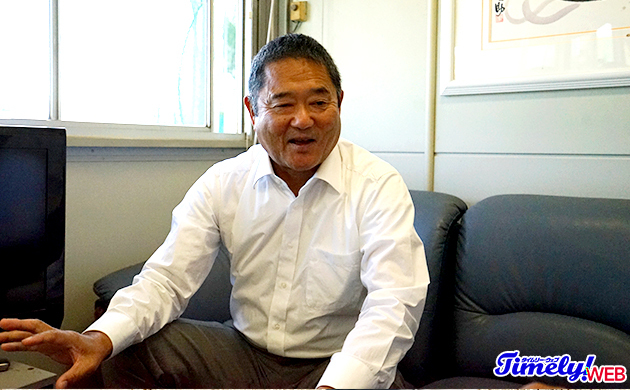〜第40回〜
一足先に舞い戻ってきた男が待ち望む、真のエースはいつ戻るのであろうか。
火野周平の投手としての復帰が待ち遠しい限りである。
山口はかつての同胞のコラムを読み終え、ぱらぱらとグラビアページをめくっていると、缶コーヒーを二本手にした小峰先生が戻ってきた。
職員室の階下にある自販機で調達したのであろう。
「おう、読んだか?」
缶コーヒーを投げて渡しながら、山口に感想を求めた。
コーヒーを受け取った山口は週刊誌を机の上に置いた。
「ええ、読みました。三島のやつ、あんな虫も殺さないような顔して、しれっとエグいこと書いてますよね。『廃車寸前のポンコツ』だとか」
プルタブを開け、缶コーヒーを飲みながら小峰先生が柔和に笑った。
「ま、技術論をさらっと印象論にすり替えるあたりは巧いよな」
小峰先生は、さすがに国語教師らしい着眼であった。
確かに、ポップスがどうだとかクラシックがどうだとかは、野球解説者が用いるような表現ではない。技術を語れないから印象論に話をすり替えて誤魔化す。
つまりは騙しのテクニック。これぞ配球の妙というやつか。
「では、専門家の先生に技術的な解説をお願いしましょうか。世良は、どこがどんな風に変わったんだ?」
専門家か。それもまあ悪い気はしない。
「スポーツニュースのハイライトでしか見てないから、細かいとこまでは分かんないすよ」
山口はそう言い置きしてから、ピッチングの解説を始めた。
「特に変わったのはプレートを踏む位置ですかね。今まで三塁寄りだったのが、ぐっと一塁寄りになってました」
「へえ、それでなんか変わるのか?」
小峰先生が興味深そうな顔をした。
「マウンドから見える風景は確実に変わるでしょうね。従来右打席に立っていたバッターが左打席に立つぐらいの違いまではないでしょうけど、感覚的にはそれぐらいの差があるかもしれません」
山口も缶コーヒーのプルタブを開けて、一口飲んだ。
「ま、俺はピッチャーじゃないので、実際のところは分からないですけど」
どちらかといえばブラックが好みだが、甘ったるいのも嫌いではない。
ありがたく頂戴することにする。
「あと、決め球にスプリットを投げるようになったみたいですね。甲子園の決勝で最後の一球にたまたま投げたボールの軌道と酷似してるんですけど、意図的に投げれるようになったのがデカいっすね。カウント球にも使えますし、見せ球にも使えますから」
小峰先生は「あー、マー君スプリットね」と納得したような声を上げた。
海を渡った田仲将雄の代名詞スプリット。もちろん世良のそれはあんなにえげつなく沈まないが、ストレートとの球速差が少ないためボール一個分ぐらい落ちれば十分と言える。
加えて、高校時代から投げていた横滑りするスライダーの曲がり幅を小さくした球種としてカットボールも覚えたようだ。俗に言うカッター。これも直球とほぼ同じようなスピードでボール一個ほど横にズレるのでバットの芯を外すのに極めて有効だ。
左打者のインサイドに向かって食い込む変化をするので、対左用に威力を発揮する。
「高校、大学時代はピンポイントの制球だけで勝負していたんですけど、今はそれにボール一個分ズラすっていう技が加わったみたいです。打者としては手元でボールが微妙に動くのって嫌なもんですからね。球が手元で動くっていうのが念頭にあると、普通のストレートが来ても、変化しないことによって逆に打ち損じるってこともありますし」
山口の解説に「ふーん、プロっていろいろ考えるんだなあ」と曖昧な返事をした。
無論、そういう微妙な反応になるのは致し方ないだろう。実際にバッターボックスに立ってみなければ、ボール一個の変化などささやかな違いでしかない。
だがプロともなれば、ボール一個、究極ボール半個分の変化を自在に操ることが要求される世界だ。その精度の差が生死を分けるといっても過言ではない。見ている以上に繊細な職人芸の領域なのである。それは口で説明したところで分かるものではないだろう。
「すげえ世界で戦ってるんですよ、世良は」
山口はコーヒーを片手に、しみじみとそう呟いた。
「いろいろマイナーチェンジはしてますけど、悲壮感が消えたっていうのが一番かと」
結局は三島が書いたような印象論だが、マウンド上での自信なさげな表情がなくなったこと。唐突な変身の理由はそれに尽きる。技術的には高校時代の延長でしかなく、高校時代からもともと出来ていたことをプロでもやっているだけに過ぎない。
三島は忘れ去られた男が帰還したと書いたが、自分自身の姿を忘れていたのは世良本人も同様だ。プロ入りして、もがき、試行錯誤する中で自分の姿をすっかり忘却した。
それが、プロ三年目も半ばを過ぎて元ある姿をやっと思い出した。マウンド上での表情の変化が、何よりも雄弁に物語っているではないか。
活躍に理由があるとすれば、技術云々よりも精神面での充実が理由であろう。
その意味からすれば、作家の目はきっと正しい。
「この記事、貰っていいすかね?」
山口が机の上に置かれた週刊パトスを指差した。小峰先生が顎をしゃくる。
どうやら「持っていけ」という意味であるらしい。
復活を記した記念碑として、大事にコレクションしよう。
ほとばしる熱いパトス。
それはきっと、マウンド上だけでなく、生きる上で、もっとも重要な要素であるのかもしれない。
三島シンジが寄稿した「週刊パトス」へのコラムは、当初は読みきりの予定であったはずが、いつのまにか連載コラムと化していた。
(著者:神原月人)